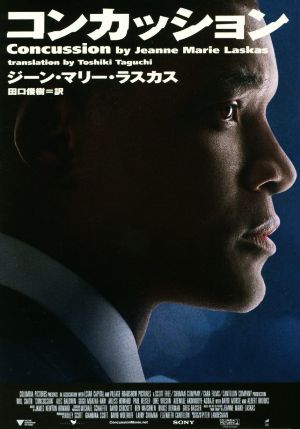
- 新品
- 書籍
- 文庫
- 1225-12-08
コンカッション 小学館文庫
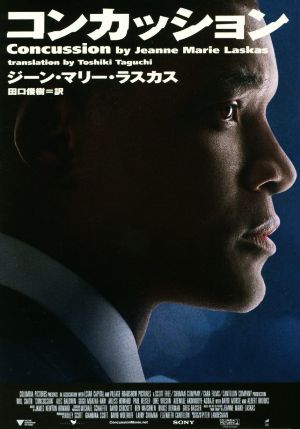
913円
獲得ポイント8P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 小学館 |
| 発売年月日 | 2016/04/06 |
| JAN | 9784094062809 |
- 書籍
- 文庫
コンカッション
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
コンカッション
¥913
在庫なし
商品レビュー
4.5
2件のお客様レビュー
コンカッションとは脳震盪の意味。ナイジェリア移民のピッツバーグの検死医のノンフィクション・ストーリー。アメリカン・フットボール選手が、プレー中の度重なる衝撃からアルツハイマー症候群を発症することを発見する。NFLの組織的な隠蔽・サボタージュに屈せず真実を追求する。ウィル・スミス主...
コンカッションとは脳震盪の意味。ナイジェリア移民のピッツバーグの検死医のノンフィクション・ストーリー。アメリカン・フットボール選手が、プレー中の度重なる衝撃からアルツハイマー症候群を発症することを発見する。NFLの組織的な隠蔽・サボタージュに屈せず真実を追求する。ウィル・スミス主演の映画の原作。 衰退した鉄鋼の街であるピッツバーグの歴史、ナイジェリアの内戦の話、主人公オマルの長年の鬱病との闘病記、オマルのナイジェリアと米国の家族の物語、というストーリーが複層的に重なっており、まったく飽きない。 東京→京都→大阪→DC→ダラス→NYの移動中に読破。
Posted by 
タイトルの『コンカッション』とは「脳震盪」のことだ。NFL(全米アメリカンフットボールリーグ)におけるプレー時の衝撃がプレイヤーの脳に与える影響をひとりの医師が究明していく過程を描いたものだ。 主題はふたつ。ひとつはNFLという大きなスポーツビジネスにおける致命的な脳神経系にお...
タイトルの『コンカッション』とは「脳震盪」のことだ。NFL(全米アメリカンフットボールリーグ)におけるプレー時の衝撃がプレイヤーの脳に与える影響をひとりの医師が究明していく過程を描いたものだ。 主題はふたつ。ひとつはNFLという大きなスポーツビジネスにおける致命的な脳神経系における健康障害の実態。もうひとつは、ナイジェリア生まれの医師で、それがゆえに被ったであろう差別や不利益を産む現実。そして、このふたつに関してビジネス利権を背景にした不誠実な圧力が絡んでくることになる。 読書前に期待していたのは後者のストーリーよりも前者の現実や危険性や対策についての科学的な分析や知見であった。そういう意味では映画化の原作であることも理由であろうが、後者に重きを置いているところは若干不満が残った。またノンフィクションとしての出来を問うのであれば、NFL側について不誠実な対応をすることとなった科学者たちへのインタビューなどが必要であろう。 それにしても、元プロボクサーの言動や調子がおかしいことをもはや笑うべきではないのだと思う。脳の繊細さを知るとともに、脳の可塑性に着目したリハビリ技術の向上にも期待したい。 しかし、おそらくはほとんどの日本人がコンカッション(Concussion)が脳震盪のことだとはわからないのではないか。さらに言うと、そのタイトルからはNFLのプロスポーツにおける身体障害の危険についての警鐘というテーマが伝わらない。原題含めて「NFL」や「アメフト」という名前やそれを示唆するタイトルをつけることは難しかったのではという勘繰るのはうがちすぎなのだろうか。いずれにせよ、映画のタイトルにもなっているので仕方がないのかもしれないが、本としてのタイトルには工夫の余地があるのではと思う。 --- この本の主人公でもあるBennet Omaluが次のような本を出している - ”Play Hard, Die Young: Football Dementia, Depression, and Death”。どうやら日本語化の予定はないようだけれど読んでみたい本だ。
Posted by 



