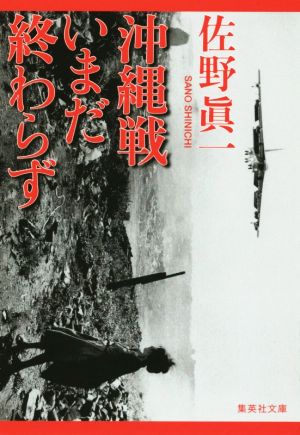
- 新品
- 書籍
- 文庫
- 1224-26-01
沖縄戦いまだ終わらず 集英社文庫
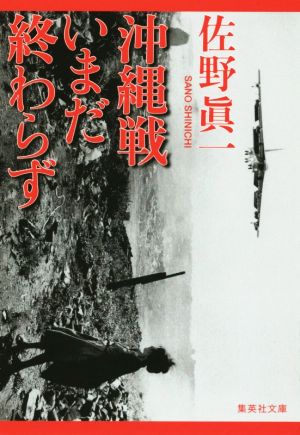
792円
獲得ポイント7P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 集英社 |
| 発売年月日 | 2015/05/20 |
| JAN | 9784087453188 |
- 書籍
- 文庫
沖縄戦いまだ終わらず
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
沖縄戦いまだ終わらず
¥792
在庫なし
商品レビュー
4.3
6件のお客様レビュー
米軍側の従軍記者をして「醜さの極致」と言わしめるほどの悲惨さを極めた沖縄戦。両親や兄弟を目の前で失いながらも過酷な戦場を生き延び、戦後もたった一人で生きていかざるを得なかった、かつての子供たちの証言。 本書はノンフィクション作家、佐野眞一氏が著した『沖縄 だれにも書かれた...
米軍側の従軍記者をして「醜さの極致」と言わしめるほどの悲惨さを極めた沖縄戦。両親や兄弟を目の前で失いながらも過酷な戦場を生き延び、戦後もたった一人で生きていかざるを得なかった、かつての子供たちの証言。 本書はノンフィクション作家、佐野眞一氏が著した『沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史』という本の続編的な位置づけになっているのだそうです。 太平洋戦争(もしくは大東亜戦争)末期、日本本土で本格的な地上戦が行われた沖縄。米軍側の従軍記者をして「醜さの極致」と言わしめるほどの凄惨な戦いを生き延びたかつての子供たちが長年封印していたその目で見てきた出来事を筆者に語っております。 僕がこの問題を初めて知ることになったのは以前放送していたNHKのETV特集で放送されていたシリーズ番組の『沖縄戦 心の傷~戦後67年 初の大規模調査~』を偶然とはいえ、見たことからでありました。 そこで彼らの口から出たことは本書で筆者に語られていることとほぼ同様のすさまじい話で、日本軍による住民虐殺や、自身が戦火を逃げ回ったこと。飢え。などでありました。 本書の中にもすさまじい話のオンパレードで中には祖母の腕を切り落としたという話や、軍人に毒入りミルクを飲まされたという話、『ウチナー口(沖縄地方の方言)』で話しているとスパイとみなされ、日本軍に殺されたという話などが延々と続き、ハイライトは自分の母親を石で撲殺したと語る神父の話でございました。 それらの悲劇は現在でも連綿と続いており、オスプレイがなぜ沖縄であれほど忌避反応を示すのか?沖縄全体の70%以上を占める米軍基地。そして現在でも起こる米兵による沖縄陣女性への集団レイプ事件…。佐藤優氏(彼の母親は沖縄出身)がよく 『沖縄が日本から離れつつある。これは民族問題の初期段階だ』 と警告を発している理由がよく分かりました。 そして、戦場で見聞きしたものが何十年もPTSDという形でその人間の裡に巣食い、苦しめるのかということも同様でした。沖縄といえばまず思い浮かぶのは美しい島と海の風景ですが、その裏に隠されているこうした『悲劇』を決して忘れてはなりません。 ※追記 本書は2015年5月20日、集英から『沖縄戦いまだ終わらず (集英社文庫)』として改題、文庫化されました。佐野眞一氏は2022年9月26日、肺がんのため千葉県流山市内の病院で死去されました。75歳でした。この場をお借りして御冥福をお祈りいたします。
Posted by 
日本にとってアメリカは「宗主国」、沖縄は「植民地」、この言葉が深く頭に残る。まもなく沖縄戦が終結した6月23日を迎えることもあって読み直した。 本書を読まずとも沖縄が太平洋戦争終結後も基地問題や在日米軍による集団レイプ事件、そしてオスプレイ大学校内への墜落事故など沖縄には真の戦後...
日本にとってアメリカは「宗主国」、沖縄は「植民地」、この言葉が深く頭に残る。まもなく沖縄戦が終結した6月23日を迎えることもあって読み直した。 本書を読まずとも沖縄が太平洋戦争終結後も基地問題や在日米軍による集団レイプ事件、そしてオスプレイ大学校内への墜落事故など沖縄には真の戦後が訪れていない状況を多くの人が理解している。それと同時に中国の台湾や尖閣諸島、南シナ海への対外強行姿勢を目の当たりにし、日米安保、米国の庇護・抑止力なしに平和の均衡が保たれないリスクも理解している。未だ戦後の訪れない沖縄について、誰も明確な答えは出せないのではないだろうか。 本書はノンフィクション作家である筆者の沖縄戦に始まる様々な傷を負った当事者たちへのインタビューによって構成される。 現状の沖縄経済の基地依存度は低いとは言うものの、それに頼らざるを得ない人々。自ら意思表示できない様な0歳児すら、準軍属扱いにし靖国に祀るとともに遺族年金をばら撒く国と基地のあり方。集団自決に追い込まれ、家族にすら手をかけても「生き延びてしまった」人々の苦しみ。戦争で身寄りを失い、戦後もアメリカ軍のゴミの山を漁らざるを得ない戦争孤児たち。その孤児院での生活と孤独に苛まれるその後の人生。 それら様々な傷を負った人々に直接インタビューした数は膨大な量に及んでいる。特に自決の中から生き延びることのできた人々を近年まで癒えないPTSDなど、その心に負った傷は深く生々しいものだ。多くの書籍でそうした沖縄県民の悲惨さを読んできたが、本書の多くの声からは再び胸の辺りを掻きむしる様な、胃液が昇ってくるような惨状を思い起こさせる。 なぜ人と人がこれ程までに闘い、そして身内を手にかける程に残酷になれるのか。子を想い親を想い兄弟姉妹を想い、再びあの世で逢おうと約束して散っていく人々。その魂は靖国にいるのか、それとも沖縄の地の底にまだ埋まっているのか。 平和な時代に生まれながらも、未だ危険と隣り合わせ、国内の基地のほとんどを抱えた沖縄。冒頭に書いた「植民地」と言う言葉が頭から離れない。 本書最終章では英国とスコットランド間に見られる独立闘争の歴史にも触れる。日本国民として沖縄が離れていくのは見たくないが、そうした現実に触れて生きる沖縄県民が総意として独立を望んだ時、自分は反対できるだろうか。 今まさに緊迫する世界情勢を見ながら、沖縄と言うかつて琉球王国と呼ばれた場所を想いながら深く考えさせられる書籍だ。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2015年(初出2012~13年)刊。 沖縄戦や集団自決、米軍基地など現代沖縄問題と戦争との関連を述べた著作は少なくない。しかし、定点に「戦災孤児」を据えつつ、その孤児のみならず、孤児視点の沖縄戦や現代的影響を多面的に検討する書は多くはなさそう。 そんな特徴を有しているのが本書だ。 とは言うものの、如何なる視座でも、戦争被害や集団自決、基地問題は勿論、靖国合祀、遺族年金や弔慰金問題、ヘイトスピーチなどは相互に絡みあっており、本書からもこの事実を窺い得ることは難しくない。 他方、現代特有の問題意識は体験者の死亡による記憶の風化である。そんな中、本書のような一問一答式の記録の価値はますます高まりそうだ。 内容面では、 ① 靖国合祀の拒絶は、遺族年金の受給如何により事実上封じられている点(本来、年金受給権と信仰問題とは次元が違い、扱いを異にしなければならないはずだが)、 ② 戦災孤児のPTSD的後遺症、 ③ 親を失った孤児よりも、子を失った親の方が手厚い年金制度。これは是か否か。 ④ こういう仕打ちが、感情的に沖縄独立へと向かう住民意識の醸成へ。 ⑤ 返還前は借地料50億円しか生み出さなかった那覇新都心の経済効果は年600とも700億円とも。 そもそも基地依存の沖縄経済というのは認識不足。より言えば幻想の領域にある可能性。 そんな中でも、とりわけ ⑥ 集団自決の強要によって家族を殺さざるを得なかった戦災孤児の慟哭と悔恨の証言が痛く刺さる。
Posted by 



