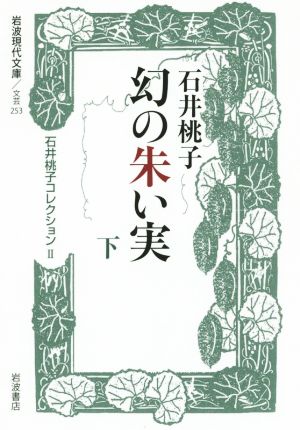

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2015/02/01 |
| JAN | 9784006022532 |
- 書籍
- 文庫
石井桃子コレクション(Ⅱ)
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
石井桃子コレクション(Ⅱ)
¥1,342
在庫あり
商品レビュー
4.1
9件のお客様レビュー
社会に出て間もない女性がひょんなことから同世代の同性と知り合い親友になる。自分の結婚や親族の介護などを経ながらも親友とはお互いに欠けがいのない存在になる程親交を深めるが、病弱な親友は若くして亡くなってしまう。その親友が、自分には見せなかった面でどんな生き様でどんな思いを抱いていた...
社会に出て間もない女性がひょんなことから同世代の同性と知り合い親友になる。自分の結婚や親族の介護などを経ながらも親友とはお互いに欠けがいのない存在になる程親交を深めるが、病弱な親友は若くして亡くなってしまう。その親友が、自分には見せなかった面でどんな生き様でどんな思いを抱いていたのかということを、数十年後、年老いてから当時の手紙などをひっくり返しながら振り返り回想するという、石井桃子さんの自伝的小説。 私の妻にとってはそういう親友は誰だろうか、とか、私の大学時代の仲間内にもそういう親友同士の女性たちならではの絆があるだろうなとか、いろいろ思い起こされて、胸が熱くなる小説だった。 親友だとしても、親友だからこそ、見せない一面がある。 それでも相手の存在は必須だし、相手を思う気持ちは誰よりも強い。そんな関係って大切だよなと思う。 自分にとってそんな存在は誰だろう、いるだろうか、いたとして、自分は相手の見えない一面まで理解に努めた経験があるだろうか、とも思った。 児童文学に興味を持って、それに多大な貢献をした石井桃子さんてどんな人だろうか、という動機で読んでみた。 当然といえば当然だけど、児童文学で知られた方にも大人の人生がある、でもその反面、いつまでも若い頃の思いを大事にされている素敵な方なんだなと思った。 プーさんの翻訳は病床の親友を楽しませるために行なっていたと知って、改めて読んでみようと思った。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
昭和初期、戦前戦後の時代を生きた人のその時の感覚が伝わるような、それでいて読み易い物語が読みたいなぁと探して、一か八かで上下巻買ってみたら、ドンピシャで好みに合うお話でした。 石井桃子さんの筆致好きだ、もっと読みたい!と思ったら小説はこれだけなのね。70〜80代で書かれた作品なんて…まだまだその年でも習熟していくことがあるのね、と驚いた。40代の自分はもうこれから先はいろんな意味で下り坂だろうと思いがちだったけど、本人次第だわ。 好き合って結婚したとしても、嫁いだが故の不自由さ、憤りを明子が感じるあたりが本当にリアル。萩尾望都の『10月の少女たち』という短編に通じるものも。どこか、こうなるとわかっていても大人になるために受け入れざるを得ないことのように、結婚という選択肢を選ぶ。明子の場合は、蕗子以外の居場所をつくらなければ、ということがきっと心のどこかにあった。もちろん新たな人間関係で得られる部分もあるんだけど。現代を生きる多くの人にも十分共感できる部分だと思う。 『何者かが、ただひと言、あの世へのみやげに持たしてやるといったら、「愛している」という、日本語としてはなじめない言葉をいうしかないと思っていた』 蕗子と明子はもう本当に理屈ではない、唯一無二の関係なのね。こんな人と巡り会えて羨ましいとしか思えない。 上の台詞を明子は蕗子に言えなかった。そして、命が入れ替わるように子を授かった。 明子と蕗子の掛け合いの様子を実写で見てみたいなぁ…。俳優さんは、最近の若い人はよく知らないから、蕗子には20代くらいの仲間由紀恵さんがなんとなく頭に浮かぶ。明子は誰だろう…第三部の頃だったら、最近の倍賞千恵子さんかな。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この本を読んでいたのは一年前なのだが、今になっても響いてくることがある。図書館に返却してしまったのでうろ覚えだが、解説か何かで、石井桃子さんご自身が「明子は家庭を取ったことにより蕗子を捨てたのだと思っていただいても構わない」と仰っていた、と読んだ。これは、人生の出会いと別れを振り返って初めて言える、とても深い言葉ではないだろうか。 明子は最期まで蕗子との関係を断つことはないものの、いつでも好きなときに駆けつけるわけには到底いかなくなる。家庭をもつという選択をすること自体が、「家族」を優先する生き方を選択するということである。できるだけ全方位を大事にしようと努めることもできるかもしれないが、自立した一人の人であるならば、大事にしたい全ての人にくっついて生きるわけにはいかない。生きる道は皆いつか離れていくのであり、それでも自分の道を歩もうとすることは、明子のように、日常に紛れて意図せずとも実は取捨選択しているということをはらむ。 家庭は一つの例でしかないと思うが、これに限らず人間には、どうしても仕方のないことがある。生きるとはそういうこと。晩年の石井桃子さんが、自身の来し方やご友人へのどんな思いとともにこの小説を書かれたのかを想像すると、とても静謐な気持ちになった。
Posted by 



