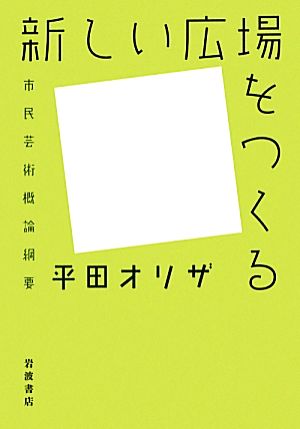- 書籍
- 書籍
新しい広場をつくる
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
新しい広場をつくる
¥2,310
在庫あり
商品レビュー
4.3
10件のお客様レビュー
(内容)演劇と都市の関係を論じている。 (文体)著者の体験に沿って言葉を選んでおり、共感しやすいという点で読みやすい。 (残るもの)芸術法や劇場法を作ってみせるという気概すごい、大卒資格の改善を実現したっていうところも強い。マジで、変えるために言い続けることを自分に課せられるって...
(内容)演劇と都市の関係を論じている。 (文体)著者の体験に沿って言葉を選んでおり、共感しやすいという点で読みやすい。 (残るもの)芸術法や劇場法を作ってみせるという気概すごい、大卒資格の改善を実現したっていうところも強い。マジで、変えるために言い続けることを自分に課せられるってすごい、こうなりたい。
Posted by 
著者は、劇作家、演出家、大学の先生。芸術を作るヒトである。読みながら、気がついたのは、日本のまちづくりには、広場がなかったということだ。 神社やお寺には、境内というのがあり、それが広場みたいであるが、みんなが集まるような広場がなかったということに、日本のまちづくりの特徴だったかも...
著者は、劇作家、演出家、大学の先生。芸術を作るヒトである。読みながら、気がついたのは、日本のまちづくりには、広場がなかったということだ。 神社やお寺には、境内というのがあり、それが広場みたいであるが、みんなが集まるような広場がなかったということに、日本のまちづくりの特徴だったかもしれない。中国の天安門広場なんぞは、実に大きく、人が集まれる。軍事パレードに使われるが、天安門事件みたいなことも起こした。広場は実に、重要だ。日本は公会堂というところが集会所になる。 本のまえがきは、宮沢賢治の『農民芸術概論要綱』の一節から始まる。「誰人もみな芸術家たる感受をなせ」という農民への呼びかけについて考察している。人は、みな芸術家なんだ。 「芸術なんて必要ない」「あんなものは、一部の特権階級の暇つぶしだ」という中で、社会の中での芸術の位置づけを明らかにしようとする。 芸術の役割は、①芸術そのものの役割。②コミュニティの維持や、再生のための役割。③教育、観光、医療、福祉など目に見える形で直接的に役立つ役割。それに、もう一つ「文化による社会的包摂」を加える。 「女川の獅子舞」から、共同体の在り方を考察する。農業は、農作業の中に、共同作業があり、そしてお祭りがある。地域ごとに、神社をベースにした祭りが、ライフスタイルに弾みをつけていた。日本的なモデルは、集団というチームプレーの良さが発揮されていた。稲作文化なんだろうね。 著者は、2012年の大阪の橋下府知事が、文楽を生まれて初めて観劇し、「つまらない。二度と観に行かない」と言って、文楽への補助金をカットする。まぁ。橋下らしい勘違い行為だ。 それは、世界遺産のバーミヤンの遺跡をタリバンが破壊した行為に似ているという。 個人が「つまらない」「わからない」ということで、知事が伝統芸能を絶やすことがいいのか?という問いかけもあって、芸術のあり様を問う。 文化資本は、三つの形態に分類されるという。①客体化された形態。②制度化された形態。資格など。③身体化された形態。①、②は、お金の力や本人の努力でなんとかなる。③身体化されたもの、礼儀作法、言葉使い、センス、美的性向は、子供の頃からの経験として積み重ねられるものだ。 東大生の文化資本の2極文化の問題。東大生になるには裕福な家庭でないと無理という客観的事実。如何なの優秀な子が、そこに飛び込んで、コンプレックスを感じてしまうほどの差があるということだ。結局「努力したら負け」という厳然たる事実。最近は、「親ガチャ」という言葉で語られる。 文化格差をどう是正するのか?を考察する。 1990年代以降、これまでの日本の強固な地縁・血縁型の社会、企業における社員旅行、社員慰安会、年功序列、企業年金などのシステムが崩壊することになった。いわゆる「無縁社会」である。 それに対して、排除する論理でなく、社会的な包摂が求められ、それが文化によるものになる。 阪神大震災、東関東大震災などを経験した中での社会包摂による復興というのが必要にもかかわらず、そのことが十分になされない。心の救済がないというあり方が大きな問題だとも指摘する。 著者は、劇場法に関わってきたので、そのことを意識して書かれている。日本には文化ホールがたくさんあるが、それが有効に使われていない。またその管理する人たちも、文化を愛していない人もいる。そういうことは、変える必要がある。もっと必要なことは、劇場が、創造と発信の場になることをだという。 この本を読みながら、あまり考えていなかった部分に光が当てられて、なるほどなぁと思うことが多かった。ヨーロッパの劇を中心とした文化政策と日本の置かれている劇の状況の格差は日本が今の時代に適応できないような気もした。創造の場を作ることが必要であり、創造する人材を育成することの方がもっと重要だと感じた。文化による社会包摂ができる社会が必要だ。
Posted by 
アートの価値がまともに受け取られていないこの社会と、その背景にある市場原理にたいする無策がよくわかる。 不況から回復できないのは、我々にとって、欲しいモノがなくなったからだという論は目からウロコだ。外資のiPhoneが最後か。 文化資本は市場原理のもとでは不要品として、かつて...
アートの価値がまともに受け取られていないこの社会と、その背景にある市場原理にたいする無策がよくわかる。 不況から回復できないのは、我々にとって、欲しいモノがなくなったからだという論は目からウロコだ。外資のiPhoneが最後か。 文化資本は市場原理のもとでは不要品として、かつての文楽のように、むしろ目の敵にされる。ということは地方都市に住んでいるとよくわかる。 AmazonやiTunesがあったとしても、そもそものインプットは与えられない
Posted by