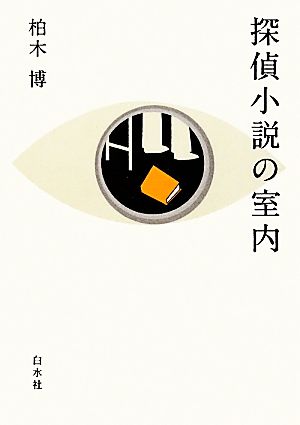商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 白水社 |
| 発売年月日 | 2011/02/25 |
| JAN | 9784560081150 |
- 書籍
- 書籍
探偵小説の室内
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
探偵小説の室内
¥2,640
在庫あり
商品レビュー
4
3件のお客様レビュー
後書きでも述べているけど,「探偵小説」と銘打っていながら取り合っているのは探偵小説以外の方が多くて,その点はちょっと期待はずれ.まあ,買う前に目次を見ていれば問題なかったのだけれど.
Posted by 
柏木博がこの32年間に共編著も含む35、6冊の著作で世に問うてきたのは、単なるデザインや物の歴史をひも解いたり、それらを総網羅的に概観するということではなく、それは1985年の『道具の政治学』や『肖像のなかの権力』(1987年)の書名が示すように、当初から現代批判および日常生活批...
柏木博がこの32年間に共編著も含む35、6冊の著作で世に問うてきたのは、単なるデザインや物の歴史をひも解いたり、それらを総網羅的に概観するということではなく、それは1985年の『道具の政治学』や『肖像のなかの権力』(1987年)の書名が示すように、当初から現代批判および日常生活批判だったはずだと私は思っています。 彼の言説から、日用品や消耗品などありとあらゆる物が、それこそ家具から玩具にいたるまで私たちの身のまわりの物すべてが、純朴なる美意識や美学で形作られたのではけっしてなく、それらはすべて政治的な意図によって作られているなどということを目にすると、たちまち昔ながらの左翼的偏向の眼と勘違いされそうですが、そうではなく彼はサブリミナル刺激によるマインドコントロールにも似た疑似支配・潜在的支配を指摘するのです(そこまで言ってなくて私の勝手な思い込みかもしれませんが)。 今年もすでに半年以上が過ぎてしまいましたけれど、1月末頃から小説家ではありませんが、私が高校生の頃から着目して読んできた4人の著者の著作を、たまたま偶然同じくして回顧する機会を得たのですが、その時、ただ自分で読んで再確認するだけでなく、ここでひとつ四方田犬彦が『ザ・グレーテスト・ヒッツ・オブ・平岡正明』という本で、平岡正明が1962年から2001年までに書いた百冊の本を紹介編集したことに倣って、自分も同じようなことをしてみようと思いつきました。 その4人とは、海野弘・柏木博・川本三郎・粉川哲夫ですが、そんなことを思っていた矢先に、柏木博の新しい傾向の新著が出ました。 この本の真の面白さは、もちろん分析されているその当の対象の小説を、その人自身がどれだけ想像力たくましく楽しんで読んだか読んでいないかで、天と地ほどに変わってきますが、でも、まったく読んでいなくても抜群に面白く楽しんで読めるのは、さすがただの学者然とした文筆家じゃない筆力のある彼ならではの力技です。 私はよく、架空じゃない実際の場所を舞台にした小説、それはミステリだけではなく恋愛小説でもですが、それを読むときに地図はもちろん時にはその描写されている場所の本物の写真をピックアップして読むことがあります。多くは推理小説の場合、情況がより鮮明になったり、殺されるまでの足取りが文章に不備でも現実に助けられたりとか、文字だけで読むより何らかのプラス・アルファがあって気に入っています。 私が思いもしないような視点ですが、おそらく建築家的な素養のある人なら、この本のような小説に描かれている人物と、部屋とか場所などの空間との関係性の熟考はあり得るのではないかとは思われますが、とても新鮮でワクワクしました。 ・・っと、ちょっと待って下さい、何だか急にモヤモヤしてきて、今、突然浮上してきました。 敬愛する柏木博にはたいへん申し訳ありませんが、こういう傾向の本、すでに1992年に出ているのを思い出しました。 高校生の頃に書店で発見して、ユニークなアプローチだと感心して読んだことがありました。 それは、広告ディレクターの小幡陽二郎と建築家の横島誠司による『名作文学に見る家』(「愛と家族」編と「謎とロマン」編の2冊刊行)というものです。たとえば後者は、宮沢賢治の『注文の多い料理店』からカフカの『変身』を経由して山口瞳の『江分利満氏の優雅な生活』まで全部で31冊の作品について、まるで妹尾河童の『河童が覗いたニッポン』のような手書きの部屋の間取り図がついて、一作に3~4頁ほどですが名作を圧縮した名解説という感じでした。 まったく思いがけないところへ飛んでいって自分でもびっくりしましたが、もちろん本書は本書で読み応えのあるすばらしい本にかわりはありません。
Posted by 
小説は、虚構である以上、意図をもって描かれているのは確かなわけで、描かれている「室内」から登場人物の性格や内面、生活スタイル、嗜好を読み解くというのはとりたてて目新しい視点ではないようにも思われる(失礼!)。 とはいえ、著者が主として依拠しているベンヤミンによれば、「室内」を意...
小説は、虚構である以上、意図をもって描かれているのは確かなわけで、描かれている「室内」から登場人物の性格や内面、生活スタイル、嗜好を読み解くというのはとりたてて目新しい視点ではないようにも思われる(失礼!)。 とはいえ、著者が主として依拠しているベンヤミンによれば、「室内」を意識したのは19世紀のブルジョワジーとのことで、そうであるならば、それ以前の人々にとっての「室内」は生活の痕跡ではあっても、内面を映したものではない(かもしれない)ということになる、という示唆は興味深い。 ともあれ、読後に、読み流してしまった小説の場面、ふと流してしまった映画のシーンをあれこれ思い出してみたくなる。
Posted by