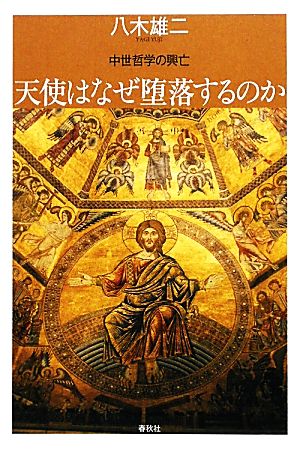

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 春秋社 |
| 発売年月日 | 2009/12/25 |
| JAN | 9784393323304 |
- 書籍
- 書籍
天使はなぜ堕落するのか
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
天使はなぜ堕落するのか
¥5,280
在庫あり
商品レビュー
4.6
7件のお客様レビュー
天使はなぜ堕落するのか―中世哲学の興亡 (和書)2011年01月27日 23:45 八木 雄二 春秋社 2009年12月22日 asahi.comで柄谷行人さんの書評を読んで知りました。 哲学と神学というものがどのように捉えられていたのか著者の悟性によって書かれている。 中...
天使はなぜ堕落するのか―中世哲学の興亡 (和書)2011年01月27日 23:45 八木 雄二 春秋社 2009年12月22日 asahi.comで柄谷行人さんの書評を読んで知りました。 哲学と神学というものがどのように捉えられていたのか著者の悟性によって書かれている。 中世というものの認識が読んで変わる作品でした。といってもこの本は入門編と言われているけど内容を正確に捉えることは僕にはできなかった。 でも近代というものと中世、古代というものが哲学によっているという指摘は面白く哲学というものを捉え直すことにとって良かった。
Posted by 
書名こそ宗教学の本のようだが、実は中世哲学史を新たな 側面から記述しようとした哲学史書である。中世における 哲学とはすべてキリスト教の名の元に展開されたので あるからこのような書名になるのは実は正しい。 今までは暗黒の時代とされ、哲学史的にも見るべきものが 少ないと思われ切り捨...
書名こそ宗教学の本のようだが、実は中世哲学史を新たな 側面から記述しようとした哲学史書である。中世における 哲学とはすべてキリスト教の名の元に展開されたので あるからこのような書名になるのは実は正しい。 今までは暗黒の時代とされ、哲学史的にも見るべきものが 少ないと思われ切り捨てられがちだった中世哲学と、その 偉大な成果に再び脚光を当てる、その端緒となる本なの だろう。確かに私は中世における哲学についてはまったくと 言っていいほど無知であった。この本で初めて目にした名前 も少なくなかったしね。まぁこの一冊を読んだだけで中世 哲学が頭に入るほどいい脳みそ持っているわけではないの だが(苦笑)。
Posted by 
私たちはなんとなく、西欧中世といえば「暗黒の時代」であり、中世哲学はなんだかよくわからない「煩瑣哲学」であるというある種偏見にも似たイメージを持っているのではないかということは否定できない。 しかし、本書を読んで蒙が啓かれた思いがした。中世とはそれ自体で完結した世界であり...
私たちはなんとなく、西欧中世といえば「暗黒の時代」であり、中世哲学はなんだかよくわからない「煩瑣哲学」であるというある種偏見にも似たイメージを持っているのではないかということは否定できない。 しかし、本書を読んで蒙が啓かれた思いがした。中世とはそれ自体で完結した世界であり、近代哲学の跳躍は中世哲学によって準備されていたのだ。本書を読んで、中世一流の哲学に比べれば、デカルトの『省察』など検討するに値しない大学の卒論レベルであるという著者の強気な言葉も宜なるかなと感得した。さだめし、デカルトやライプニッツなど近代哲学の巨星たちは中世哲学から直接的に多大な影響を受け、それらを応用発展させたに過ぎないのだろう。たとえば、アウグスティヌスの著作には「わたしは疑うゆえにわたしはあることは確実である」、同『神の国』において再度、「わたしが欺かれているなら、わたしは存在する」と述べている。つまりデカルトの「我思うゆえに我あり」という人口に膾炙している言葉より遥か千百数十年前に発見された概念だったのである。 さて、中世の哲学というのは信仰と密接に連関しており、両者は不可分のものであった。宗教と哲学が融合し、あらたに、神学という学問が創設されることと相成った。この流れは、真理性の探求という純粋科学的信条から発生したというよりもむしろ、政治的、宗教的理由によるところが大きい。当時、西ヨーロッパでは教育機関として教会がその主導権を独占していたが、世俗の大学が隆盛しそこで、哲学が教えられ力をつけていたからである。つまりキリスト教会の世界という完結した世界が壊される危険があったので多くの協会側の人間があせったのだ。哲学は理性の力によって、論理的に命題を吟味していく営みである。哲学に魅せられて続々と大学に集まった有能な若者たちを教会に留めおくためにも宗教の側も論理的に神の存在を、その合理性を明らかにする必要が生じた。これがいわゆる「神の存在証明」である。神の存在証明は当時いわば、タブーであり、非常に危険な試みであった。なぜなら神の存在など自明であって。信じることによってその存在は保証されているからである。とはいえ、前述のような現実に対処するため、信仰をかっこに入れて証明することでより神への理解が深まるものとして、正当化されたのであろう。
Posted by 



