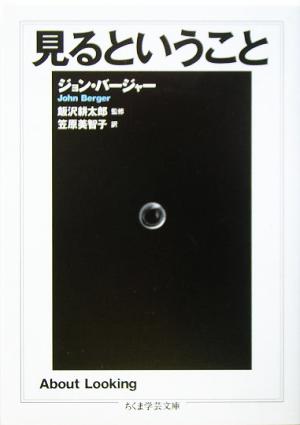
- 新品
- 書籍
- 文庫
- 1224-35-01
見るということ ちくま学芸文庫
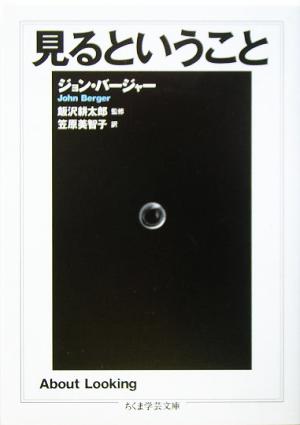
1,540円
獲得ポイント14P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2005/08/10 |
| JAN | 9784480089304 |
- 書籍
- 文庫
見るということ
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
見るということ
¥1,540
在庫なし
商品レビュー
3
6件のお客様レビュー
「イメージ」を読んだジョン・バージャーによる一冊。見るということに絡んだ様々な主題を扱っていた「イメージ」に対して、見るということから考えた美術評論集になっている。美術史・美術論にはそれほど詳しくない私だが、このバージャーの評論が影響大だったことは何となく想像がつく。逆に言えば、...
「イメージ」を読んだジョン・バージャーによる一冊。見るということに絡んだ様々な主題を扱っていた「イメージ」に対して、見るということから考えた美術評論集になっている。美術史・美術論にはそれほど詳しくない私だが、このバージャーの評論が影響大だったことは何となく想像がつく。逆に言えば、それくらいの理解しかできなかったということだ。図版も多く収録されているが、やはり作品を目の当たりにできるインターネット検索に大いにお世話になりました。
Posted by 
前半は哲学的な話で興味深かったが、後半は美術的な話で、作品のイメージなしに読み進めるのが困難だった。自分の教養のなさが大きいが。 特に、動物関連の話が興味深かった。 ・人間が動物を見るように動物も人間を見ていると人間は錯覚している。そこには埋められない隔たりがあり、それは言葉...
前半は哲学的な話で興味深かったが、後半は美術的な話で、作品のイメージなしに読み進めるのが困難だった。自分の教養のなさが大きいが。 特に、動物関連の話が興味深かった。 ・人間が動物を見るように動物も人間を見ていると人間は錯覚している。そこには埋められない隔たりがあり、それは言葉によるコミュニケーションが不可能なこと。 ・古来より動物は「たとえ」となるほど人間と深い関わりがあったが、現代では周縁化されている。動物園がその最たるもので、本物ではあるが本質の動物ではない ・ペットは飼い主の人生観が生み出した産物
Posted by 
以前、写真展で高値で取引される写真を観た。 ーかつて写真は自分が見た事実の一瞬を切り取って、大衆に伝える媒体としての存在だったように思う。決して動くことのない写真から、より多くの情報を取り込もうと注意深く隅々まで観察し、考察したことだろう。時は流れ、ビデオの登場で映像がそれに取っ...
以前、写真展で高値で取引される写真を観た。 ーかつて写真は自分が見た事実の一瞬を切り取って、大衆に伝える媒体としての存在だったように思う。決して動くことのない写真から、より多くの情報を取り込もうと注意深く隅々まで観察し、考察したことだろう。時は流れ、ビデオの登場で映像がそれに取って代わった。動きのある映像は人々に写真より強い印象を与え、内容を伝えることが容易になったーこれが、ぼくの写真に対するイメージだった。写真展の作品は、アートとしてだったり、当時の時代を切り取ったものなど、それぞれ意図を持って制作され、感覚でたまたま撮られたようなものはなかった。では、その作為的なモノを見るとはどういうことなのか。見ることで作者の、あるいは作品のなにを感じればよいのか。技術革新により、様々な媒体から表面的な情報を読み取ることは簡単なことになった。たしかに情報量は増えたが、前の世代の人ができたであろう深い洞察はできているのだろうか。おそらく、できてはいない。つまり、大事な本質を読み取れてないだろう。ぼくはなにか注意を引くものに出会った時、単に目立っていたから、好きなモノだったから。美術館においては、鮮やか、好きな色、構成などなど、まさに上辺しか見ておらず、次の瞬間には忘れている。実際は、好みはもちろん、影響を受けたもの、共感できるモノ、過去の体験など様々な要因や背景に基づいて引き起こされた感覚なのだと少し考えれば気づく。見ることによって、対象の深い部分まで「なぜ」の思考を深めることができる。そうすれば、見える幅が拡がる。あるいは見える世界の数が増える。さらに、見ることによって、ぼくは自らの思考すら見ているように思う。様々な角度から見る。単なる芸術論の押し付けでなかった分、面白かったが、審美眼への道は果てしなく遠い。
Posted by 



