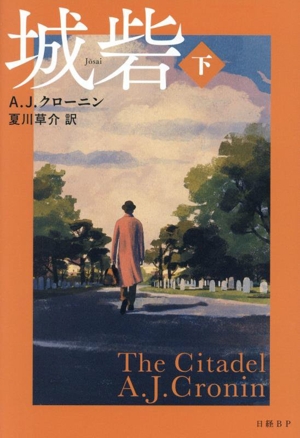城砦(下) の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
一人の医師の半生の物語。 やぶ医者・えせ医療の話がたくさん出てくる。これが当時の医療の実態を反映していて、かつ医師のみならず一般民衆にも読まれたのだとしたら、医療不信を大いに煽ったのではないかと思うが、どうだったのだろうか。 かつては多くの医師の愛読書であったが、現在は絶版となってしまった物語の新訳版。『神様のカルテ』の夏川草介氏による翻訳。 主人公が色々な地に医師として赴き、最初は住人に受け入れられないが、真摯に医療に取り組むことで次第に信頼を得ていく、というのが基本の流れ。主人公は王立科学会員かつ医学博士を取得しているので、相当高い地位にいてもおかしくないのだが、基本的には清貧を旨とし、金儲けではない正しい医療を志している。ただ、ロンドンでは、腐敗した医療慣行の中に主人公自らが身を置いてしまい、金を稼ぐことを成功と称するようになってしまう。患者の死によって目が覚めるが…。クリスティンが可哀そうすぎる。 ストーリーも楽しんだが、それ以上に、100年ほど前のイギリスの医療等の環境について興味深く読んだ。 ・医療保険制度に相当する仕組みが既にあった(職業団体が取りまとめて医師を雇用する。その団体のメンバーは医師にかかることができる) ・王立科学会員について(優れた実績などで推薦されたりするのだと思っていたが、本書によれば、試験によるらしい) ・薬剤師はいるが、医師自ら調剤することもある。というか、資格のない妻にやらせていたりする。欧米では医師と薬剤師の分業はもっと確固としたものというイメージがあったが(王様の毒殺を防ぐために処方する医師と調剤する薬剤師を分ける、みたいな)、必ずしもそういうわけでもないらしい。 ・チーム医療という言葉が出てくる。主人公は終盤で、これからの医療の理想像としてチーム医療を掲げる。ただし、これは複数人の医師が各々の専門性に応じて役割分担をするというような意味なので、今日の多職種連携の意味とは異なるようだ。医師は内科・外科の違いくらいしかなく、呼吸器とか循環器とかいうような専門性は確立されていなかった様子。 ・臨床研究の概念はあるものの、薬の評価を科学的に行うという流れは未発達だったのか。あるいは前向きに臨床研究をするという発想がなかった時代?
Posted by
後半に差し掛かるにつれて面白くなっていった。 以下、引用 幸福というものは――たとえ世の皮肉屋が何と言おうと――世俗的な財産からは完全に独立した、ある純粋な心の状態だということが、これまで考えもしなかったほどはっきりとア ンドルーには理解できた。
Posted by
名著&良書。 一金を稼ぐためだけの無意味な治療、不必要な手術、科学的な振りをした何の役にも立たない数々の処方•••。こんなことは、いい加減やめるべきではありませんか。[363頁引用] この文章にすべてが詰まっている気がしました。 翻訳してくださった夏川草介先生に感謝です。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
上巻はワクワク、スイスイ読んだが、下巻になると胸が苦しくなるシーンが多かった。 とくにクリスティンの気持ちを考えるとこちらまで辛かった。 翻訳が素晴らしく、自分のような医療素人でも違和感なく読み進めることができた。しみじみ出会えてよかったと思える作品だった。 人名を覚えるのが大変なので、登場人物のメモがあったらよかった。 以下印象に残ったところをメモ ・看護師さんには気をつけて ・本人が覆い隠したい事実の指摘は自尊心を大きく傷つける ・自尊心を傷つけられた人は復讐する場合がある ・傷ついた心の回復には適切な運動とそれに伴う睡眠と食事 ・志を同じくする友の大切さ
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
翻訳者・夏川草介さんの熱い解説文が良い。 普段の小説のやわらかな空気感とは違い、鋭く力強い言葉で原著を分析・解説していて、原著の描かれた背景のみならず今回夏川さんが翻訳書を出す意義までわかり胸が熱くなった。 この夏川さんの使命感のようなものは、この本の中で主人公アンドルーが持っていた医師としての使命感に通づる。 「本書を読めば、我々と異なる時代、異なる環境で、我々と同じように悩みながら、懸命に生き抜いた人間がいたことが力強く伝わってくる。どれほど社会が変わっても、人間が何に悩み、何に立ち向かおうとしたかは変わらない。そのことがはっきり理解できるのである。」(解説より) クリスティンとの溝がどんどん深まってしまう期間は切なくて切なくて読むのが辛かった。 クリスティンは本当に苦しかったろうによくクリスティンは離れずにいたなと、女性目線で読んでしまった。
Posted by
- 1