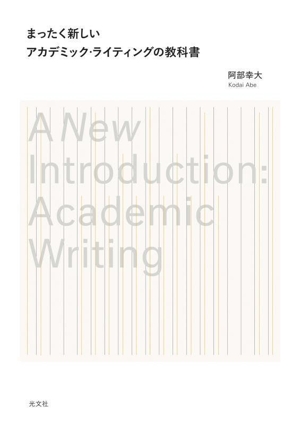まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書 の商品レビュー
文系の論文の型が気になっていたことと、話題だったので手に取ってみた。 内容は平易ではないが、興味深かったり、目から鱗の記述が多く、新しいという書名を体現していると感じられた。 難しすぎると感じたら、後ろの9章から読んでみるといいかもしれない。
Posted by
学問にかかわるすべての文章を書くために必要なテクニックや考え方を実践的に紹介した本。演習もある。 論文は反証可能なアーギュメントを持ち、受動態ではなく、他動詞で書く、という前提を知ることができた。一文一文の分析のしかたなども書かれており、実践的に思う。
Posted by
巷で話題の本なので、買ってみた。自分のためだけでなく、学生の子ら三人の誰かの参考にもなるかもしれないという下心もあり。
Posted by
2025年1月18日読了。SNSで話題になっていた本を購入・読んでみたがなるほど…!冒頭から提示された「謎」がピタピタと検証されていく快感を味わい、さらに終盤には謎を超えて「人類全体への価値」に向けてメッセージが昇華していき、かつ著者の個人的な体験や問題意識についても共感を得られ...
2025年1月18日読了。SNSで話題になっていた本を購入・読んでみたがなるほど…!冒頭から提示された「謎」がピタピタと検証されていく快感を味わい、さらに終盤には謎を超えて「人類全体への価値」に向けてメッセージが昇華していき、かつ著者の個人的な体験や問題意識についても共感を得られる…という、極上のミステリ小説の読後感を超えた「すごいものを読んだ…!」という読書の喜びを得ることができた。かつ、「いかにして論文を書くか」という自分を含めた初学者の悩みにも精神論でなく実践的に答えうる本と感じる。すぐれた本というものは、「なんで今まで誰もこんな本を書かなかったんだろう」と疑問に思うほどに普遍的なメッセージを含むものなのではないだろうか。
Posted by
論文を書くにあたっての理論がまとめられていて、本当に助かる。文章に関しての見識も深めてくれる一冊だと思う。
Posted by
恥ずかしながら50代も半ばを過ぎてから大学院で学ぶべく、入学は許可されたものの、来春から途方にくれないかソワソワしていたところに日経新聞に紹介されて急いで手に取った。著書の中で参照されている「論文の教室」を支えに取り組もうとした甘い考えが早めに打ち砕かれて良かった一方、本書は一度...
恥ずかしながら50代も半ばを過ぎてから大学院で学ぶべく、入学は許可されたものの、来春から途方にくれないかソワソワしていたところに日経新聞に紹介されて急いで手に取った。著書の中で参照されている「論文の教室」を支えに取り組もうとした甘い考えが早めに打ち砕かれて良かった一方、本書は一度では消化しきれなかった為、繰り返し精読をしたい。
Posted by
論文とは何か?「ある主張をし、その主張が正しいことを論証する文章である」とされ、この主張のことをアーギュメントという。このアーギュメントを述べるために、論文は書かれる。その点を軸に語られる論文づくりの説明がとても興味深かった。論文を書かなくても何かに応用したい気持ちが芽生えてくる...
論文とは何か?「ある主張をし、その主張が正しいことを論証する文章である」とされ、この主張のことをアーギュメントという。このアーギュメントを述べるために、論文は書かれる。その点を軸に語られる論文づくりの説明がとても興味深かった。論文を書かなくても何かに応用したい気持ちが芽生えてくる。 本書の半分以上をパラグラフの分析に費やし、いかにこのアーギュメントを論証していくかについて一冊通して理解を深める。反論可能だからこそ、主張はアーギュメントたりうる。 アーギュメントは飛躍しており、だからこそその飛躍を論理的なパラグラフで埋めていく。これが論文だと言われる。 引用されていたヘイヨットの抽象度についてのグラフの話は、論文に限らず活用できそう。抽象度が低い順にレベル1〜5まで、パラグラフ内の文章を分ける。抽象度の高いレベル5がアーギュメントとなり、それを論証すべく、レベル1〜4の文章で補い、最終的にU字型(5→1〜4→5)となるパラグラフが完成する。 何かを説得する時の話し方や資料作りにも繋がる考え方なのだろうな。半分以上パラグラフ分析で構成される本であることも新鮮な感じでそこにも面白さを感じた。「原理→実践→演習」で構成されるこの目次自体も論文構成のメモの機能を果たしているように見えてくる。 あと帯の読書猿さんの「韜晦」という単語を恥ずかしながら初めて知った。
Posted by
一部でもてはやされていたミステリ方面は一切ピンときませんでしたが、論文を書くにあたって必要な構造の部分を明快に紐解いていて、「人文学の研究の目標は世の中を良くすること」という話も大変よかったです。ちょっと論文書きたくなりますね。
Posted by
レポートの書き方が分からず、やりたくなくて後回し。提出日に急いで仕上げ、出来たは良いがゴミレポート呼ばわり…そんな負のループから抜け出すヒントが、本書には詰まっています。論文の核「アーギュメント」という概念を軸に、先行研究との付き合い方や実際の論文執筆、また研究人生に至るまでを...
レポートの書き方が分からず、やりたくなくて後回し。提出日に急いで仕上げ、出来たは良いがゴミレポート呼ばわり…そんな負のループから抜け出すヒントが、本書には詰まっています。論文の核「アーギュメント」という概念を軸に、先行研究との付き合い方や実際の論文執筆、また研究人生に至るまでを、華麗に乗りこなしていくスキルが解きほぐされているのです。しかし、本書の魅力はそれだけではありません。もちろんそれらのスキルも魅力的なのですが、鮮やかに言語化された本書の文章そのものが、これからレポートや論文に向き合う私たちに、大きな力を与えてくれます。何度読みかえしてもおいしい教科書を、ぜひお試しあれ。 また、本書の刊行時にCEGLOCで開催された、阿部先生のワークショップの参加体験記を、以下のリンクからお読みいただけます。 https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja/support/Prism (ラーニング・アドバイザー/人文 MASU) ▼筑波大学附属図書館の所蔵情報はこちら https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/opac/volume/4205657
Posted by
配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=10281038
Posted by