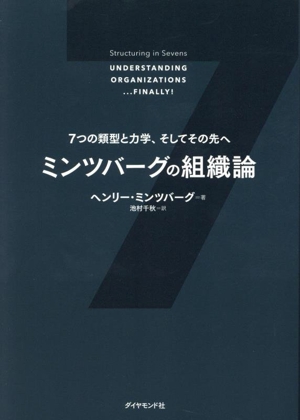ミンツバーグの組織論 7つの類型と力学、そしてその先へ の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
組織には型があると教えられた一冊。冒頭の「効率的なオーケストラ」の例は、笑い話のように思えて、自身もこのような見当違いの示唆出しを行っていないのか、身につまされる思いであった(例: 20人のバイオリン演奏者が全く同じ楽譜を演奏しているのは無駄であり、削減できるはずだ)。 本書を踏まえた個人的な行動変容は主に2点。1点目は、新規事業や戦略の創出などを議論する場合、必ず組織の型を念頭に置くこと。スタートアップのようなパーソナル型と、大企業に象徴されるプログラム型の組織を一緒くたに比較し、差異分析を行ったとしても、意味のある示唆出しに繋がらない可能性が高い。夫々の組織形態の特徴を理解の上、どの粒度で比較を行うのかを慎重に検討する必要がある。2点目は、コンサルとしてクライアントの組織変革に携わる中で、全てをプログラム型組織への移行で解決しないようにすること。本書で学んだ通り、プログラム型と馴染まない組織も当然存在する中で、特にコンサルはこの傾向/指向性があると想定。プログラム型組織になっていないのであれば、それなりの文脈/理由があるはずであり、仮にクライアント内でのルール/意思決定構造等が明確化されていなかった(≒プログラム型ではない)としても、一度「なぜこれまでルールや意思決定構造が明確化されてこなかったのか?」を問いかけ、解の方向性を慎重にすべき。 特に印象に残った箇所は以下の通り ・「ハブやウェブやセットをチェーンに縛りつけることはやめにしよう」(p.43) ・「本当に批判されるべきなのは、戦略の形成と実行を切り離す発想そのものだ。このような発想は、戦略をつくる人たちが十分な情報をもっていて、しかも、状況が十分に安定していたり、予測可能性が十分に高かったりして、戦略の実行段階で戦略をつくり直す必要が生じないことを前提にしている」(p.128) ・「経営コンサルタント、政府機関の職員、企業のCEO、そして経営専門誌の編集者は、プログラム型組織こそが組織だと思い込んでいる。そのため、アドホクラシーは組織の体を成していないように思えるのだろう」(p.152) ・「プロフェッショナル型組織で働くマネジャーは、組織内のどの階層にあっても、専門職たちを監督するのではなく、支援することを役割としている」(p.176) ・「重要な結論は、組織がどの程度有効に機能できるかは、どれくらい矛盾をマネジメントできるかにかかっているということだ。異なる力が競い合うことによって対立が生じている場合は、そこから目をそらすのではなく、その状況をしっかり見据えて、対立を緩和しなくてはならない」(p.260) ・「影響力をもつ外部の勢力や、内部のアナリストたちはしばしば、そうすべきでないにもかかわらず、プログラム型ではない組織をプログラム型組織へ転換させようとする」(p.271)
Posted by
配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=10279867
Posted by
面白い。 マネジメントの類型をアップデート出来る。 ぐちゃぐちゃに見えてた組織にも類型があるし(ウェブ型) 結婚相手を科学的に決めない理由も決定できる(アート、クラフト、サイエンス)
Posted by
組織とはなにか?どの様な組織が存在し、今後どうあるべきか?をまとめた本。 組織づくりの要素となるアート、クラフト、サイエンスがあり、これらの組み合わせによって作られる大きく4つの基本的な組織形態(パーソナル型、プログラム型、プロフェッショナル型、プロジェクト型)について述べられて...
組織とはなにか?どの様な組織が存在し、今後どうあるべきか?をまとめた本。 組織づくりの要素となるアート、クラフト、サイエンスがあり、これらの組み合わせによって作られる大きく4つの基本的な組織形態(パーソナル型、プログラム型、プロフェッショナル型、プロジェクト型)について述べられている。 自分が所属した経験のある組織が、プロジェクト型、プログラム型であったが、あるあるの話が多く大変面白かった。 非常に有意義な内容であるものの、やはり難易度は高めで1回では表面的な所しか理解出来ていないだろう。少し時間を置いて再読してみたい。
Posted by
はじめに 第1章 私たちを取り巻く組織の世界 そもそも組織とはなんなのか マネジメントの「唯一で最悪の方法」 あまりに多様な組織の世界 問題は「用語」がないこと 5つの類型から7つの類型へ(そしてさらにその先へ) 第Ⅰ部 組織を再検討する 第2章 プレーヤーと構成要素...
はじめに 第1章 私たちを取り巻く組織の世界 そもそも組織とはなんなのか マネジメントの「唯一で最悪の方法」 あまりに多様な組織の世界 問題は「用語」がないこと 5つの類型から7つの類型へ(そしてさらにその先へ) 第Ⅰ部 組織を再検討する 第2章 プレーヤーと構成要素 「箱」の外で考える 主なプレーヤー プレーヤーたちの関係 ── 以前に描いた図 「チェーン」「ハブ」「ウェブ」「セット」 第3章 組織づくりの「アート」「クラフト」「サイエンス」 意思決定 ── アートとクラフトとサイエンス 戦略形成 ── クラフトとアート、そして少しのサイエンス マネジメント ── クラフトに、アート、そして少量のサイエンス 第Ⅱ部 組織デザインの基本的な構成要素 第4章 調整のメカニズム すべてのメカニズムを併用する 第5章 組織デザインのさまざまな要素 役職の設計❶ 職務範囲 役職の設計❷ 正式化の度合い 役職の設計❸ 研修と教化 上部構造の設計❶ グループ化による部署づくり 上部構造の設計❷ 部署のサイズを決める 上部構造の設計❸ 分権化のあり方を決める 上部構造の骨格への肉づけ❶ 計画とコントロール 上部構造の骨格への肉づけ❷ 水平方向のつながり 第6章 文脈を踏まえた組織設計 歴史の長さと規模 技術的システム 環境 権力 第Ⅲ部 4つの基本的な組織形態 第7章 パーソナル型組織 ── 個人が君臨する事業 パーソナル型組織の基本構造 パーソナル型組織の環境と種類 パーソナル型組織の長所と短所 第8章 プログラム型組織 ── 工程が定められている機械 プログラム型組織の基本構造 プログラム型組織の環境と種類 プログラム型組織の長所と短所 機械としての構造や性質を上手に活用する 第9章 プロフェッショナル型組織 ── 専門職の寄せ集め プロフェッショナル型組織の基本構造 プロフェッショナル型組織の環境と種類 プロフェッショナル型組織の長所と短所 第10章 プロジェクト型組織 ── 革新を目指すプロジェクト プロジェクト型組織の基本構造 プロジェクト型組織の環境と種類 プロジェクト型組織の短所 第11章 4つの組織形態を比較する 4つの組織形態は古代から永遠に 4つの組織形態の概要 戦略形成のあり方 マネジメントのあり方 現実世界と4つの組織形態 第Ⅳ部 組織を形づくる7つの基本的な力 第12章 4つの組織形態で作用する「4つの力」 パーソナル型組織の「統合」 プログラム型組織の「効率」 プロフェッショナル型組織の「熟達」 プロジェクト型組織の「協働」 第13章 すべての組織形態に関わる「3つの力」 上からの分離 ── 部署と部署を切り離す 文化の注入 ── 組織内の人々を同じ方向に引き寄せる 対立の浸食 ── 組織内の人と人、部署と部署を引き離す 文化と対立は共存する 第Ⅴ部 さらに3つの組織形態 第14章 事業部型組織 事業の拡大と事業の買収 事業部型組織への移行のプロセス 事業部型組織の基本構造 事業部型組織はプログラム型組織との相性がいい コングロマリット化の弊害 ビジネス以外の世界での事業部型組織 第15章 コミュニティシップ型組織 コミュニティシップ型組織の基本構造 コミュニティシップ型組織の類型 コミュニティシップ型組織の長所と短所 第16章 政治アリーナ型組織 政治アリーナ型組織の長所 第Ⅵ部 組織類型の枠を超えて作用する力 第17章 暴走を防ぐ「錨」の役割 「エクセレント」の落とし穴 「汚染」の危険と「封じ込め」の効用 第18章 ハイブリッド型の素晴らしい世界 ブレンド型のハイブリッド 寄せ集め型のハイブリッド 協力、競争、そして「裂け目」 第19章 組織のライフサイクルと組織形態の変遷 組織構造のライフサイクル・モデル 誕生 ── パーソナル型組織としてのスタートアップ時代 青春 ── パーソナル型組織の性格を部分的に維持する 成熟 ── 自然な構造に落ち着く 中年 ── 突然訪れる転換 老い ── 生き残りのための刷新 死 ── 自然死と政治的な死 第Ⅶ部 7つの類型を超えて 第20章 外へ向かう組織 垂直統合と多角化により境界線が確立されているパターン 外へ伸びるネットワーク 契約によるアウトソーシング 提携による合弁事業 部外者を参加させるプラットフォーム 共通の目的に向けた「合同」 テーブルを囲む寄り合い 組織形態の類型と境界線の開き方 第21章 組織デザインのプロセスを開放する 巻末注 主な論文・インタビュー
Posted by
- 1