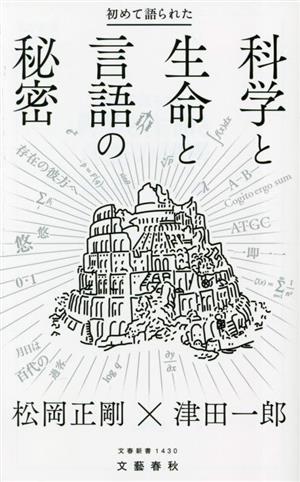初めて語られた 科学と生命と言語の秘密 の商品レビュー
オーディオブック。 何を読んでるのか(聴いてるのか)よくわからんかった。 松岡正剛の本は、一文一文はなるほど〜と思うけど、全体としてなんだかわからないということがよくあって、なぜなのか(私の頭が悪いだけの可能性が高いがw)。いつもちょっと悔しい。
Posted by
メモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1821324949073825990?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
Posted by
難しすぎて大部分ついていけなかった。カオスや複雑系をよく理解してないと何のことやらよくわからない記述が多い。その中でも時間、生命の発生、神経の統合と物語理解の話、誤読による進化や発展、最も美しいものはよく練られた逸脱、意識はマイナスの操作というあたりは面白かった。
Posted by
読んでいて面白いのは確かなのだが、二人とも半端ない智者なので、置いてきぼりを喰らったこちらは半分くらいしか理解できていない気がする(苦笑)。津田一郎の本も何冊か読んでみなければ。
Posted by
難しい・・・何を言ってるのかわからん・・・けど面白い!?という不思議な本。 少し前にも津田一郎先生の『心はすべて数学である』を読んだけど、こちらも難しくてよくわからないのに面白く読めてしまう(しかし全く理解できた気はしない)不思議な本だった。 本書もよくわからないけど読めてしまう...
難しい・・・何を言ってるのかわからん・・・けど面白い!?という不思議な本。 少し前にも津田一郎先生の『心はすべて数学である』を読んだけど、こちらも難しくてよくわからないのに面白く読めてしまう(しかし全く理解できた気はしない)不思議な本だった。 本書もよくわからないけど読めてしまう・・・ので、少し頑張って精読はしてみたのだが、やっぱりわからない、汗。 それでも面白く読めてしまうのは、「生命の起源」や「言語の起源」といった大きなテーマについて、お二人が読者に忖度することなく、持てる知識を総動員して大真面目に議論されているからだと思う。まあ、私は思いっきり置いてけぼりにされているわけだが、熟練したアスリートの走りにほれぼれするような感じなのだろうか。 印象に残っているところは色々あるが、p.152津田,ジョン・ニコリス共同論文の話が出てくるあたり。津田・ニコリスによれば人間が瞬時に記憶できるチャンク(文節)数は7±2の範囲とのこと、だから「物語」を持つと非常に大きな容量のカテゴリーが記憶できるとある。 そんなこと考えたこともなかったけど、原始社会で文字などの記録ができない社会では、情報の伝達手段として「物語」があったというのはありうるかもなあ、と思った。そして当然口承であり、旋律やリズムがあれば音楽の起源もそこにあるのかも、と思ったり。
Posted by
数学 ~意識と意識外のものをつなぐ(津田) デジタル化で周りとの関係性「場」が失われる。 原子の速さは光の速さ、人間は1秒1m程度。租視化し、時間を圧縮。 生命はエントロピーを食べている。「自己組織化」 物語る 太古の人類は文字を持たないためナラティブ情報に 歴史を遡れ...
数学 ~意識と意識外のものをつなぐ(津田) デジタル化で周りとの関係性「場」が失われる。 原子の速さは光の速さ、人間は1秒1m程度。租視化し、時間を圧縮。 生命はエントロピーを食べている。「自己組織化」 物語る 太古の人類は文字を持たないためナラティブ情報に 歴史を遡れるのは文字の後 少しだけ間違える 新しい意味が生成される 構成要素 ストーリー、シーン、キャラクター、ナレーター、ワールドモデル 最終状態のための初期値の選び方 抽象的な拘束条件 文字 文字の初期は音読のみ 写本の転移力 音読はリニアな展開軸 黙読は映像的 脳 記憶 情報をためる 学習と編集 視/聴/臭/体性感覚情報の統合=物語編集 神経は筋肉と同じ 負担をかけると力を発揮する ツイッター 脳に負担をかけない 宗教 スピリットとゴースト 組織で説明できないこと 宗教で 意識 in/form 形作る →information 情報 =A-B:整えられた情報を作るために引かれた部分Bが意識
Posted by
碩学の2人による対談語り下ろし。かなり濃い話題をしろうとにもわかりやすく努力しているけど、やはり知らないことはおおいなあと感じる1冊。
Posted by
津田先生はまだまだ新しいことを考えていた。北大から中部大学に共同研究者を引き連れて来られているくらいだから、まだまだやるべきことがあるのだろう。脳がどのようにしてできてきたのかシミュレーションをされている。カオスのダイナミクスの中に情報を蓄えることができるという。論理に時間を導入...
津田先生はまだまだ新しいことを考えていた。北大から中部大学に共同研究者を引き連れて来られているくらいだから、まだまだやるべきことがあるのだろう。脳がどのようにしてできてきたのかシミュレーションをされている。カオスのダイナミクスの中に情報を蓄えることができるという。論理に時間を導入しようとされている。自己他者言及がおもしろくて授業でも何度か話をしているが、このパラドックスに興味を持ってくれる生徒がどれだけいることだろう。そして、意識とはいったい何なのか。A-BのBとはいったい何なのか。養老先生が眠る動物には意識があると言っていたが、Aが脳全体で、Bが意識で、A-Bが眠っている状態なのだろうか。もう、とにかくすごいことを考えているということはわかるのだが、私の読解力不足、知識不足のためについて行くことがかなり困難であった。そして、松岡さんはそれを津田先生が突っ走るのを緩和するのではなく、それ以上にさらに加速されている。どうしてこの人はそんなに専門的な内容に食い込んでいくことができるのか。とにかくすごすぎる。まあ、それはともかく、2人の出会いからいろいろと固有名が出てくるあたりは読んでいて楽しい。津田先生はいったい湯川先生と何があったのか。朝永先生のことは良い人物として話されているのだが。さて、私は若いころ3年ほどだが東京で出版社に勤めていた。その際、唯一自分で企画した本が完成している。それが津田先生の「カオス的脳観」だ。雑誌「数理科学」や「エピステーメー」などで津田先生の文章にふれ、ぜひ新しいシリーズの1冊にと思ってお願いした。最初に「情報的自己組織化」(だったと思う)というタイトルで原稿をもらったときには興奮して一気に読ませていただいた。当時、青二才の私は雑誌「理想」なんかも読んでいて、自分の感じたことを1ページほど食い込ませていただいたりした。ド素人のくせに自分で制作の仕事までして、なんかもうカバーとか思うような色にならなくてずいぶんと落ち込んだりもした。本文に「動的脳観」ということばがあり、それならばいっそのことタイトルは「カオス的脳観」にしようということになった。その本が松岡さんの千夜千冊107夜に紹介されたときはうれしかったなあ。ということで、昔のことを少し思い出しながら、また興奮しながら、楽しく読ませていただきました。今後も研究成果を、できれば一般書としても、発表されていくことを期待しております。それと、自伝も。
Posted by
【まだ見ぬ「神」を探して――岡潔×小林秀雄の名著『人間の建設』の現代版がここに誕生!】生命はどこから来たのか。時間はどこから生まれたか。生命原理解明のための最後のピースを探し、文理の知性を総動員して語り尽くす。
Posted by
- 1