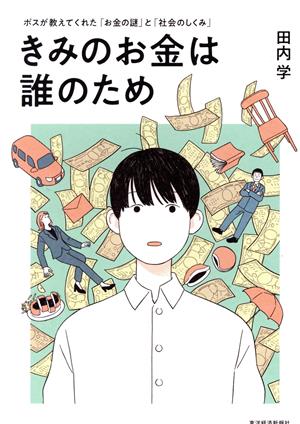きみのお金は誰のため の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
禅問答のようだったけれど、読み易くまとまっている 目に見えない、概念として捉えづらい「お金」の意味を主軸に、格差や、社会のしくみ、働くことの意味をも改めて考えさせられた こういう視点があることを知るだけでも意識は変えられる 中高生に手に取って欲しい一冊
Posted by
中高生たちは、 お金持ちになりたい、 高年収の会社に入りたい、 安定した企業に勤めたいという。 親御さんは、中学受験をさせたり、 いい高校出て、いい大学を出て、 一生安泰で過ごしてほしいと願う。 みんなが当たり前に考えていること。 ぶっちゃけすべてはお金がつきまとう。 そのお金...
中高生たちは、 お金持ちになりたい、 高年収の会社に入りたい、 安定した企業に勤めたいという。 親御さんは、中学受験をさせたり、 いい高校出て、いい大学を出て、 一生安泰で過ごしてほしいと願う。 みんなが当たり前に考えていること。 ぶっちゃけすべてはお金がつきまとう。 そのお金を少し角度を変えて見ると、違ったものに見えてくるかも、というお話しだと感じました。 お金の流れが止まったり、流れたり、早く動いたり、ゆっくり動いたり、逆流したりするどうなるのか。 キャッシュフローをわかりやすく解説しながらストーリー展開。 そのお金の流れが次の未来ではどうなるのか予測しながら考えると、貯金したりお金を多く集めることではないことがわかってきます。 わたしたち個人が仕事で得た給料は、 自分が自分による自分のためにお金と思いがち。 ほんとうにそうなのか。 優斗くん、七海さん、そしてボス、 三人の会話で解説。 そして最後の結末まで、しっかり感動。 読み終わって思いました。 意外と今の中高生の方が薄々気づいているのでは。 逆にバブル期の経験者はお金で買えないものはないと今も思い込んでいる人いますから、この本は50,60,70代に読んでもらいたいと思いました。 そうすれば、経済的にも愛にも満ち溢れた豊かな日本になると思います。 そう願います。
Posted by
自分の人生がお金中心になってしまわないように、お金を道具として考える。 お金によって、人々が支え合える社会が実現していること。 お金の移動や格差について。 お金のことを勉強する機会がなかったため、改めて考える良いきっかけになった。
Posted by
サラッとすぐに読めた。 お金は天下の回りもの、生きた金を使え、若いうちの借金は買ってでもしろ、など、お金に関する言葉が繋がった気がした。
Posted by
電子ブックへのリンク: https://kinoden.kinokuniya.co.jp/hokudai/bookdetail/p/KP00089926 ※学外からはこちら→ https://www.lib.hokudai.ac.jp/remote-access/?url=htt...
電子ブックへのリンク: https://kinoden.kinokuniya.co.jp/hokudai/bookdetail/p/KP00089926 ※学外からはこちら→ https://www.lib.hokudai.ac.jp/remote-access/?url=https://kinoden.kinokuniya.co.jp/hokudai/bookdetail/p/KP00089926
Posted by
お金は何も解決してくれない 問題を解決してくれているのはお金の向こうにいる人 お金が増えても、問題を解決してくれる人がなければ意味がない(食糧難な時に食べ物が高騰したとして、お金をたくさん配っても分け合うものがなければお金の意味はない) 働く事自体が誰かのためになっている ...
お金は何も解決してくれない 問題を解決してくれているのはお金の向こうにいる人 お金が増えても、問題を解決してくれる人がなければ意味がない(食糧難な時に食べ物が高騰したとして、お金をたくさん配っても分け合うものがなければお金の意味はない) 働く事自体が誰かのためになっている 物々交換できないものをお金が仲介している など、 とてもわかりやすく書かれている 学校や塾で勉強できるのは、両親のおかげと考える。それは偉そうな客と根本は同じでお金が解決してくれると考えているんや というところはちょっと納得できなくて 塾や学校に行かなければ自分自身(親も含めて)で問題を解決する事 学力をつけたり、人のためになる技術を得たりする事は難しいと思う だから親の経済力で子供の学力差ができてしまったりするし、そこらへんはもやっとした すごく性善説で書かれていて私も気持ちは同じだけど 日本的な和を持って恩を送るような考え方は、現代のグローバル社会(奪い合うイメージ)に対応するのかなと思った こんな考えの人が増えて増えまくればいいと思う お金に苦しめられている人にはどううつるのかなとも少し思った
Posted by
とても分かりやすいです。 お金についてこんなに考えたのは初めてです。 自分の老後のためにとお金を貯めていましたが、 その時にはお金が意味のないものになっているかもしれない。 極端な話、農業をはじめ、“ぼくたち”の輪を広げて、物々交換で昔のように暮らしていくのがいいのかもしれない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
とてもとても良かった。 19歳か18歳の頃に買ってから3年近く経ってようやく読めた。 お金の持つ意味、価値やこれからの付き合い方について考えることが出来た。 お金自体に価値がある訳ではなくて、お金によって誰かが働いてくれるからこそお金には意味があって、個人のしてんじゃなくて全体の目線で考えるとお金を貯めることにはなんの意味もなくて技術だったり、人としての繋がりだったりが必要なこと。 自分がどこまで俯瞰的な目線でお金と付き合っていけるかは正直自信が無いし、やっぱりなんだかんだお金は力を持ってるとも思う。多くの人がお金には価値があると思ってるから。でもだからといってお金を持っているから偉いだとか、お金が全て、作中の言葉を借りると"お金の奴隷"になることはないと思う。 話は変わるけど、本を読むのはタイミングが大切だと思う。この本を買ったのは3年前だけど今読めた事がとても良かったと思う。自分でアルバイトをしてお金を稼ぐようになったこと。将来、家族から自立して生計を立てることを真剣に考えないといけない時期であること。 お金とは何で、自分は誰のために働くのか、そのお金でどのような選択をするのか、もっと考えていきたい。(2025/12/09 00:02:19)
Posted by
すごくよかった! お金のことが、初めてよくわかってきたきがする。 お金の奴隷、ぼくたちの範囲を広げる、等、今後の人生の課題。これが変われば、人生観がだいぶ変わる気がする。
Posted by
「なぜ働かなければならないのか?」 「お金とは何なのか?」 そんな素朴な疑問に対して、これほどわかりやすく、かつ論理的に答えてくれる本があったでしょうか。 この本の素晴らしいところは、難しい経済用語を並べるのではなく、中学生の主人公と一緒に「謎解き」をしていく点です。複雑な問題...
「なぜ働かなければならないのか?」 「お金とは何なのか?」 そんな素朴な疑問に対して、これほどわかりやすく、かつ論理的に答えてくれる本があったでしょうか。 この本の素晴らしいところは、難しい経済用語を並べるのではなく、中学生の主人公と一緒に「謎解き」をしていく点です。複雑な問題を分解して、誰もがわかる形にしてくれています。 特に印象的だったのは、「お金の向こうには必ず人がいる」という視点。 私が今日買ったコーヒーも、誰かの労働の結晶なのだと気づいたとき、冷徹だと思っていた経済活動に体温を感じることができました。 著者の田内学さんは、物理学専攻から金融の世界に入った方ですが、まさに理系的な「構造化」と、文系的な「人間への眼差し」が見事に融合しています。 読み終えた後、自分の仕事が誰かの役に立っていると、胸を張りたくなる。そんな「働く勇気」をもらえる一冊です。親から子へ、手渡したい本ですね。
Posted by