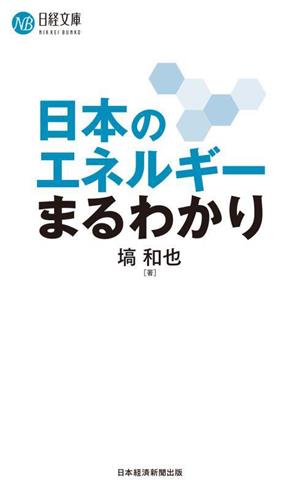日本のエネルギーまるわかり の商品レビュー
配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=01429349
Posted by
生成AIに本書のレビューを書いてもらったら、こんな感じ。 「日本のエネルギーまるわかり」は、日本のエネルギー政策と脱炭素の取り組みを体系的にまとめた入門書です。欧州と比較して、日本は企業の自助努力に頼る一方、脱炭素対応では先進国の中でも遅れている状況です。本書は、気象災害の影響...
生成AIに本書のレビューを書いてもらったら、こんな感じ。 「日本のエネルギーまるわかり」は、日本のエネルギー政策と脱炭素の取り組みを体系的にまとめた入門書です。欧州と比較して、日本は企業の自助努力に頼る一方、脱炭素対応では先進国の中でも遅れている状況です。本書は、気象災害の影響やエネルギー安保、企業の取り組み、エネルギー政策の大転換などを詳しく解説しています¹。 主にアマゾンのレビューを使っているらしい。 なるほど、それらしく書いてくれるのね、とびっくり。 けれども、やはり、自分にとって印象的だったことをまとめておきたい。 普段、どうして日本は再生エネルギーの普及が進まないのかと歯噛みするような思いでいる。 太陽光も、地熱も、小水力もやったらいいじゃないか、と。 地熱が日本では商業的に採算がとりにくいということは本書で初めて知った。 地熱発電は地下の高温高圧の水が溜まっている地熱貯留層から取り出した蒸気や熱水でタービンを回して発電する。 ところが、貯留層が小さく、深くまで掘らないといけないため、あまり効率がよくないらしい。 さらに、貯留層がそれなりにある場所は都市から離れた場所が多く、送電のコストもかかる。 そうか~、難しいのか、とわかった。 水素発電やアンモニア発電も、すぐには実用化は難しいと聞いている。 (素人考えだが、水素なんて危険じゃないかと思ってしまう。) GXが進むのが早いか、地球が沸騰するのが早いか。 まあ、ここで齊藤幸平さんのように、脱成長に舵を切るということもあるのかもしれないけど。 もう一つ、意外だったので印象に残っているのは、アメリカの今後の動向の予測。 アメリカの脱炭素の動きの主な担い手は、州であり企業で、連邦政府もなかなかそれをくつがえすことはできないという。 過去のトランプ政権の時でさえ、だ。 ということは、「もしトラ」であっても、ただちに動きが止まることはなさそうと考えてよいのかな。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
かつては、再生エネルギーは原子力と競合する、といわれて熱心ではなかった。 日本は50hzと60hzにわかれていて自由に融通ができない。ヨーロッパは、ウクライナ、ソ連まで接続できる。 洋上風力は原発45基分を目指す。太陽光よりも長く発電できる。国産化が難しい。 気候条約上の先進国、途上国の定義は現在のずれがある。日本は先進国、中国韓国は庚申国として参加。 205年では遅い。分水嶺は2030年ではないか。 ペロブスカイト型太陽電池=薄くて軽い。 地熱発電は参入障壁が高く、熱源が小さく大型化できない。
Posted by
日本が置かれている状況がわかります。 かつては再生エネルギーのトップランナーだったのに、残念でなりません。
Posted by
技術で先をいっていたのに、実装で大きな遅れをとっている日本。 既得権益を慮るばかりに、方向性を示すことができず、結果、個々の企業もどこに投資をすれば良いのかがわからない状況。 政治に期待できないなか、 これを個々でどうこうすることはできるのか。。。
Posted by
- 1