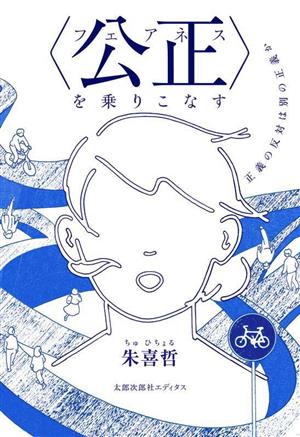〈公正〉を乗りこなす の商品レビュー
ロールズとローティの論を中心に論を進め、他の哲学者の論も絡め丁寧に論を進めている。トランプ現象や日本の道徳教育、論破など現代にはびこっている問題を具体的にはさみ理解しやすかったが、ただ哲学的な論も多く、理解が十分できたかは疑問である。ただ会話の重要性、ことばの大切さは理解できたし...
ロールズとローティの論を中心に論を進め、他の哲学者の論も絡め丁寧に論を進めている。トランプ現象や日本の道徳教育、論破など現代にはびこっている問題を具体的にはさみ理解しやすかったが、ただ哲学的な論も多く、理解が十分できたかは疑問である。ただ会話の重要性、ことばの大切さは理解できたし、最後に言葉を持てない人たちに対する我々の責任性は「正義をめぐる会話」を決してあきらめずにつないでいくことである。
Posted by
「世の中には正しさの押しつけや決めつけがあるのではないか?」 そんな疑問に対する気づきを求めて手に取った本。 主張は自分の意見という意味で一人分だけ主張しようという趣旨が貫かれている。 いくら自分は正しいと感じていても、それを人に押し付けるものではない。 ここまではよくある話。...
「世の中には正しさの押しつけや決めつけがあるのではないか?」 そんな疑問に対する気づきを求めて手に取った本。 主張は自分の意見という意味で一人分だけ主張しようという趣旨が貫かれている。 いくら自分は正しいと感じていても、それを人に押し付けるものではない。 ここまではよくある話。 この本の特に参考になる部分は次のこと。 自分の正しさと相手の正しさがぶつかり合った時、どう折り合いをつけていくかにページをさいて主張が展開されている点。 もちろんこれにも唯一の正しさなんてないけど、 「みんな仲良くしよう」「話し合いで解決を」「思いやりの心を」みたいな、 実際には何の役に立たない正しさよりも、よっぽど役に立つ内容だと思いました。
Posted by
酷暑ビブリオバトル2024 決勝 2ゲーム目で紹介された本です。ハイブリッド開催。 2024.8.12
Posted by
「正義の反対は別の正義」という、もっともらしく聞こえる相対主義に対して著書は明確にNOを突きつける。 ロールズの理論を使い、人それぞれに異なった〈善〉はあるが、それとは別に絶対的な〈正義〉は存在するのだと解く。その正義とは、例えば残酷さの拒否、信仰を強制されない自由であったりする...
「正義の反対は別の正義」という、もっともらしく聞こえる相対主義に対して著書は明確にNOを突きつける。 ロールズの理論を使い、人それぞれに異なった〈善〉はあるが、それとは別に絶対的な〈正義〉は存在するのだと解く。その正義とは、例えば残酷さの拒否、信仰を強制されない自由であったりする。 正義とは個々人の価値観の違いを超えた社会的合意を可能にするための構想であり、どのような構想を正義として選び合意形成するのかというプロセスこそが政治なのだと説く。 めちゃくちゃ理想論ではあるが、政治に理想を求めるのは当然であり、それをお花畑と笑ったりどうせ変わらないのだという冷笑的な市民の態度こそが、政治の腐敗を招くのだということは肝に銘じておきたい。とても良い本だった。 それってあなたの意見ですよね?という某ヒロユキの有名フレーズについても、「どっちもどっちという泥仕合に持ち込もうとするテクニック」「ただひたすら負けないことを目指している戦術」と断じる。 少し長いが、すごく納得できて感銘を受けたので引用すると、 『ここでの「負け」とは、相手の主張を受けて「自身の信念を改訂する」というかたちで影響を受けることを指すでしょう。そうすると、この論法の使い手は、他者から影響されることを「ダメージを負う」「恥ずかしい」ことだと考えているということになりそうです。社会とかかわりながら多様なことばづかいを学び、自己を変容させることが「敗北」であるというルール設定は、きわめてエクストリームなものだと思いますが、そうした特殊なルールを支持する「観客」がいることもまたたしかなのです。こうした態度に通底するものは「まちがっていたくない」という怯懦なのです。 わたしたちがもっとも広い意味でことばを介しておこなっているコミュニケーションの基底を「会話」と呼ぶならば、それはけっして「勝ち負け」がある、対戦相手を論破するゲームではない、というあたりまえの点です。』
Posted by
メモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1759417143660294564?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
Posted by
ロールズの正義を用いて、学術的に書いてある本でしたが、あまり理解出来ませんでした。まあ私の頭の悪さから来てると思われますが。
Posted by
こういう言語哲学の本を読むと、いかに自分がモノを考えられないかがよく分かる。難しいコトバが使われているわけでもないのに理解できない。 ロールズの正義論やローティの政治哲学が紹介されるけど、てんでついていけない。もう頭が考えることを拒絶してるんだな。さみしい。
Posted by
人権…は人類の普遍的価値/正義のはずなのに、ことば・表現として使いこなせてない、変な使われ方が多い……。ではどうする? と、自分のことばの使い方、慣れ親しんでいるはずのことばとの向き合い方について、考えを整理できる1冊でした。
Posted by
朱先生ってこういうことを考えているのか。わかりやすく書いているが、専門家向きだと思う。ロールズからはじまって現在の政治的な状況をいろいろ哲学的に考えてるやつで、非常に興味深いんだけど、細かいところはいろいろ微妙な感じもありで、同世代、あるいはちょっと上の世代からの詳細な書評を読ん...
朱先生ってこういうことを考えているのか。わかりやすく書いているが、専門家向きだと思う。ロールズからはじまって現在の政治的な状況をいろいろ哲学的に考えてるやつで、非常に興味深いんだけど、細かいところはいろいろ微妙な感じもありで、同世代、あるいはちょっと上の世代からの詳細な書評を読んでみたい。特に「正しいことば(の使い方)」っていうので考えているものがどういうものなのか……あがっている文献は、なるほどいまどきの若い先生たちはこういうの読んで育ったのか、という感じがある(ローティが専門なのね)。
Posted by
- 1