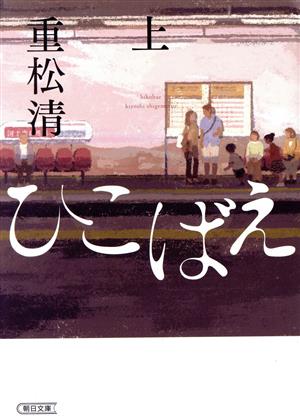ひこばえ(上) の商品レビュー
40年も前にいなくなった父親と向き合う事となった洋一郎。歳も同年代の為、置かれた環境や心情にガッツリ感情移入する。 いない存在に今更何を思うことがあるのか、普通はうっちゃってもいいと思うが、ジワジワ父親を思い出していく。何故か自分も幼少の頃を思い出し父の様子も断片的に記憶が戻って...
40年も前にいなくなった父親と向き合う事となった洋一郎。歳も同年代の為、置かれた環境や心情にガッツリ感情移入する。 いない存在に今更何を思うことがあるのか、普通はうっちゃってもいいと思うが、ジワジワ父親を思い出していく。何故か自分も幼少の頃を思い出し父の様子も断片的に記憶が戻ってきた。 悩みは家族の問題だけではないんだな、仕事の方もトラブルが尽きない。生活って単純じゃない。 重松さんの作品はこの辺りのリアルさがいつも重なり、解決も見いだせないまま進んでいく。 佐山 一見普通の時計でも、実はストップウォッチだったんだよ。子を亡くした親の悲しさの表し方が重く響いた。 ひこばえ 知らなかったタイトルの意味。息子の息子。面倒くさかった神田の発言、ようやく素直に受け止められた。 洋一郎や家族には無責任な父親、大家や図書館の親子には感じの良いおじいさん、神田には色々あったが大事な友達。人には色んな顔があるのは当たり前だが、下巻では父親のことをもっと知れるのだろうと思う。続く。
Posted by
感想 老後も自分の生活や入る墓、誰が面倒見るのかとか色々あるんだなぁ。 ちゃんと遺言を残して、残された人に迷惑かけないようにしないとなぁ、なんて思ったりする。 あらすじ 長谷川洋一郎は、小学生の時に父親が出て行った。本人はあまり気にしていなかったが、姉は実父に強い憤りを感じ...
感想 老後も自分の生活や入る墓、誰が面倒見るのかとか色々あるんだなぁ。 ちゃんと遺言を残して、残された人に迷惑かけないようにしないとなぁ、なんて思ったりする。 あらすじ 長谷川洋一郎は、小学生の時に父親が出て行った。本人はあまり気にしていなかったが、姉は実父に強い憤りを感じ、自分が母親を支えていくという強いが強い。 自分も55歳になり、孫が出来る段になって、老後のことを考え始める。姉は、母親が再婚した相手方の子供に強い不満を抱いている。 ある日、姉から出て行った父親が東京で亡くなったので、洋一郎に家財の処分などを任せたいと言われ、40年以上会っていなかった父親とお骨で再会することになり、複雑な思いになる。 父親のお骨を引き取りたくないが、父親の昔の友達などはそれを望んで、引き取らせようとする。 洋一郎が勤める老人ホームでは、本社案件入ってきた後藤さんが、天然迷惑系の人で、施設で様々な問題を引き起こす。
Posted by
・少し難しかった。 ・読んでいて悲しくなったり、イライラしたり、感動したりいろいろな感情になった。 ・全員の言っていることが正しいと思えた。 ・下がすごい気になる上だった。 ・とても良い作品だった。
Posted by
上巻の総括として、 主人公(洋一郎)の父親との記憶はおぼろげなものしか残っていない。家族を捨てた父親の死をきっかけに、「息子」としての自分が父親と徐々に向き合っていくストーリー。父の遺品を整理する中で,関わりのある人のとの交流をきっかけ親子の関係について考えていく。子をもつ「父親...
上巻の総括として、 主人公(洋一郎)の父親との記憶はおぼろげなものしか残っていない。家族を捨てた父親の死をきっかけに、「息子」としての自分が父親と徐々に向き合っていくストーリー。父の遺品を整理する中で,関わりのある人のとの交流をきっかけ親子の関係について考えていく。子をもつ「父親」としての自分、さらに、やがて娘に子供が生まれることで「祖父」としての見方がそこにプラスされていく。 物語の周辺にも、いろいろな親子の形が描かれている。 上巻では父の意外な姿に戸惑いつつ,未だ父を許すことができない。下巻ではどのようにクライマックスにつながるのか,期待を込めて★は5です。 私自身、「息子」「父親」の両方の立場なので、とても自分と重ねやすいお話だと感じました。
Posted by
久しぶりの重松清さん。 少年少女の悩める心に向き合った作品が多い作家さんだが、今回は現代の家族が抱える問題を描いた作品。 「ひこばえ」とは? 伐った木の切り株などの根元から新たに生える芽のことを「ひこばえ」と呼ぶ。もともとは、太い幹に対して、孫(ひこ)に見立てて孫が生まれる=孫...
久しぶりの重松清さん。 少年少女の悩める心に向き合った作品が多い作家さんだが、今回は現代の家族が抱える問題を描いた作品。 「ひこばえ」とは? 伐った木の切り株などの根元から新たに生える芽のことを「ひこばえ」と呼ぶ。もともとは、太い幹に対して、孫(ひこ)に見立てて孫が生まれる=孫生(ひこばえ)という意味。ひこばえは、眠っていた芽(休眠芽)が起き出したもの。 『ひこばえ』上巻 長谷川洋一郎は小学2年生の時の両親の離婚を機に、父親が2人いて苗字が3度変わる人生を歩んでいた。洋一郎も55歳になり初孫誕生が間近になったある日、母と離婚以来、音信不通となっていた実の父親の訃報が届く。 父は生前「自分史」を作ろうとしていた。 記憶も思い出も朧げな実の父親・・・ 空白の48年間父は何を思いどう生きたか・・・ 様々な葛藤を抱えながらも、洋一郎はその人生に向き合うことを静かに決意した。 下巻へ続く ※下巻を読み終わってから纏めてレビューします。
Posted by
小学校2年生の時に別れたきりの父が亡くなった。報せを受けた長谷川洋一郎は、48年間の空白を胸に、父の人生に向き合おうとする。(e-honより)
Posted by
人は、ある日を境に得るものより失うものが多くなる。それまで与えられ、または自らの意思で得たものの多くが蒸発するかの如く失われてゆく。それら全てが存在を示す証であって、失う度に心には穴があき、心許なさが募る。失ってしまうのは人との繋がり、心の穴は寂しさ、この過程を老いという。あいた...
人は、ある日を境に得るものより失うものが多くなる。それまで与えられ、または自らの意思で得たものの多くが蒸発するかの如く失われてゆく。それら全てが存在を示す証であって、失う度に心には穴があき、心許なさが募る。失ってしまうのは人との繋がり、心の穴は寂しさ、この過程を老いという。あいた穴の埋め方で老いた時の居場所や居心地が変わるのだが、それは人との繋がりを如何に保って行くかということ。最たるものは血の承継。これだけは何事にも揺らぐことのない、逆に言えば決して断つことのできない、理屈抜きの繋がりなのだ。 「おい、息子。わかったようなこと書いてんじゃねーぞ。」 「やっぱり干物ですよ。水分の抜き方が大切ってことです。」 「あんたね、そんなこと書いてる暇あるなら、他にやることあるでしょ。」 「いや、どうでもいいことなんですけどね。うちの息子なら、もう少し気の利いたことが書けますよ。」 「これでいいの。老いるってね、難しいのよ。」 (合掌。念仏・・・) 濃ゆーいキャラクター達の声が聞こえてきます。私もお近づきになりたい。 長編ではありますが、とても読みやすく、残りの人生についてあれこれ考えさせられます。心に残るフレーズが沢山出てきます。老若男女、全ての人に読んでいただきたい作品です。老いたら迷惑じゃなく面倒かける。いいなこれ。 週末は墓参りに行ってこよう。
Posted by
詳しい感想は下巻も読み終わってから。 ただ、上巻だけでも十分楽しく読めた。 人物の書き方がうまいな、と改めて感じながら読んだ。
Posted by
久しぶりに読む重松清さんの作品。その上下巻の上。 ひこばえっていう言葉の意味も初めて知りました。 自分より少し世代が上の主人公の親子の物語。 少しずつ見えてくる父の姿。 様々な人々との出会い。 下巻ではどんな物語が、と期待を感じながら読み終えました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「くちぶえ番長」に続く重松清作品。またまた職場のパートさん(もうすぐ60歳)が、「私たちの年代の方が合うかも。」と貸してくれた。どれどれ。 しっとり穏やかに、懐かしさ、哀しさ、寂しさ、辛さ、優しさ、色んな感情が胸を打つ。物語設定自体もそうなんだけれど、重松清さんの文章が、そうさせている気がする。重松清さんの文章は、礼儀正しく、柔らかい。そんなイメージ。 主人公は長谷川洋一郎、55歳。洋一郎には小学2年生で生き別れた父親がいて、長い時を経てその父親が亡くなったとの知らせが入る―。 洋一郎の幼い頃の父との思い出は、昭和のその時代を直接知らない私でも、懐かしさに胸がいっぱいになる。なんでだろう、やはり重松清マジックか。そんな父親との少ない思い出の描写もありつつ、洋一郎の今が少しずつ明らかになっていく。 洋一郎の友人で、一人息子を若くして亡くした友人「佐山」が洋一郎に相談にくる場面は、佐山とその奥さんの癒されない哀しみが、ただただもう苦しかった。誰が悪いわけでもないのに、と思うと人生とは苦行だと思ってしまう。 そして父親の死の知らせが入ってから、その父親と母親が離婚した後の洋一郎のこれまで人生が少しずつ分かってくるのだが、母の再婚、再婚相手とその子供についてなど知るうちに、洋一郎の複雑な半生がだんだんと見えてくる。ここらへんの構成もうまいなぁと思ってしまう。なんというか、徐々に情報がでてくるというか。ここ、という場面で必要な情報が出てくるというか・・・うまく言えないけど。 まぁ、なんて複雑。洋一郎は苦労をしているんだなぁ、としみじみとわかってくる。 父の死をきっかけに知り合う人たち(大家さんの川端久子、遺骨を預かってくれている和尚、父が通っていた地域の文庫の職員、田辺さん親子、そして父の友達だという神田さんなど)が、みんないい人で、その人たちが語る父親もいい人で、幼い頃に別れた父親と違いすぎて戸惑う洋一郎。何より、周りから「お父さん、お父さん」と呼ばれても全くピンとこない。洋一郎の中に父親が不在・・・という状況。 そんな中、勤め先の介護施設併設老人ホームに、面倒な人が入ってきて、その人の背中と覚えていないはずの父親の背中が重なるー まだ半分だけど、「さすが重松清さん」と言い切りたい。誠実に真剣に人間に向き合ってその人生を観察し、丁寧に読者に伝えてくれている気がする。 下巻に続きます!
Posted by
- 1
- 2