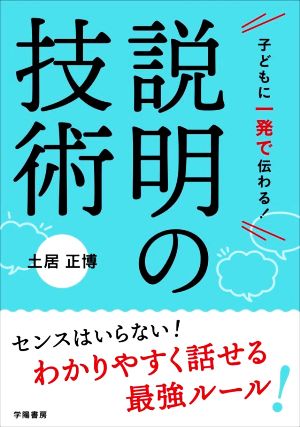子どもに一発で伝わる!説明の技術 の商品レビュー
自分の説明を定期的に録画して聞いてみる!時間感覚を磨く。説明は短く簡単に。文は区切る!何分で話すよと宣言すると◎。要約力を高まる。一言で言うと…の癖をつけよう。間を恐れない。3にこだわる。具体例を三つ考える。主語と述語は近くに置く。
Posted by
「誰もがやっていて、知っていて、言語化してこなかったこと」が整理されていると思いました。 「そうそう!それ大事だよね!」「よくぞ言ってくれた!」と思うことが沢山ありました。 「説明」って色々ありますが、この一冊で完全に整理されると思います。
Posted by
<本のタイトル> 子どもに一発で伝わる! 説明の技術 <本の紹介> 教師が具体例や実物を用いて、分かりやすく説明すれば、 子どもも「そうか!なるほど!」と納得感を持って、教師の意図や伝えたいことが理解できます。 本書では、「子どもの理解を促す説明」「子どもの説明力を高めていく技...
<本のタイトル> 子どもに一発で伝わる! 説明の技術 <本の紹介> 教師が具体例や実物を用いて、分かりやすく説明すれば、 子どもも「そうか!なるほど!」と納得感を持って、教師の意図や伝えたいことが理解できます。 本書では、「子どもの理解を促す説明」「子どもの説明力を高めていく技術」を紹介します。 <何が書いてあったか(誰でも書ける)> ・説明とは「明らかでない」状態を「明らかな」状態へと改善する言語活動である。 ・指示、発問、説明の違い 指示:子供の行動に働きかける 発問:子供の思考に働きかける 説明:行動と思考の両方に働きかける ・丁寧な説明の積み重ねにより、相手の納得感を得られ、相手との信頼関係構築につながっていく。 ・説明の基礎 端的に・短くする 結論を先に言う・全体像を先に示す 具体例を出す(相手にとって身近なものを具体例に使うこと、そうでないと逆に混乱を招く) 理由・目的を伝える 曖昧な言葉ではなく、具体的な言葉を使う 知識のない相手でも確実に理解できるような言葉を使う 実物を見せる(百聞は一見に如かず) ・説明の応用 説明したい内容をほかの物事に喩えてみる 対比と類比を使う 因果関係に気づかせる(いまやっていることが将来にどうつながるのかを説明する) →理由や目的はどちらかというと短期的な「なんのため」で、因果関係は長期的な「なんのため」を示す 対義語や類義語を用いる 極論・仮定を用いる 経験を想起させる 教師の経験を語る 学問の知見を活かす 言葉での説明+体験をセットにして伝える <そこから何を学んだか(自分自身のオリジナルの意見)> ・指示、発問、説明の違い 指示:子供の行動に働きかける 発問:子供の思考に働きかける 説明:行動と思考の両方に働きかける 知識のない相手でも確実に理解できるような言葉を使う <それをどう活かすか(アウトプットによる実践経験の蓄積)> その場しのぎではなく、相手の成長にも長期的に貢献できるよう、真摯に説明する努力を継続する。 また相手の立場に立って、相手がわかるような説明を日ごろから心がける。
Posted by
なんとなくやっていたことを、教師向けに「分かりやすく」まとめてくれている一冊。説明の技術が、基礎と応用に分けて紹介されている。そして、これらを子どもたちも使えるようにしていくことが大切である。
Posted by
説明する目的 学習内容の理解を深める 学習内容の意義付け 子どもの説明力向上 そのためにコツを利用する 端的に言う、具体的に言う、極端を使う、比喩をする 子ども目線で話す、子ども同士で話す 評価基準を明確にする、あえてハードルを上げさせる。
Posted by
タイトルにある「技術」の通り、説明は練習をすれば改善することができます。 どなたが書かれたか失念してしまいましたが、「生徒への説明の仕方が悪いと、場の雰囲気が濁る」という旨のことを読んだことがあります。 1日の間に授業でも学級の時間でも説明をする機会が多い教師だからこそ、自分の説...
タイトルにある「技術」の通り、説明は練習をすれば改善することができます。 どなたが書かれたか失念してしまいましたが、「生徒への説明の仕方が悪いと、場の雰囲気が濁る」という旨のことを読んだことがあります。 1日の間に授業でも学級の時間でも説明をする機会が多い教師だからこそ、自分の説明のスキルを伸ばしたいと考えています。 本書を読み、自分の説明はどうなのか、改めて振り返ることができました。 特に発見があったのは「子どもに理解を促す教師の説明 応用編」です。 以下、その項目です。 応用編① 喩える 応用編② 対比と類比 応用編③ 因果関係に気づかせる 応用編④ 対義語や類義語を用いる 応用編⑤ 極論・仮定を用いる 応用編⑥ 経験を想起させる 応用編⑦ 教師の経験を語る 応用編⑧ 学問の知見を生かす 応用編⑨ 体験をセットにする 応用編⑩ 挑発を入れる それぞれの詳しい内容は省略しますが、生徒にイメージや実感をもたせやすい説明の工夫が書かれていました。 一つひとつの工夫を使ってみるところから、説明力に向上につながっていくのでしょう。 前書の『指示の技術』にも通じますが、土居先生は教師だけがその技術を高めることを良しとしていません。教師が技術を高めていく中で、目の前にいる子どもの力を伸ばすことを見据えています。(『指示の技術』では子どもの「聞く力」を伸ばすことを大事にしていました) 本書では子ども自身の「説明力」を高めていくことを大事にしています。 土居先生は、その意義を①「わかったつもり」を解消する(p.110)と②理解を深める(p.113)としています。 子どもの説明力を向上させる指導技術の詳細は省略しますが、印象に残ったのは、教師自身がモデルとなること、子どもに説明させる機会を多くつくること、子どもの説明の評価をすることでした 「ペアで説明させ、機会をつくること」「全体で子どもが説明する際は、説明の評価を行うこと」を大事にしたいと考えています。 説明は意識をすればすぐに良くなっていきます。 説明について基礎から応用、子ども達の「説明力」を伸ばすことまで学びたい方におすすめの一冊です。
Posted by
一文要約 教師が説明力を磨くことで子どもの力をさらに引き出すことができ、それがひいては子どもの説明力向上につながる。 以下感想 「説明とは」というところに光を当てて、説明の意義、役割から丁寧に説明してくれていた。 題名にもあるとおり説明は技術であり、伸ばそうと思わなければ伸び...
一文要約 教師が説明力を磨くことで子どもの力をさらに引き出すことができ、それがひいては子どもの説明力向上につながる。 以下感想 「説明とは」というところに光を当てて、説明の意義、役割から丁寧に説明してくれていた。 題名にもあるとおり説明は技術であり、伸ばそうと思わなければ伸びないもの。しかし反対に、伸ばそうと思えば誰でも伸ばせるものだと改めて感じた。 この本を読んで説明を大切にするとはすなわち、子どもたちを一人の人間として尊重するということなのだろうと思った。 「言われた通りに動け」ではなく、「どうしてやるのか」「何を思って、狙っているのか」を子どもが納得して取り組めるようにするために説明の技術を高めていきたいと感じた。 自分自身の説明力を高めるためにまずは、基本の7項目ができているのかを録音などを通して振り返り、見直していきたい。 この本を通して改めて自分の説明力を見つめ直そうと思えた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
面白い。タイトルに使われている言葉が「話し方」ではなく「説明」と書かれている点からも、内容が説明に焦点を当てた具体的であるものということが分かる。 印象的だったのは、説明の役割の一つに「子どもの説明力を向上させる」といった内容が書かれていたことである。今までこのように考えたことはなかったが、教育現場である以上、この項目は必須だなと納得した。 これまでの土居先生の著書に、子どものやる気に火をつけることが教師の役目の一つであること、そのまま言うのではなく工夫して伝えることが教師に必要な力の一つであると言ったことが書かれていたように思う。(もしかしたら違う本かも…)そこに通じる内容であり、自分も教師力を高めるために実践していきたいと思った。まずは自分の説明を見返す(きき返す)ことから始めたい。 本書にはいろいろな具体例が出てくる。著者と作者の違いや低学年優先の理由など…それだけでも面白かった。 ○心に残った内容 ・発問は思考に働きかける、指示は行動に働きかける、説明はその中間。 ・分かったつもりを本当の分かったにするために、自分の言葉で説明させて、自身の知識や経験と結びつけさせる。 ・常に何のためにを問い続ける。 ・喩える…全く別物にたとえること。 ・説明が分かりにくいときは、長いですなととはっきり伝えて切る。 ・説明は自ら挙手できる発進型へ ・引っかかれる子、スルーしない子が賢い。
Posted by
- 1