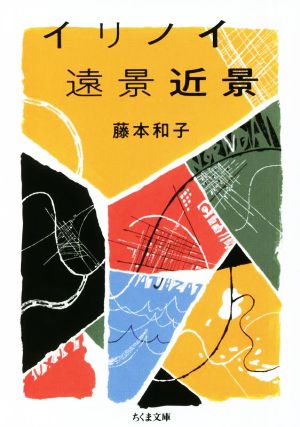イリノイ遠景近景 の商品レビュー
イリノイ州のシャンペンという街で暮らしている著者が、アメリカでの日常生活における人との関わりや、(恐らく取材での)インタビューなどを通して見聞きした言葉やできごとを綴るエッセイ集。会話が多いので、文字を本で読むというよりは音で聞いたような読後感があった。 巻末の解説でも触れられ...
イリノイ州のシャンペンという街で暮らしている著者が、アメリカでの日常生活における人との関わりや、(恐らく取材での)インタビューなどを通して見聞きした言葉やできごとを綴るエッセイ集。会話が多いので、文字を本で読むというよりは音で聞いたような読後感があった。 巻末の解説でも触れられていたが、著者が会話している相手は「社会の主流から離れたところに立っている人々」ばかりだ。それがとても人間臭いというか、「アメリカだろうがどこだろうが、人間はこうやって生きているんだよな」と妙にリアルな親近感を覚える。生い立ちや立場、環境はまったく違うのに、その人がそのように考えてそのように語るのがすんなりと共感できるから不思議だ。 どの話も面白かったが、私は「金山の天使島」が心に残った。中国から移民してきた人々が強制的に収容され非人道的な扱いを受けていた時に、壁にたくさんの漢詩を書き残していたというお話。 ❝ 彼女は書くこと、語ること、つまり知らせることは報じることで、それこそが復讐だという。 「復讐を意味する感じは『報』、『仇』である。報告は復讐である――打首がそうなのではない、腹を切ることがそうなのではない、言葉がそうなのである」 その彼女の考えを借りれば、「金山」へやってきて、不安と屈辱の日々を天使島でおくった人々はそこで反乱をおこし、蜂起することはたしかになかったが、ひたすら壁に文字を書きつけ、あるいは彫りつけることで、堂々と復讐していった、ともいえるのである。❞ (p.168) 生きた人間の語る言葉を聞き、ただ書き残すという営みは、私にはとても有意義で楽しいもののように思える。
Posted by
最初の方のアメリカの田舎の住民の日常会話の盗み聞きが非常に面白かった。途中、ドイツ滞在記のあたりは少々退屈。
Posted by
23/05/20読了 ギヴミーシェルターの最後、映画「ヨーロッパ、ヨーロッパ」の土台である自伝の作者、ドイツ人生まれのユダヤ人少年がヒトラーユーゲントの団員として生き延びた方のエピソードから、ガラリと景色が変わった気がした。 1992年頃に連載されたエッセイ集で、中のエピソードは...
23/05/20読了 ギヴミーシェルターの最後、映画「ヨーロッパ、ヨーロッパ」の土台である自伝の作者、ドイツ人生まれのユダヤ人少年がヒトラーユーゲントの団員として生き延びた方のエピソードから、ガラリと景色が変わった気がした。 1992年頃に連載されたエッセイ集で、中のエピソードはそれよりも以前のものもあるから、当時の大戦との近さを感じる。私も物心ついていたはずだけれど、そんな温度感は当然記憶にない。
Posted by
青山ブックセンターFBショップお勧め本から。 約30年前のエッセイ本だが、そんな昔を感じさせない。 世界を見る、知るということでは今が旬でもある。 というものの読み始めは、正直読みにくかった。 著者の後書きや岸本佐知子さんの解説を元に再読すると、すんなり受け入れられたのがあれ不...
青山ブックセンターFBショップお勧め本から。 約30年前のエッセイ本だが、そんな昔を感じさせない。 世界を見る、知るということでは今が旬でもある。 というものの読み始めは、正直読みにくかった。 著者の後書きや岸本佐知子さんの解説を元に再読すると、すんなり受け入れられたのがあれ不思議。 日本人という固定した視点ではない、様々な国を俯瞰してみることができる著者に敬服する。
Posted by
読むにつれどんどん深くなっていった。 聞く力がすごい。聞いて理解してさらに掘り下げて、と。こちらもついうんうんと頷いてしまう。
Posted by
1990年代のアメリカの市井の人々の日常を綴った面白いエッセイ とだけ思って読み進めたら大間違い。 中盤以降、テーマはさまざまなれどどんどん広く深くそしてますます面白くなっていく。 眼差しの先には、常に社会のメインストリートから外れた、外された人たちがいる。 彼ら彼女らの口から溢...
1990年代のアメリカの市井の人々の日常を綴った面白いエッセイ とだけ思って読み進めたら大間違い。 中盤以降、テーマはさまざまなれどどんどん広く深くそしてますます面白くなっていく。 眼差しの先には、常に社会のメインストリートから外れた、外された人たちがいる。 彼ら彼女らの口から溢れる言葉を丁寧に記録している。ハッとさせられる言葉にいくつも出会えた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
印象的なタイトルと表紙に惹かれて読んだ。近過去なおかつ異国における経験をつづったエッセイを読むのが久しぶりで新鮮でオモシロかった。 タイトル通りイリノイ州シャンペーンで生活する中で感じたことを徒然とつづっている。いわゆるカントリーサイドでの生活で派手なアメリカライフというよりローカルなアメリカの当時の空気を身近に感じることができる。それはカフェやドーナツショップでの街の住人たちの会話であったり、友人との旅行であったり、シェルターでの仕事であったり。観察眼の鋭さと落ち着いた文体が読んでいて心地よかった。どのエピソードも人が生きることへの興味が尽きないように思えたし、著者の生きることへの以下ラインが刺さった。 都会の雑踏や賑わいの中にいると、のびのびした気分になったものだった。うきうきした気分になったものだった。(中略)でもうきうきしてるだけじゃ生きていけないからねえ。 わたしもいよいよ生きなければならないのかな。そのためには息をする空間も必要なのかもしれない。子供までいるのだから。そう思って駐車場を眺めわたす。するとにわかに、ふん、この荒涼たる醜さも結構なのかもしれない、という映画の台詞みたいな言葉が頭にうかんだ。 あと著者の友人の以下ラインも生きることへの問いかけだと思う。 あたしが繋がれているのはこの街路だ。なのに、あたしは何をしている?大学院にまでいって、修士号までとって、結構な話だけど、あたしが繋がれているこの街路にとって、あたしは何者だろうか。 後半は著者によるインタビューがいくつか収録されており、これがかなり読み応えがあった。ユダヤ人やアメリカ先住民など迫害された人々にフォーカスしている。社会的に弱い立場になったときに何が起こるのか、格式張らないトーンで友人同士のような会話形式で書かれているので読みやすいし実感をもちやすかった。今でいえばポッドキャストを聞いているような感覚。著者は翻訳家としても活躍しつつ、本著の後半部のような、アフリカンアメリカンへのインタビュー集が二作文庫で出ているようなので読んでみようと思う。
Posted by
おすすめ資料 第537回 知らない町に住んでみて(2022.11.11) 自分が生まれ育ったのとはまったく違う場所に、しばらくの間住んでみたい。 知らない土地の、知らない人達が話していることを聞いてみたい。 カフェで、ジャクジで、占い部屋で。 現実にはむずかしいそんなこと...
おすすめ資料 第537回 知らない町に住んでみて(2022.11.11) 自分が生まれ育ったのとはまったく違う場所に、しばらくの間住んでみたい。 知らない土地の、知らない人達が話していることを聞いてみたい。 カフェで、ジャクジで、占い部屋で。 現実にはむずかしいそんなことが、 本を通してならできるのは、すごいことだと思いませんか。 このエッセイが気に入ったら、同じ著者のほかの本もぜひどうぞ。 【神戸市外国語大学 図書館蔵書検索システム(所蔵詳細)へ】 https://library.kobe-cufs.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00359449 【神戸市外国語大学 図書館Twitterページへ】 https://twitter.com/KCUFS_lib/status/1591989304363872256
Posted by
岸本佐知子さんのエッセイを全部読んでしまったので、面白いエッセイストを探している。 これは、岸本さんが解説を書いているので「面白いのかも」と期待して手に取った。 パラパラとページをめくって、ザックリ雰囲気をつかんで、まずは岸本さんの解説から読んだ。 面白いと、その箇所のページま...
岸本佐知子さんのエッセイを全部読んでしまったので、面白いエッセイストを探している。 これは、岸本さんが解説を書いているので「面白いのかも」と期待して手に取った。 パラパラとページをめくって、ザックリ雰囲気をつかんで、まずは岸本さんの解説から読んだ。 面白いと、その箇所のページまで記載している"盗み聞き"の2話は確かに面白かった。 生活には困らないが裕福でもない高齢者たちの、毎日きまって交わされているらしい勝手気ままな会話の盗み聞きで、 一つは、コーヒーショップに集まる親父たちの会話。 「鹿狩りに行って誤ってほかのハンターを撃ってしまった。」 「市民の寄付で集めた金を警察がいくらか横領した。」 「ボケ老人の金を騙し取る家庭が増えているから、自分はボケる前に自分の金は自分で使ってしまうのだ。」 といった、身近のちょっとヤバイ話。 もう一つは、スイミングに通う老婦人たち。 「あんたは毎日水泳するわりには随分太っているわね。」 「美は内面よ。大事なのは内面なの。」 といった、大阪のおばちゃん達のボケとツッコミを聞いているみたいな話。 盗み聞きで耳に入って来る会話って、普段は黙っていて言わないけど「そうだよネ」とか「絶妙な言い分けだ」と思ったりして面白い。 勝手に期待値を上げ過ぎたようで、350ページ中"盗み聞き"の20ページ以外は正直楽しめなかったので、★2つにしました。(ゴメンナサイ)
Posted by
1992年から一年半にわたって雑誌に連載された在米翻訳家による十八編のエッセイ。おおむね1990年前後、著者の50歳前後の出来事を題材としているようだ。執筆当時、著者がすでに九年住んでいたアメリカ・イリノイ州のシャンペンという小さないなか町が拠点となっており、これにアメリカの他の...
1992年から一年半にわたって雑誌に連載された在米翻訳家による十八編のエッセイ。おおむね1990年前後、著者の50歳前後の出来事を題材としているようだ。執筆当時、著者がすでに九年住んでいたアメリカ・イリノイ州のシャンペンという小さないなか町が拠点となっており、これにアメリカの他の都市や、ベルリン滞在記が加わる。約350ページ、5パート。各パートに2~4章の構成。 前半は喫茶店や美容室、プールのジャグジーといった市井の人々が集う場所からアメリカ市民一般の何気ない言動を伝え、のどかな人間観察記といった様相である。 後半以降は、黒人の女性ホームレスたち、ナチスドイツ時代を生きのびたユダヤ人、アメリカ先住民、移民といった、社会的弱者ともいえる人びとが主な対象となり、彼らの証言からそれぞれの人生をたどる。 インタビュー形式も含めて、多くの人々への聞き取りが含まれるのも本書の特徴だろう。 全体に落ち着いた文章で、コミカルさやユーモアは目立たない。また、後半で紹介される人々のシリアスな来歴はあっても、そこまで深刻な雰囲気に傾くでもない。折に触れて垣間見える著者自身の人生がユニークで、著者の過去に興味が沸くのだが、深入りせず素通りしてしまうのが残念だ。 全体に、良くも悪くも印象に残らず。解説を書いた岸本佐知子さんのエッセイが好きで、岸本氏が推すのならという気持ちも手伝っての購読だったが、個人的には刺さらなかった。
Posted by
- 1
- 2