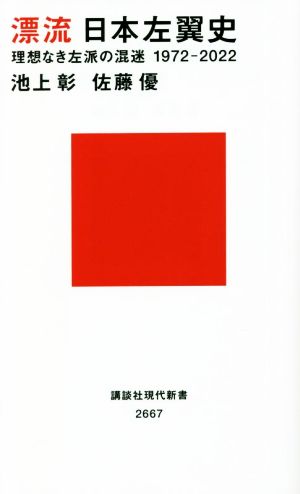漂流日本左翼史 理想なき左派の混迷1972-2022 の商品レビュー
このシリーズを読むのは初めてだけど左翼の歴史は割と血生臭い歴史なんだね。 今は昔に比べれば平和な時代で、何かに対して闘うなんてことは少ないので日本にもこんな時代があったと言う事実は、うっすらとは記憶してるけど改めて読むとちょっと衝撃。 機会があれば同シリーズの残り2冊も読んでみた...
このシリーズを読むのは初めてだけど左翼の歴史は割と血生臭い歴史なんだね。 今は昔に比べれば平和な時代で、何かに対して闘うなんてことは少ないので日本にもこんな時代があったと言う事実は、うっすらとは記憶してるけど改めて読むとちょっと衝撃。 機会があれば同シリーズの残り2冊も読んでみたい。
Posted by
このシリーズがこの本で完結するわけだが、現在行われているウクライナ戦争の位置付けが明確になった。読む価値のある本だと思います。
Posted by
シリーズの3冊目。 このお二人の本の中で最も価値のある本だと個人的には思いました。特に最近の左派、共産党、学生運動的なものについての考察は今までになく感銘を受けました。 いわゆる革命に対する成就への時間的感覚の差については指摘をされる機会が少ないように思いますが、様々なところで当...
シリーズの3冊目。 このお二人の本の中で最も価値のある本だと個人的には思いました。特に最近の左派、共産党、学生運動的なものについての考察は今までになく感銘を受けました。 いわゆる革命に対する成就への時間的感覚の差については指摘をされる機会が少ないように思いますが、様々なところで当てはまる根本的な背景であると感じる。 左派的な活動に親和性があったからこそ内部の実情というか、見えるものがあるのだろうと率直に。 詳細の名前や出来事は覚えてないし覚えようとも思わなかったですが、家にこのシリーズは置いておこうと思えます。
Posted by
なんと言っても、解説的立場を池上さんが務めるので、左翼思想、労働運動に疎い世代にも、わかりやすい。 また、佐藤さんの解釈・説明、博学さからの話題の広がりが、面白く、最後まで読み通せました。 左翼の将来像に薄暗くも灯りを照らして論じる最終章は好きです。 また、成田闘争の概説、土井元...
なんと言っても、解説的立場を池上さんが務めるので、左翼思想、労働運動に疎い世代にも、わかりやすい。 また、佐藤さんの解釈・説明、博学さからの話題の広がりが、面白く、最後まで読み通せました。 左翼の将来像に薄暗くも灯りを照らして論じる最終章は好きです。 また、成田闘争の概説、土井元衆議院議長のエピソード、バブル前後でのマスコミ人の急速なエリート化など、興味深いエピソードが散りばめらており、飽きずに読み切ることができるのではないでしょうか。 組合活動の報告書などで目にしたことのある用語や活動。これらには何の意味があるのか全く理解できなかったのですが、労働運動の残滓であることも、本書で理解できました。
Posted by
1.この本を一言で表すと? 現代の左翼がどうなってしまったのかを論じた本。 2.よかった点を3~5つ ・冷戦後も生き残った事実唯一の左翼政党である日本共産党が、ウクライナ戦争に対して「あらゆる戦争に反対する」と言う声明を出すことができず、逆にこのような祖国防衛戦争の論理を打ち出...
1.この本を一言で表すと? 現代の左翼がどうなってしまったのかを論じた本。 2.よかった点を3~5つ ・冷戦後も生き残った事実唯一の左翼政党である日本共産党が、ウクライナ戦争に対して「あらゆる戦争に反対する」と言う声明を出すことができず、逆にこのような祖国防衛戦争の論理を打ち出し始めたと言う事は、日本の左翼がもはや戦争の論理に完全に搦め捕られたと言うことを意味しています。(p177) →これは今いる共産党の議員に聞いてみたい。志位委員長の発言はあなたの考えと矛盾していないのか? ・国労や動労の場合は自分たちの運動がひとつのきっかけになって流通革命を招き、それが組織力低下につながっていったと言うのはなんとも皮肉です。(p111) →国鉄の労働運動と、ヤマト運輸の「宅急便」進出がちょうど重なっていたとは知らなかった。 ・左翼ではなく「アナキスト」(p40) →左翼とアナキストは似ているが、根本的には全く異なることはよく注意する必要がある。 ・国鉄職員の場合、正確にはストではなく順法(遵法)闘争が基本的な闘争の仕方でした。(p64) →スト権が無くてこのような手段で闘争していたのはり知らなかった。 ・共産党vs社会党・新左翼という分節化に基づいて日本左翼史を論じた本は他にない。(p183) →今まで共産党と社会党は同じ左翼との括りだったが、歴史的にも別物と考えた方が理解しやすいと思う。 3.参考にならなかった所(つっこみ所) ・左翼にとって価値判断の基準は「国家」でも「民族」でも「国民」でもない。基準は常に「階級」であり、戦争であろうと環境問題であろうと、「労働者階級にとってそれは何を意味するのか」と言う問題設定から全ては始まります。(p182) →現代では、「労働者階級」と言う言葉自体が死語になってしまったのではないか?だからそのような問題設定が今の日本社会ではできないのではないか? ・創共協定(p90) →共産党が公明党批判してたらしいが、池田大作と共産党は意気投合していたのでは? 4.議論したいこと ・左翼史を振り返って、今後に活かせる教訓は何か? ・今後の日本で左翼的価値観が見直される事はあるのだろうか? ・日本左翼史シリーズをお通してどのように感じたか? 5.全体の感想・その他 ・左翼の終焉という言葉が出てきているが、それは日本共産党のは変節ぶりに現れていると感じた。 ・日本の左翼は、少しでも考え方の違う人を受け入れなかったために自滅したのではないか、と自分なりに解釈した。 ・中曽根首相がいかに重要な功績を残したかがわかった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
図書館の新着コーナーで手に取った。3巻シリーズの最終巻だ。 社会党や社会民主党、日本共産党等の漂流について労働組合の盛衰とともに語られる。鈴木善幸首相から中曽根康弘首相による3専売公社の民営化により労働組合は衰退していっった。そして新自由主義のもとで労働組合や共産党など漂流をつづける。ただ、共産党は高齢化するとはいえ全国で27万人の党員を抱える組織だ。この漂流を止められるのか見守りたい。
Posted by
外山恒一による左翼史本を読んだ直後だったので理解しやすかった。 今の若者として、労働運動の盛り上がりってちょっと想像できず、上尾駅での暴動など当時の様子を興味深く思いながら読んだ。 共産党は、社会党の平和路線をうまく引き継ぐことでここまで生き残ってこられたということも理解できた。...
外山恒一による左翼史本を読んだ直後だったので理解しやすかった。 今の若者として、労働運動の盛り上がりってちょっと想像できず、上尾駅での暴動など当時の様子を興味深く思いながら読んだ。 共産党は、社会党の平和路線をうまく引き継ぐことでここまで生き残ってこられたということも理解できた。共産党は今苦しいだろう、ウクライナ戦争勃発の場面で「帝国主義のぶつかり合いだからどちらにも汲みさない。戦争反対」と日本で堂々と叫ぶことは可能だったのかと考えると… あと少し思ったのが、マルクスは革命には組織された労働者が担い手になると考えていて、そうではない末端労働者は「ルンペンプロレタリアート」といって馬鹿にしていたとの記述について。 まず、私は自分が組織されたプロレタリアートであることに無力感を抱き辛い気持ちになっているが、これはマルクスから見るとプラスなんだと知って目から鱗な気分になった。 私は自分の力で生きているフリーランスの労働者=ルンプロに尊敬の念を抱いてるけど、これはマルクス的観点からしたらおかしいんだなと思うとウケた。 とはいえ、今の時代、組織化されたプロレタリアートから革命なんて絶対起きないと思う。 だってその立場にいたら社会を変革する必要ないもんね。 社会が変わる兆しはルンプロにあるのでは?と私は考えます。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
たしかに労働者が団結することを希薄化させた政府の計略は成功したのだろう。しかし、自民党が備えていた、社会民主主義的な性格も、どんどんと失われた。結果として、現在の日本が、ますます張りぼて化していることも明確だ。 社会党の批判的な検証は、確かに必要だろう。 しかし、正直言って、批判的な検証が必要な政党は、他にもありそうな気がする。
Posted by
- 1
- 2