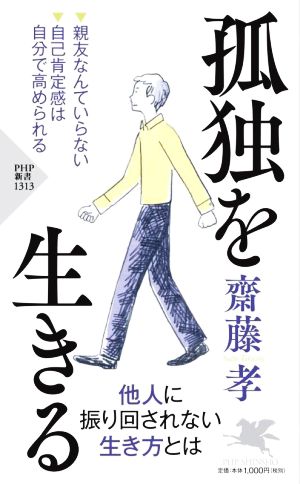孤独を生きる の商品レビュー
孤独に向き合ってきた先人たちの言葉や生き方を引用しながら進む本書。 緩く軽やかにつながっておく友人でいいのだ。あとはもっと本を読もう。私と同じような自意識やや性に戸惑いながらも向き合ってきた先人の作品に触れよう。 -- 友人関係というのは、会う頻度よりも「緩やかにつながってい...
孤独に向き合ってきた先人たちの言葉や生き方を引用しながら進む本書。 緩く軽やかにつながっておく友人でいいのだ。あとはもっと本を読もう。私と同じような自意識やや性に戸惑いながらも向き合ってきた先人の作品に触れよう。 -- 友人関係というのは、会う頻度よりも「緩やかにつながっている」ことが大事だと思いますね。 必要以上に自分を卑下したり、自分は自信がなく、メンタルが弱いことに対して周囲の理解を求めたりするのは、大人としてマナー違反であると認識する。 孤独感は「知性の力」で振り払う⎯⎯教養を身につけることを軸に生きていけば、孤独感はもはや敵ではなく、強く、豊かな人生の味方になってくれるはずです。
Posted by
福沢諭吉の言う「淡交」に賛成。 つかず離れず淡白に交流することが一番おたがのためになると頷きました。 斎藤先生の本でまた読みたい本が増えました!
Posted by
ひとりでいる時間が人生を豊かにするそうです。何だか矛盾した話にも思えますが、そう考えると少し気持ちが楽になるような気がしました。
Posted by
1人で読書を通じて先人と対話して、深みを増やす。 自分の中に泉を作るように、文化芸術に触れて、楽しみながら深さを積み上げたい。
Posted by
オーディブルにて読了。 最近齋藤孝さんの本を読むことが多く、何となく聴き始めたが想像よりも良かった。 読み進めていく中で、自分は孤独感は感じることがほとんどないな〜っと思ったが、読書をすると孤独を感じにくくなる?ようなことが書いてあり、なるほど、と納得。 その流れでお勧めの本紹...
オーディブルにて読了。 最近齋藤孝さんの本を読むことが多く、何となく聴き始めたが想像よりも良かった。 読み進めていく中で、自分は孤独感は感じることがほとんどないな〜っと思ったが、読書をすると孤独を感じにくくなる?ようなことが書いてあり、なるほど、と納得。 その流れでお勧めの本紹介もあり、参考にもなって良かった。 死についても、死は予防接種の順番待ちのようなものとあり、すごく腑に落ちる考え方だと思った。 スマホとSNSが発達した現代は、孤独感を感じやすい環境だなとあらためて感じた。 皆、もっとSNSと向き合う時間を自分で制限すれば孤独感ないのになと思った。今の10代の子とかは難しいのかもしれないけど。
Posted by
現代の「孤独」とは、大勢の中にいても誰とも つながっていない感覚を持ってしまう、いわゆ る「孤独感」を指すことが多いと思います。 しかしたとえ本当の孤独であっても、それは雌 伏の時ととらえ、自分の力を磨けばいいだけの 話だと思います。 ましては「孤独感」は考え方次第で全く見え...
現代の「孤独」とは、大勢の中にいても誰とも つながっていない感覚を持ってしまう、いわゆ る「孤独感」を指すことが多いと思います。 しかしたとえ本当の孤独であっても、それは雌 伏の時ととらえ、自分の力を磨けばいいだけの 話だと思います。 ましては「孤独感」は考え方次第で全く見えて くる風景が違ってきます。 自己肯定感を高め、孤独を「孤高」に生きる。 カッコいいですよね。 齋藤メソッドによる現代社会での生き方の伝授 の一冊です。
Posted by
先人たちの「孤独の教養」から学ぶ「単独者のススメ」 現代人の「孤独」が大きな問題だと言われている。 たしかに人間関係が希薄化するなか、孤独感を強く抱いて不安な日々を過ごしている人も少なくない。しかし 本来、孤独とは、人が自らを成長させるために必要な時間である。偉大な業績を打ち立て...
先人たちの「孤独の教養」から学ぶ「単独者のススメ」 現代人の「孤独」が大きな問題だと言われている。 たしかに人間関係が希薄化するなか、孤独感を強く抱いて不安な日々を過ごしている人も少なくない。しかし 本来、孤独とは、人が自らを成長させるために必要な時間である。偉大な業績を打ち立てた先人たちは、 例外なく膨大な「孤独時間」を通じて、事を為している だからむしろいま必要なのは、ひとりで行動することをポジティブにとらえること。自らの意思で孤独を貫き「単独者」として生きることだ「淡く浅い交わりを持て」「本は孤独の最高の解決策」など、知る限りの 「孤独の教養」が詰まった決定版。【本書の内容】 ・軽やかな人づき合い――「淡交」のすすめ ・「本」こそが孤独の最高の解決策である ・「孤独」を哲学すると見えてくるもの ・大きな孤独感でちっぽけな孤独感を洗い流す ・若者よ、「脱・友だち至上主義」を ・老いて復活する友だちづき合いもある ・「推し」のいる人生はすばらしい……etc.
Posted by
齋藤先生はメディアや著書でおおむね好感を持っていましたが、今回の本に関しては、孤独を勧めたり、人と群れるなとか、あまりに極端な内容にちょっと共感できないなと読んでいましたが、最後の老年期の孤独についての中で、 会社を退職するなどすると、社会から離れてしまって孤独感は増す、そういう...
齋藤先生はメディアや著書でおおむね好感を持っていましたが、今回の本に関しては、孤独を勧めたり、人と群れるなとか、あまりに極端な内容にちょっと共感できないなと読んでいましたが、最後の老年期の孤独についての中で、 会社を退職するなどすると、社会から離れてしまって孤独感は増す、そういう時は石垣をひとつづつ積み上げるように(実際そういう方を例に挙げ)日常の中で自分のできることを見つけ、コツコツやっていると社会にもつながるだろうし、横の広がりも増えるだろうとおしゃっていて、 今私がやっている音訳がまさにそれなんじゃないかとうれしくなってきたのでした。 斎藤先生ありがとう!
Posted by
孤独の乗り越え方、孤独の良さについて語られているが、はて、この本、本当に孤独な人向けなのだろうか?と感じた。孤独な人というのは、多分行動力があまりなく何にもできない場合が多いと思うが、著者の言う孤独の乗り越え方は少し、いや、かなり行動力を有しているが同時に孤独であるという不思議な...
孤独の乗り越え方、孤独の良さについて語られているが、はて、この本、本当に孤独な人向けなのだろうか?と感じた。孤独な人というのは、多分行動力があまりなく何にもできない場合が多いと思うが、著者の言う孤独の乗り越え方は少し、いや、かなり行動力を有しているが同時に孤独であるという不思議な方々を対象としているように感じた。完全に否定するわけではないが、これはむしろ行動力のある人向けであり、孤独とは言うが、孤独的修養法という修行的な生き方のすすめのような体裁である。だが、『孤独』というタイトルに騙されなければ、まあまあ良書ではないか? サブスクの垂れ流しについては私も取り入れたいと感じたが、万人に適応するかというとどうだろう。ある意味、玄人向け?であるように感じる。
Posted by
目次をパラパラっと読み これは面白そうなところの拾い読みでいいかなと 思いながら読む 「孤独」を「孤高」と表現するか… 「俺は孤独だからさ~」 「俺は孤高の人だから」 うん、確かに後者のほうがカッコええな 今日から、こう言おう 第3章 本こそが孤独の最高の解決策であ...
目次をパラパラっと読み これは面白そうなところの拾い読みでいいかなと 思いながら読む 「孤独」を「孤高」と表現するか… 「俺は孤独だからさ~」 「俺は孤高の人だから」 うん、確かに後者のほうがカッコええな 今日から、こう言おう 第3章 本こそが孤独の最高の解決策である この章は学びがありそう だが、初っ端 「戦争と平和」を読むときは、 私(トルストイ)が単独で苦しみながら4年かけて熟成させた作品です。 あなたは単独者として味わってください と言われて、プレゼントされたと感じ取るべき って…重いわ!! 齋藤先生、そんな読書術すすめてましたっけ汗 単独者としてオススメの本として 宮本武蔵の「独行道」 21項目(自分の快楽を求めない、女性と恋愛しない、趣味の世界に溺れない 住む場所にこだわらない、贅沢な食事を好まないetc) このうち、恋愛するなという教えに限ってはスルーしてもいいでしょう って…それだけですか!! わし、仙人の入門書かと思いましたけど汗 他に、寂しいときに 定番の曲をヘビロテする 私(齋藤先生)は学生からback numberをすすめられて 「高嶺の花子さん」を何度も聞きました。 俺も一時期、好きでよく聞いてたわ~ 齋藤先生と一緒や はっ、今、孤独感少しなくなった なーんて感じで軽く読みました。 この本はツッコミを入れながら、 いいとこ取りがいいんじゃないでしょうか 今回は、エッセイ風に感想を書いてみました。
Posted by
- 1
- 2