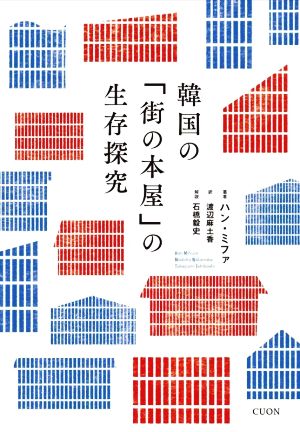韓国の「街の本屋」の生存探究 の商品レビュー
酷暑ビブリオバトル2024 決勝 3ゲーム目で紹介された本です。チャンプ本。ハイブリッド開催。 2024.8.12
Posted by
2029 かつては独裁者たちが思想の検閲をし、本を奪ってきた。いまは資本が本の多様性を奪っている。資本主義の時代に本の多様性を守る砦となるのは、それぞれスタイルが異なる街の本屋たちだ。本屋の多様性が失われれば、人びとが本と距離をとる暗鬱な未来が訪れるだろう。 妹とさんざん遊...
2029 かつては独裁者たちが思想の検閲をし、本を奪ってきた。いまは資本が本の多様性を奪っている。資本主義の時代に本の多様性を守る砦となるのは、それぞれスタイルが異なる街の本屋たちだ。本屋の多様性が失われれば、人びとが本と距離をとる暗鬱な未来が訪れるだろう。 妹とさんざん遊ぶと、「ちょっと休憩する」といって、本を読む。二〇分も、三〇分も本を読み、 それから再び妹と遊ぶ。 本を読むことで、息子は自分の呼吸を整えているような感じがする。妹と遊べば、当たり前だが、 自分の思う通りにはならない。ましてや、学校にいるあいだなんて、なにひとつ思いどおりには進まない。 そんなとき、彼は本を読む。自分のペースでページをめくり、作者の声を自分の声に吹き替えて、 本の世界でゆったりと、作者や登場人物たちとなにがしかについて語り合う。 ぼくが尊敬するある作家は、本の世界がホームだ、といった。つまり、本を読んでいるときが落ち着くときで、あとはすべてアウェイなのだという。本を愛するひとがみなそうだとは思わないが、こ の感覚を理解できる人はそれなりにいるだろう。息子もきっと、作家のいっていることがわかると思 う。本の世界が読者にくつろいだ気分を与えるとするならば、本が並ぶ世界もまた同じはず。読者たちは何らかの必要性に駆られて本屋さんに来るのではない。なんとなく気分の赴くままに本 屋さんにやってきて、そこで思い思いに時間を過ごす。そこには気の合う友だち同士で来ている者も いるし、カップルや家族連れもいる。でもなんといっても、いちばん多いのはひとりで来ている読者 我々は顔も名前も知らないその読者たちにまじって、顔も名前も知らないたくさんの作家たちの名前が印刷された本の背を指でなぞる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
歴史、表現や言論の自由の違いはありながら、韓国と日本の本屋事情はよく似ている。韓国の本屋さんの周辺を知ることで、日本の本屋さんの過去現在、未来に思いを巡らせた。石橋さんの解説がまたとてもわかりやすくて、良い!翻訳もののノンフィクションの新しい形だと思ったし、本を愛する人ならではの、読者への寄り添い方でもあるな、と思った。 学びの多い一冊であったと同時に、どんな規模の、どんな形態の店でも、本屋は絶対なくなっちゃいけない、と心の底から思えた。
Posted by
韓国でも本離れなど、本にまつわる問題は日本と変わりない。しかし、韓国各地に個性的な街の本屋は増えており、「本屋巡り」が定着しているらしい。 この本は、街の本屋を丁寧に取材し、その盛衰を描くことにより、韓国の本の生態系に深く切り込んでおり、学ぶ点が多かった。
Posted by
本は、「商品」でありながら「文化財」でもある。(160頁)「商品」ではあるのだが、一般的な商品と同じように扱えば、本の固有値価値と存在意義は失われる。本がスーパーに並ぶ工業製品と同じように、中身に大差のない「品物」になったら、思想を統制された独裁国家でもない限り、客は本を見捨てる...
本は、「商品」でありながら「文化財」でもある。(160頁)「商品」ではあるのだが、一般的な商品と同じように扱えば、本の固有値価値と存在意義は失われる。本がスーパーに並ぶ工業製品と同じように、中身に大差のない「品物」になったら、思想を統制された独裁国家でもない限り、客は本を見捨てるはずだ。(161頁)本は洋服のように手に取って満足できるわけでもなく、最後まで読んでみないと良さが分からない。時間も使うし、座りっぱなしで体も痛くなるし。そのような読書習慣がある人にもない人に本を提供する場所づくりの思いを知りました。
Posted by
- 1