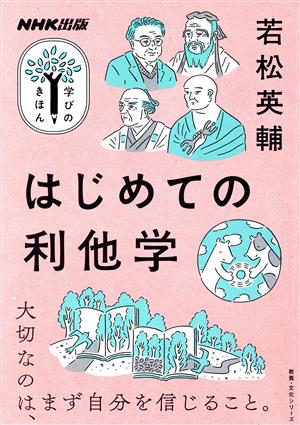学びのきほん はじめての利他学 の商品レビュー
ちょっと個人的には、後半につれ内容が難しかったです(おっしゃっている意味はわかるけど、腑に落ちるまで至っていない感じ)。まだ理解が追いついていない部分が結構あるので読み返しながら深めていこうと思います!
Posted by
まず読みやすい。 いろんなシリーズを読んでみたい。 私は自分のことが好きだけど信頼はして無いのかも。信頼と期待は別なのかな。 私は考えすぎるところがあるからまずは行動したい
Posted by
いい本だったなあ。哲学的にもほんとに入門編って感じで小難しくないし、「もっと余裕があれば人に優しくできるのに!」っていう私の最近の悩みを言語化して噛み砕いてくれた気がした
Posted by
449 若松英輔 1968年新潟県生まれ。批評家、随筆家。2007 年「越知保夫とその時代 求道の文学」にて第14 回三田文学新人賞受賞。2016年『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』にて第2回西脇順三郎学術賞受賞。2018年詩集『見えない涙』で第33回詩歌文学館賞を受賞。201...
449 若松英輔 1968年新潟県生まれ。批評家、随筆家。2007 年「越知保夫とその時代 求道の文学」にて第14 回三田文学新人賞受賞。2016年『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』にて第2回西脇順三郎学術賞受賞。2018年詩集『見えない涙』で第33回詩歌文学館賞を受賞。2018年、『小林秀雄 美しい花』で角川財団学芸賞を受賞。2019年、『小林秀雄 美しい花』で蓮如賞を受賞。著書に『井筒俊彦 叡知の哲学』(慶応義塾大学出版会)、『生きる哲学』(文春新書)、『霊性の哲学』(角川選書)、『悲しみの秘義』(ナナロク社)、『イエス伝』(中央公論新社)『霧の彼方 須賀敦子』(集英社)『言葉の贈り物』『弱さのちから』(亜紀書房)など。 エゴイズム 身体の 境目 と結びついた思考であり、快楽を選び 量るように、苦しみや病気を 予見 し遠ざけることに 専心 した思考である。もしエゴイズムが魂から、 恥ずべき情感、 卑怯 さ、 過ち、悪徳を遠ざけるために魂を監視するならば、エゴイズムは一種の徳となるだろう。しかし、エゴイズムはその用法上、意味の拡大を禁じている。 皆さんが通った学校にも金次郎の像はあったでしょうか。私が通った小学校、中学校にはありました。昭和期の後半まで、 寸暇 を惜しんで勉強する二宮金次郎の姿は、学ぶ者の 模範 だったのです。薪は「労働」、本は「学問」を象徴しています。働くことと学ぶことのあわいに真実を見出していくこと、それが幼い頃からの彼の生き方でした。 金次郎は、今の神奈川県小田原市に生まれました。幼いときに両親を 喪い、 伯父 の家に預けられます。金次郎は幼い頃から学ぶことに目覚めていました。しかし、伯父は学ぶことよりも働くことを命じます。夜、火を 灯して学ぶ金次郎に、その油代すら節約するようにいいました。それでも、金次郎は学ぶことを諦めません。彼が選んだのは、 菜種 を自分で育て、油を自分の手で作って学びを続けることでした。この経験は彼の生涯を決定します。 成人して名を「尊徳」と改めた彼は、役人として関東各地の貧しい村の復興に 奔走 し、およそ六〇〇の村が尊徳の方法(のちに「 報徳仕法」と呼ばれます) によって救済されたと伝えられています。 現代でも財政 破綻 した地方自治体がありますが、尊徳はそうした危機にあった地域を再生させた人なのです。財政が破綻するということは、田畑が荒廃しているだけではありません。そこに暮らす人は希望を失い、まさに道に迷った状態にある。そういった村々を訪ね、人々を励まし、財政を立て直しました。その手腕が卓越していて、小田原藩だけでなく、他藩、さらには幕府に登用されるまでに至ります。
Posted by
利他とは何か。東洋、西洋の哲学や宗教を横断し、様々な観点からスポットライトを当てる。 仏教から「自利利他」「菩提心」、「愛語」、儒教から「仁」、「知行合一」、キリスト教からパウロの「愛」、そしてフロムの「愛」へと、論は飛び回る。 結局、人間は社会的生物であることからは逃れられ...
利他とは何か。東洋、西洋の哲学や宗教を横断し、様々な観点からスポットライトを当てる。 仏教から「自利利他」「菩提心」、「愛語」、儒教から「仁」、「知行合一」、キリスト教からパウロの「愛」、そしてフロムの「愛」へと、論は飛び回る。 結局、人間は社会的生物であることからは逃れられず、古今東西あらゆる人が「人とどう関わるか」について論じてきたということだ。 そして、「固有の自分」自身を許し、受容れることを第一歩にし、同様に他人も受容れていくことが寛容だということだ。それは知識だけでなく、実践を伴わないと意味がない。この実践をどれだけできるかが、人生の豊かさを左右するのだろう。 本書を通じ、フロムの著作を読みたくなった。
Posted by
優しく書いてあるんですが、それでも私には少し難しかった。流して読まずに、キチンと理解しながら読む必要あるし。 3回くらい読めば理解できそう。 最後に 愛 については理解できました。
Posted by
私も利他について勘違いしていました。利己の反対語かと思っていたが、そういう訳では無い。その説明から本書は始まります。利他とは自分を活かし他者も活かすこと。 誰でも場面ごとに自分を変えている時間の方が多いく、思ってもいないことを口にしながら生きることがある。と書かれています。確か...
私も利他について勘違いしていました。利己の反対語かと思っていたが、そういう訳では無い。その説明から本書は始まります。利他とは自分を活かし他者も活かすこと。 誰でも場面ごとに自分を変えている時間の方が多いく、思ってもいないことを口にしながら生きることがある。と書かれています。確かにその通りかもしれない。 そのように自分を失ってしまえば、自分を愛することはできない。自分を愛することができなければ、他者を愛することもできない。つまり、利他を実行することができないということ。 著者は自分を深く信頼することが、自分を愛することにつながるとも言います。利他を実行するために信頼できる自分を形成していくようにする。
Posted by
自利利他という言葉に出会えてよかった。どこまで自を広げていけるか、それが利他につながっていくのだと思った。
Posted by
利他ということをこれまで勘違いしていたことに気付いた。自他他利は2つで1つ。そして、ここでも自分を信じること、自信を持つこと、そこから始まるということが書かれており、課題だなと思う。
Posted by
利他を端的に表す言葉は西洋に少なく、東洋には多いために現代日本人には分かりにくい概念となっている。我が国で利他を初めて使ったのが空海であるが、その概念を洗練させたのが最澄であった。そして最澄から親鸞が生まれるのであるが。利他の利を理解するために儒学から解き起こし、利他を生きた人と...
利他を端的に表す言葉は西洋に少なく、東洋には多いために現代日本人には分かりにくい概念となっている。我が国で利他を初めて使ったのが空海であるが、その概念を洗練させたのが最澄であった。そして最澄から親鸞が生まれるのであるが。利他の利を理解するために儒学から解き起こし、利他を生きた人として吉田松陰、西郷隆盛、二宮尊徳、中江藤樹をあげる。西洋のりたはコントから解説し、最後はフロムの愛について、でまとめるが、自分を愛せない人は他者も愛せないということ。
Posted by
- 1
- 2