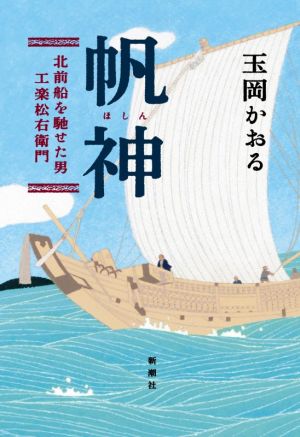帆神 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
不幸な事故で弟を失った蔵元の娘、千鳥と、残念ながら結局は死んでしまうその弟を救った漁師の息子、牛頭丸、のちの工楽松右衛門。故郷、高砂を離れて船乗りになってからは兵庫の津、北風屋で働く小浪などとのさまざまな出会いを積み重ねながら成長していく。折々に出会う登場人物も魅力的で、水主、船頭となり、帆布を発明し、実業家となり、択捉に港を開く際の彼の働きは実に魅力的だ。
Posted by
▼配架・貸出状況 https://opac.nittai.ac.jp/carinopaclink.htm?OAL= SB00549288
Posted by
本書は、播州高砂の漁師から身を起し、北前船を駆ける海商にまでのし上がった松右衛門を描いた長編歴史小説。「松右衛門帆」の開発のみならず、弁才船の瀬戸内海、日本海、また、江戸海運における活躍、特に港の出入りやその航海の様子が具体的にイメージできるエンターテイメントとしてもお薦めの一冊...
本書は、播州高砂の漁師から身を起し、北前船を駆ける海商にまでのし上がった松右衛門を描いた長編歴史小説。「松右衛門帆」の開発のみならず、弁才船の瀬戸内海、日本海、また、江戸海運における活躍、特に港の出入りやその航海の様子が具体的にイメージできるエンターテイメントとしてもお薦めの一冊。 莚帆(むしろほ)に代わり刺帆(さしほ)と呼ばれる木綿帆が一般の廻船に普及したのは17世紀後半からだが、18世紀になると廻船の帆走常用化が進み、刺帆の強度不足が廻船業者と船乗りの悩みの種となった。本書で扱う「松右衛門帆」とは、石井謙治著「図説和船史話」によると「帆装の改善の一つに松右衛門帆の出現がある。これは天明5年(1785)、工楽松右衛門が創製した木綿帆で、太い木綿糸を縦糸・横糸ともに二筋にして織ったごく厚手の布地。刺帆に対して織帆(おりほ)とも呼ばれ、二倍近い価格にもかかわらず大いに歓迎され、文化年間(1804-1817)には全国的に普及した」とある。また、同氏著「和船Ⅰ」の解説では、「縦糸・横糸とも刺帆とは比較にならない太い糸で織っており、その厚さからみても強度は優に刺帆の数倍はあった。しかも刺帆では宿命的につきまとう縫い合わせの手間が一切不要となり、技術革新の意義は極めて高い。一端の幅はのちに76センチにほぼ規格化され、機織りの改良から始めなければならなかったはずだから、松右衛門の苦心は太い糸を作るのと同時にこの点にあったのではないかと思われる」、 さらに高値については、「丈夫さからくる耐用年数の増大とか手入れに要する時間や費用の減少が、値段の高さを補って余りがあった」ので、 速やかな普及になったとしている。さらに強風下での帆走が可能となり、「結果的に航海の所用時間の短縮と風待ちを大幅に減らせる効果を生み出した」と解説をしている。江戸時代後期の廻船航海スピード向上にこの「松右衛門帆」の発明があるわけだ。江戸時代の技術革新をテーマにした小説は色々あるが、弁才船の特定技術を採り上げた長編歴史小説は珍しい。本書によれば、工楽松右衛門の「工楽(くらく)」とは「工夫を楽しむ」から来たそうだ。 和船の専門的な知識となると石井謙治氏の著作に頼ることが多いと思うが、特殊な和船専門用語では混乱してなかなか理解が進まぬところもある中で、本書を通じて往時の弁才船の運航イメージが大きく膨らんだ。
Posted by
新田次郎文学賞 舟橋聖一文学賞 海洋ものは好きなのだが、今回なぜかなかなか読み進められなかった。 先日、著者の講演会があり、やわらかい関西弁で、わかりやすい画像も駆使し、さすが大学の先生、 それにテレビのコメンテーターだし、と思うほど、楽しい講演だったのだが。 しかし、今まで読...
新田次郎文学賞 舟橋聖一文学賞 海洋ものは好きなのだが、今回なぜかなかなか読み進められなかった。 先日、著者の講演会があり、やわらかい関西弁で、わかりやすい画像も駆使し、さすが大学の先生、 それにテレビのコメンテーターだし、と思うほど、楽しい講演だったのだが。 しかし、今まで読んだ本には書いてないような情報が多く、取材はかなりしたのだろうなと思う。
Posted by
2022.8 最初のうちはごちゃごちゃしていて、半ば過ぎてから人物が少なくなって物語的に勢いが出てきた。そして最終コーナーを回るとまたごちゃごちゃ… いい話だとは思うんだけど今一つリズムが私には合いませんでした。
Posted by
気持ちのいい小説でした。立身出世談だけど誠実で公共心に溢れるものづくりの大好きな日本人の原型のような海商の話。
Posted by
兵庫、高砂にこういう人が居たの知らなかった。 海運並びに北前船がなぜ江戸時代、経済の根幹になり得たのか理解を深める切っ掛けとなりそう。
Posted by
また たくさんの事を知る事が出来ました。 松右衛門さん が スゴすぎ 素敵すぎです。 船の事 湊の事 時代背景 などなど 色々な事がどっしり詰まっています。 私も高砂の海をみてみたい! 「年をとるというのは、力を得るということ。時間を味方にできたということやったんや」
Posted by
北前船、北回り航路、高校の日本史で暗記したが、いまいち何のことか分からなかったことが、30年たってようやく理解できた1冊。日本の地理と時代背景がないとなぜ日本海航路が中心なのかわからない。ストーリーは一人の男が水夫から大船主になる、ありふれたサクセスストーリー。しかし背景にある、...
北前船、北回り航路、高校の日本史で暗記したが、いまいち何のことか分からなかったことが、30年たってようやく理解できた1冊。日本の地理と時代背景がないとなぜ日本海航路が中心なのかわからない。ストーリーは一人の男が水夫から大船主になる、ありふれたサクセスストーリー。しかし背景にある、船の製造工程、商いの仕組み、身分制度に派生する幕末の外交姿勢など、サイドメニューが抱負で、学ぶことが大きい一冊だった。繰り返すが、北前船の意義を理解したことが、すごい収穫として感じられた。なぜだろう。高校時代から引っかかっていたのだろうか。
Posted by
兵庫ラジオカレッジ 玉岡先生のお話はわかりやすくて興味深い! 物語の背景と人物に理解が深まると 歴史が面白くなっちゃいますね 北前船の帆を極めた主人公 そして玉岡先生お得意のそれを支えた女性たち 生き生きした物語が期待できます
Posted by
- 1
- 2