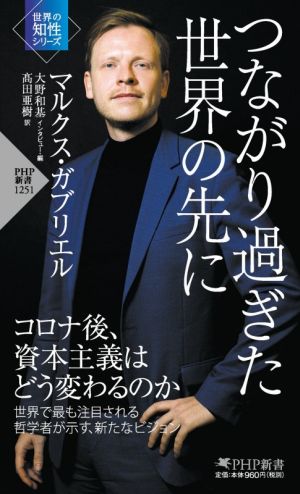つながり過ぎた世界の先に の商品レビュー
コロナの頃に書かれていた本ですが、哲学者の言うような世界になっているのでしょうか?ますます混沌とした社会になってるような気がして仕方ありません。それほど世界は単純じゃない、のかもしれません。SNSと距離を置いたほうが良さそうです。
Posted by
Audibleにて。 陰謀説が流行るのも、ステレオタイプ思考が表に出てくるのも根は同じなのかもしれないな。未知のもの=予測がつかないものは不安だから。同じ人間がやってる=「悪意」と解釈すれば、まだ想定の範囲内。その方が相対的な不安感は下がるのだろう。 人の脳は予測とその結果...
Audibleにて。 陰謀説が流行るのも、ステレオタイプ思考が表に出てくるのも根は同じなのかもしれないな。未知のもの=予測がつかないものは不安だから。同じ人間がやってる=「悪意」と解釈すれば、まだ想定の範囲内。その方が相対的な不安感は下がるのだろう。 人の脳は予測とその結果のズレによって自己に含まれるか、そして安全な環境かを判断している。同類の人間が抱いた悪意なら、パンデミックも世界の終焉も腹は立つけど仕方がいない…ということかな。反射による恐怖の処理だ。それくらいには追い込まれているからそうなる。 一方で、パンデミックはチャンスだったのかもしれない。「怖いのは分かる。でもだからこそ反射的な判断をするな。もう一度、人間とはどうあるべきかを対話によって考え直せ」というメッセージが投げかけられた…それ故に。 人間全体にとって良いことをしましょうというのが倫理。それに基づいた倫理資本主義の提唱。繰り返されるゼロサムゲームでは、結局のところ貧しく、破綻に向かっていくしかない。あらゆる判断、活動を倫理を軸にというのは納得の主張だ。ブリザードの中、螺旋を描くことで生き残る北極だか南極のペンギンたちに思いを馳せる。
Posted by
哲学界のロックスターと言われるマルクスガブリエルの本を一冊読んでみたくて手始めに読んでみました 印象に残ったのはパンデミックの見解について。 最近、100分de名著でショックドクトリンを観たのですが、ショックに漬け込んで資本主義政策(公営の民主化)を推し進める怖さを知ったので...
哲学界のロックスターと言われるマルクスガブリエルの本を一冊読んでみたくて手始めに読んでみました 印象に残ったのはパンデミックの見解について。 最近、100分de名著でショックドクトリンを観たのですが、ショックに漬け込んで資本主義政策(公営の民主化)を推し進める怖さを知ったのですが、パンデミックでショックドクトリンの逆バージョンみたいなこともできるのだなと感心しました。 具体的にはロックダウンを利用して人々を森へ行かせる。 経済活動を止めることで、経済活動以外の価値に気付かせる政策はいっぱいできたのかもなって思いました。 ただ、恣意的なものを感じさせた時のバッシングみたいなものは想像できるので、押し付けるのではなく、私が考える良さをアピールするくらいに留めるのが良さそうに思うのは、私がヘタレだからでしょうか。 あと、30分早く行くために山にトンネルを掘る必要があるのか!? という問いはすごく考えさせられました。 ここを通過する人の30分の価値の総和みたいなものから経済価値は算出できて、経済合理性のもと判断できるのだと思うけど、この試算には経済以外の価値が取りこぼされてるのですよね。 まもなくリニア新幹線が開通しますが、その効果とそれにより取りこぼしたものとの比較は永遠にできないんだろうな。 赤ちゃん学の本で、赤ちゃんがお座りできたらすぐに立つことを覚えさせるのではなく、お座りした景色をまずは楽しませてあげよう、と言っていたのが印象的で、今の景色をまずは楽しむ、というのがまずは大事な気がしています。 世の中、課題は山積み。課題を一つ解決したからと言って世の中の全ての課題を解決できたわけではない。課題を解決し続けた結果、最終的に新たな課題が生まれた、という結果になることも往々にしてある。 まずはその課題が克服できたことを喜びたい。 全体の感想というより、私が印象に残ったことを膨らませた感想となりました。まぁ、いつものことですり
Posted by
先だって読んだ本「人生百年の教養」に著者の亀山郁夫先生がこの本から「幸せになれるゾーン」が人間にはあると引用していたのでマルクス・ガブリエルの「つながり過ぎた世界の先に」を読んでみた。 最終章に「人には幸せになれるゾーンがある。ゾーンは人によって違う。このゾーンをみつけられたら...
先だって読んだ本「人生百年の教養」に著者の亀山郁夫先生がこの本から「幸せになれるゾーン」が人間にはあると引用していたのでマルクス・ガブリエルの「つながり過ぎた世界の先に」を読んでみた。 最終章に「人には幸せになれるゾーンがある。ゾーンは人によって違う。このゾーンをみつけられたら、それは自分の運命。そしてその運命が幸せをもたらす。」と書いてありました。 パンデミックはじめの頃書かれた本ですが、トランプ大統領の政策 コロナ対策、外交、経済など間違ってなかったと論じてます。コロナがなければ選挙に勝っていたろうと言ってます。マスコミが彼を悪役にしたてたと。ガブリエルはメルケル首相は世界最高の指導者だとも礼賛して、倫理資本主義が広まることを行動している哲学者です。
Posted by
考えを整理するとき、哲学者の助けがあった方が良いケースはあるのだと思う。マルクス・ガブリエルは分かりやすく噛み砕いて、自分の考えを伝えようとする宗教者のようだ。 倫理資本主義とは「“人と社会にとってよいこと”を判断軸とした資本主義」のこと。 社会性と経済的(儲け)を高いレベル...
考えを整理するとき、哲学者の助けがあった方が良いケースはあるのだと思う。マルクス・ガブリエルは分かりやすく噛み砕いて、自分の考えを伝えようとする宗教者のようだ。 倫理資本主義とは「“人と社会にとってよいこと”を判断軸とした資本主義」のこと。 社会性と経済的(儲け)を高いレベルで両立した経済のあり方とも言える。 ここで言う「社会性」とは、儲けの前に、まず人の幸せを本気で考え、顔の見える他者を想像する倫理性を持つこと。
Posted by
この本が特に印象的だったのは倫理的価値と経済的価値は同意であると話してるのは本当に印象的でした。 twitter含めてなんですが、近年、本当に倫理的に考えて発言しなくなってる事に危機感を覚える。 また、企業も含めて本当にひどいなと感じます。 改めて倫理の重要性を感じました。 特に...
この本が特に印象的だったのは倫理的価値と経済的価値は同意であると話してるのは本当に印象的でした。 twitter含めてなんですが、近年、本当に倫理的に考えて発言しなくなってる事に危機感を覚える。 また、企業も含めて本当にひどいなと感じます。 改めて倫理の重要性を感じました。 特に恋愛、仕事、婚活において! 倫理と経済 これは今後大事だと感じさせる本です。
Posted by
科学に関するところは怪しすぎたのですが、後半はとても良い内容だった気がしました。 ステレオタイプによって他者を判断することは非倫理的であること、対話が必要であること、SNSが我々に自己を与えていること、などのところはかなり興味深く感じました。 この辺りは不必要に自己の属性について...
科学に関するところは怪しすぎたのですが、後半はとても良い内容だった気がしました。 ステレオタイプによって他者を判断することは非倫理的であること、対話が必要であること、SNSが我々に自己を与えていること、などのところはかなり興味深く感じました。 この辺りは不必要に自己の属性についてSNSを通して自ら確定してしまうというのは実際に感じるところで、他者に対する属性化も問題だとは思っていたのですが、反面自己を不必要に規定してしまうことが生きづらさを生む温床となってしまうのを感じました。 交友層の偏りがかなり出てるように見えるので自分がもっと広く対話したらどうかなと思いますし、哲学者を雇うべき的なところなど所々プラトン的にも思えますし、やってないことをいつでもやれるぜっスタンスで語るのは個人的には格好悪いと感じてしまいますし、歴史的経緯から倫理的に正しい自分であることを表明し続けなければならないドイツにおけるナショナリズムってこんな感じなのかなと想像したりもしました。 哲学はズブの素人なのですが、医学についての語りはだいぶ怪しかったので、同氏の専門以外の発言は、話半分くらいで考えようと思いました。
Posted by
日本人のインタビューアによる、マルクス・ガブリエルのインタビュー。audibleで聴く。 ウィルス学者が統治してはいけない、力を持っていけない、というのは、本当に良い意見であると思う。日本のコロナ対策は、専門家チームをまとめる尾身会長がかなりの発言権を持ってしまった。そのことが...
日本人のインタビューアによる、マルクス・ガブリエルのインタビュー。audibleで聴く。 ウィルス学者が統治してはいけない、力を持っていけない、というのは、本当に良い意見であると思う。日本のコロナ対策は、専門家チームをまとめる尾身会長がかなりの発言権を持ってしまった。そのことが、東京オリンピックを史上初の無観客によるオリンピックにしてしまった。このときに、日本にマルクス・ガブリエルのような人が、専門家チームの意見が力を持つような状況に声をあげて議論をしていけば、無観客を避けられたかもしれない。そういったことを考えてしまう。 トルコをEUに加盟させないのは、EUの最大の過ちという。なるほど。 人間の本質は、「答え」ではなく、「問い」なのです。良い言葉である。
Posted by
マルクス・ガブリエルは注目している知識人の1人なので、本書も手に取りましたが、とても満足しています。この手のインタビュー本ですと、内容がかなり薄くがっかりすることも多々あるのですが、さすが哲学者ガブリエルです、インタビュー用にわかりやすい言葉を使いつつ、かなり深いことも多数盛り込...
マルクス・ガブリエルは注目している知識人の1人なので、本書も手に取りましたが、とても満足しています。この手のインタビュー本ですと、内容がかなり薄くがっかりすることも多々あるのですが、さすが哲学者ガブリエルです、インタビュー用にわかりやすい言葉を使いつつ、かなり深いことも多数盛り込んでいました。ガブリエルは本書の中で「倫理資本主義」こそ我々が今後目指すべき道だと主張します。そしてこれは名称にもあるように資本主義と両立する、つまり今の資本主義の方向を修正すれば可能だというわけです。 倫理資本主義に向かうかどうかのカギを握っているのは「危機」です。実はガブリエルは、危機が生み出す全く異なる2つの推進力について本書で語っています。1つ目は、危機が人々を倫理的、道徳的にする力。しかし同時に、危機が恐怖を生み出すとしたら、それは非倫理的な行動を引き起こすわけです。ガブリエルは非倫理的な行動の背後には恐怖があると述べていますが、確かにパニックになると他人のことはどうでもよくなる、自分の生存だけに頭が向かうわけです。つまり「危機」は諸刃の剣であって、これをチャンスによりよい「倫理資本主義」に向かうこともできるし、ホッブズなどがいう「自然状態」になってしまう恐れもあるということでしょうか。まさに不安定な社会になっているわけです。 本書は「つながり」をキーワードにしていますが、著者が最後に神聖性についての見解を述べているのは秀逸だと思いました。つまり究極の「つながり」とは、言葉では表せない宇宙(全体)とつながっているというような感覚であって、人々はそれを得たときに神聖性を感じる、という主張です。仏教的な世界観もまさにそれを述べているわけです。そして芸術がそれを促進する、という主張もまさにその通りだと思います。個人的な話ですが、私はクラシック音楽のなかでもバッハとシューマンの楽曲を聞くと心が震えます。なぜかというと、彼らの楽曲を聴いていると、何か宇宙の真理がかなでる音、大乗仏教的にいうなら、大日如来がかなでている音楽はこういうものではないか、と感じるからです。ミヒャエル・エンデの小説「モモ」のなかに、主人公のモモが「時間のみなもと」を訪れるシーンがありますが、そこでは数えきれない種類の音がたえまなく新しいハーモニーを作り出している、という記述があります。そこではまさに、「私」を意識する人間という生命体が、宇宙(全体)とのつながりを実感しているのだと思います。
Posted by
一気に読み終えたが、あまり入ってこなかった。倫理的な側面が重要であることは理解する。資本主義がいまの形でよいとも思っていない。なぜ入ってこないのか。オンラインインタビューから構成しているようで、読んでいる側からするとやや散漫になっているからかもしれない。 マルクス・ガブリエル本...
一気に読み終えたが、あまり入ってこなかった。倫理的な側面が重要であることは理解する。資本主義がいまの形でよいとも思っていない。なぜ入ってこないのか。オンラインインタビューから構成しているようで、読んでいる側からするとやや散漫になっているからかもしれない。 マルクス・ガブリエル本は数多ある。よい本も多い。時間とカネは有限なので選別しないといけないと感じた。
Posted by