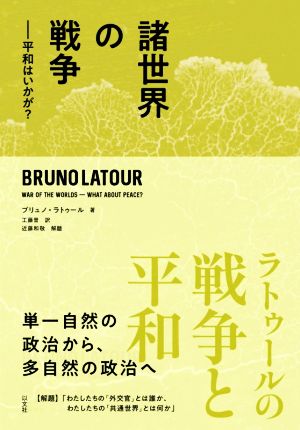諸世界の戦争 の商品レビュー
人類学(科学人類学)者ラトゥールの著書を初めて手に取る。工藤晋氏の「訳者あとがき」によれば、本書はフランスで行われたシンポジウム「諸文化の戦争と平和」のために用意された原稿をユネスコ特別号向けに再整理、2002年に英語版として出版されたもの。冒頭の章が「九一一」と題されているよ...
人類学(科学人類学)者ラトゥールの著書を初めて手に取る。工藤晋氏の「訳者あとがき」によれば、本書はフランスで行われたシンポジウム「諸文化の戦争と平和」のために用意された原稿をユネスコ特別号向けに再整理、2002年に英語版として出版されたもの。冒頭の章が「九一一」と題されているように、2001年のニューヨーク同時多発テロを受けた補筆がなされている。 戦争の原理的な考察にかかる内容かと思って購入したが、むしろ「この世界をどう見るか」という根源的な問題提起とも言える内容。「西洋」による「近代化」を自明な進歩・発展と見なすのではなく、具体的な暴力を伴った「戦争」と位置づけ、近代主義者は「戦争」を戦っているのに自らを「普遍」と欺瞞することで、日々の構造的な暴力と自分たちの世界の中での「内的な平和」の感覚とを両立させてきた、という問題提起は鋭い。例えば1990年代以降のイスラエルで起こってきたことは、「あたかも戦争などまるで存在せず、ただ西洋的な自然な〈理性〉を平和的に拡張するために警察力を使ってあまたの〈悪の帝国〉と戦い、それらを封じ込め転向させようとしているだけであるかのように振る舞」い続けたことの帰結ではないのか? ラトゥールがはるか彼方に見ようとする、「構成主義」的な立場に依拠した諸世界の共存を可能とする「和平」交渉の可能性は、ちょっと抽象的すぎてイメージが湧かなかった。しかし、先のくだりを読むことができただけでも本書を手に取った価値はあったと思う。
Posted by
- 1