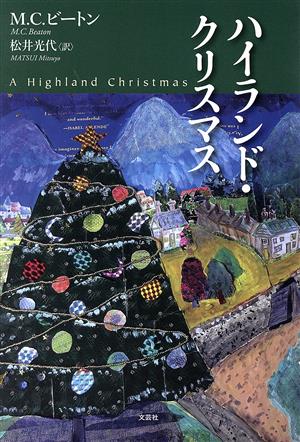ハイランド・クリスマス の商品レビュー
ありきたりな言い方をすれば、心温まる素敵な小作品。そのありきたりな褒め方がとても似合ういい作品でした。
Posted by
アガサ・レーズン・シリーズでおなじみの作家M.C.ビートンによる、ヘイミッシュ・マクベス・シリーズからの一冊である。 アガサ・レーズン同様、こちらも大人気のシリーズだ。 1985年に1作目が書かれて、以来次々と巻を重ね、計30巻、 『ハイランド・クリスマス』はその16作目である。...
アガサ・レーズン・シリーズでおなじみの作家M.C.ビートンによる、ヘイミッシュ・マクベス・シリーズからの一冊である。 アガサ・レーズン同様、こちらも大人気のシリーズだ。 1985年に1作目が書かれて、以来次々と巻を重ね、計30巻、 『ハイランド・クリスマス』はその16作目である。 シリーズ初の日本語訳は、今の時季にぴったりな一冊となった。 主人公はヘイミッシュ・マクベス、スコットランド極北の地サザーランドはロックドゥの巡査である。 若僧でもなくおっさんでもない年齢で、独身だ。 過去に女性となにやらあったらしいが、その経緯はわからない。 未訳の巻にその色々は描かれているのだろう。 しかし、村人はみんなそれを知っていて、楽しいゴシップとして口々に話している。 「私にプライバシーはないのか?」 ヘイミッシュが嘆いた。 「そうさ。生活にプライベートが欲しけりゃ、ロックドゥには住めないよ。・・・・・・」 (66頁) ロックドゥとは、そんな処だ。 だから事件の捜査も、聞き込みがとても重要で、簡単な方法なのだ。 「あの人は、いついつどこそこに現れて、なになにをしていったよ」 「あの人は、いついつあそこから来た人で、あの人から土地を買ったよ」 皆、たいへんによく知っている。 ずかずか土足で踏み込んできて迷惑なこともあるが、捜査となるとこれがたいへんに役に立つのだ。 ミステリーで事件というと、たいてい殺人なのだが、これはちがう。 猫がいなくなったこと、クリスマスツリーが盗まれたことという、血なまぐさいところのまるでない、牧歌的な事件なのだ。 話は全体にすっとぼけていて、読んでいるうちに、幸せな気持ちになりさえする。 それもそのはず、この『ハイランド・クリスマス』は、シリーズの中の「クリスマス特別編」という位置づけなのだ。 シリーズの他の作品は、原題がすべて「 Death of ~」で始まるという、ちゃんとした殺人事件のようだが、このすっとぼけたよい味は、それらの話にもあるのだろうか? 血なまぐささと相まって、対比の妙のようになるのだろうか? それを知って味わうためにも、シリーズの他作品もぜひ読みたい。 その際も『ハイランド・クリスマス』と同じように、飾っておきたくなる素敵な装丁であることを望む。 望んでいるのだが、一点だけ、気になることがある。 『ハイランド・クリスマス』の文中に、体言止めが散見されるのだ。 体言止めとは、名詞、代名詞で終わること。 つまりはこういう文章。 余韻を感じさせるとも言われるスタイル。 しかし、私がこれに感じるのは、弱さ、未熟さ、つたなさだ。 物事を断言することができない、意志のない幼さなのである。 児童書ならよいのかもしれないが、いい大人の登場する、いい大人の読む本にふさわしい文章とは思えない。 そもそも、ミステリーに体言止めは不向きなのだ。 「これはリンゴ。」 これで終わってもらっては困る。その後には、無限の可能性がある。 「これはリンゴです。」 「これはリンゴではありません。リンゴに見せかけた毒饅頭です。」 「これはリンゴが入っていると全員が思っていた箱です。」 はっきり示してもらわないと、それが謎なのか証拠なのか凶器なのか死体なのか不明になってしまうではないか。 繰り返すが、私はこのヘイミッシュ・マクベスが気に入って、ロックドゥの面々にも親しみを感じた。 シリーズの他の作品が読みたいのだ。 だから、その時には、この体言止めスタイルが無くなってほしいと願っている。
Posted by
- 1