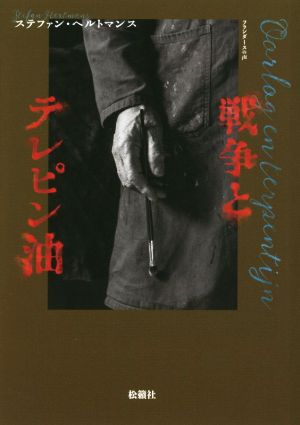戦争とテレピン油 の商品レビュー
『絵画作品を見る際、私が描かれた身振りに目を向けずにいられなくなっていたのは、歴史とは、潔白さではなく、罪悪に満ちた本を読むことであると理解したからで、それが自分自身の生の琴線に触れたのだった』 作家が祖父から手渡された日記を躊躇いつつ紐解き、そこに込められた思い、秘された事実...
『絵画作品を見る際、私が描かれた身振りに目を向けずにいられなくなっていたのは、歴史とは、潔白さではなく、罪悪に満ちた本を読むことであると理解したからで、それが自分自身の生の琴線に触れたのだった』 作家が祖父から手渡された日記を躊躇いつつ紐解き、そこに込められた思い、秘された事実を読み解く物語。どこまでが事実でどこからが脚色なのか、その境は不明。あたかも証拠写真のように挿し込まれるイメージが、抽象と具象の境をより淡くする。ああ、ゼーバルトに似ている、と思わず独りごちる。翻訳者による素っ気ないあとがきにも、作品の背景についての説明はない。 作家、ステファン・ヘルトマンスがゼーバルトの作品を意識していたことは間違いない。第三部の扉にはゼーバルトの「目眩まし」から引いたと思われる一文もある。しかしゼーバルトの小説が記憶の断片を散文的に散りばめたような作風であるのに対して、ヘルトマンスのこの小説は、余りに詳細で、余りに具体的で、時としてポール・オースターが書きそうな偶然の要素も入り混じる探偵小説のようでもある。 それでも、「先の大戦」が第一次世界大戦を意味し、列強の狭間で独立を守る多言語国家としての軋みを軍隊生活の中で味わった世代のベルギー人の人生を振り返るこの小説は、「フランダース」と言えば「犬」しか連想できない極東の人間に、欧州の歴史の綾の複雑さと解すことの叶わないその絡み合いの強張りのようなものをじんわりと伝える。全てが架空の小説であろうと、本当に作家が祖父から手渡された日記を元に想像した歴史であろうと、そこに描かれた現実は疑いようもなく重く読む者にのしかかる。 『場所とは、空間であるのみならず時間でもある。祖父の思い出を共有するようになって以来、街を見る目が変わった。考えを巡らせ続けていたカウテル広場は、催し事の場所として子供の頃から知っており、日曜の午前、両親の買った切り花の匂い、完璧に補修された野外音楽堂で演奏される管楽器の古めかしい山と結び付いている。しかし今はもの言わぬ建物の前面を見比べ、ブリュッセル出身の仕立屋トンビュイの店で数ヶ月間見習いをしていた祖父が呼び鈴を鳴らす、「洋服仲買人」ミスター・カルパンティエの店を探してみる』 普段、何も意識しないで通り過ぎるその場所が、不動不変のものである筈もないが、人は無意識の内にそれを常に存在するものと捉えてしまう。そして街並みの一区画が無くなってみて初めてそれが無常であることを知るが、更地になった後では何があったのかを思い出すことも難しくなる。言ってみれば、この小説はその「在った筈のもの」を懸命に手繰り寄せようとする行為を描いたものだ(そしてそれは、ゼーバルトの失われるに任せたような過去への態度と正反対のもののようにも見える)。よしんばその痕跡を突き止めたところで何かが解る訳ではない。作家自身とも読める主人公もそれは解っている。それでも、失ってしまった道標に自らの来し方を繋ぎとめようとするのが人の性(さが)なのかも知れない。
Posted by
- 1