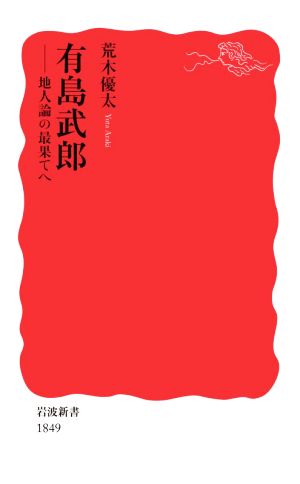有島武郎 の商品レビュー
辞書を引かなければ意味を知ることができない、それでもこの世に確かに存在している未知の言葉が、不意にあらわれて文章の一部分を硬く緊密に形象する。すべての語を消尽しようとする衝動と、すべての語に使役されんとする切迫とが、この本のなかで同居している。
Posted by
私の読書生活にとって、有島武郎はまったく縁がなかった。読みたいと思ったことがなかった。そんな中でこの本を読もうと思ったのは、ビッグイシューで“在野研究者”としての荒木優太さんのインタビュー記事を読んだからだ。 それにしても荒木さんはなぜ並みいる作家のなかから「有島武郎」に肩入れ...
私の読書生活にとって、有島武郎はまったく縁がなかった。読みたいと思ったことがなかった。そんな中でこの本を読もうと思ったのは、ビッグイシューで“在野研究者”としての荒木優太さんのインタビュー記事を読んだからだ。 それにしても荒木さんはなぜ並みいる作家のなかから「有島武郎」に肩入れするのだろうか?それが知りたかった。だって野球漫画で例えれば、巨人の星やドカベンではなく、アストロ球団に肩入れするようなものではないか? 荒木さんには失礼ながら私が意外だったのは、荒木さんの論調が、いわゆる個人的感想ではなく、有島作品を精読し詳解していたところ。在野とは言いながら、好き放題に自分の思いを書き散らすというのとは真逆のオーソドックスな研究者としての姿勢がまず良かった。 だけど荒木さんの論調は決して平易ではなかった。それは有島作品が元々一筋縄ではいかない要素を多く有しているからかもしれないが。 この本の各章は一見独立したような体裁のようになっていて、有島という1本の幹として捉えづらかったのが原因かもしれない。1つの章をやっと読み終えた、と思えば次の章ではまた新たな展開が、という感じの波状攻撃は、文学講読の基礎力がないと難儀すると思う(私は基礎を学んでいないので苦労した)。 だが、あえて私から1つポイントを言うとすると「何が何でも最後まで読め」につきる。 各章独立していると思われたものが、ある瞬間につながるように感じるはずだから。通しで読むことで、ようやく荒木さんが言わんとする有島の魅力に一歩近づけたような気がする。 そして最後に改めてこの本のエピグラフ――ソローの「森の生活」からの引用――「ごく小さな泉でさえ、その一つの値打ちは、それをながめていると大地は陸つづきではなくて島であることがわかることである。」(神吉三郎訳/荒木さんの引用は原文の英語による)の真意に辿り着けるという、考えられた構成になっていたことに最後の最後でやっと気づくことができた。 それはすなわち人間を形づくるおおもとの要素は畢竟“個性”なのだ、という考えに有島が紆余曲折しながら辿り着けたことと大なり小なり同じ道程なのかもしれないし、裏返して、“地人論”としての一つの到達点に辿り着けることにもなる。 荒木さんの文章は一見粗削りだから、もしかしたら誤解も多く生じるかもしれないと杞憂するけれど、私は荒木さんの“誠実さ”は確実に受け取れた。
Posted by
メモ→ https://twitter.com/lumciningnbdurw/status/1360731770195386372?s=21
Posted by
著者は在野の研究者(cf.『在野研究ビギナーズ』)。有島武郎研究を専門とする。 副題は「地人論の最果て」。地人論とは、地理的な場所と人の生み出す文明に関係を見出すものである。有島は、美術鑑賞において、作品はその生まれ育った風土にあってこそ真に理解されると説く。 だが、有島自身、果...
著者は在野の研究者(cf.『在野研究ビギナーズ』)。有島武郎研究を専門とする。 副題は「地人論の最果て」。地人論とは、地理的な場所と人の生み出す文明に関係を見出すものである。有島は、美術鑑賞において、作品はその生まれ育った風土にあってこそ真に理解されると説く。 だが、有島自身、果たしてどうだったのか。 ある地に根差して、その地を代表し、それを描き切るような作品を果たして生み出せたのか。 実のところ、 ある地に生まれたことの宿命を重く受けとりながら、かといってちゃんとしてナショナリストになれるわけでもない それが有島であり、そしてつまりは有島の作品群は(内なる矛盾を抱えて)「地人論の最果て」にあり、むしろそうであることこそが価値なのではないかというのが(いささかトリッキーな)著者の主張であるようである。 著者の言う意味とは少し違うかもしれないが、有島が私にとってどこか引っかかるのは、やはり純粋に作品そのもののみというよりもその生涯に依るところが大きいように思う。どこかちぐはぐな、どこか目指すところに行きつけなかったような、いや、そもそも目指すところが絞り切れなかったような、何だかそんな印象を受けるのだ。 育ちの良さゆえに純粋な理想を抱き、才能があるがゆえに自身の限界が見えてしまったのか。 「赤い鳥」で発表された『一房の葡萄』は、教科書にも採られたお話である。意地悪な言い方をすれば泰西名画の複製のように思えなくもないが、美しい先生の白い手が印象的な「よい」話である。 『小さき者へ』は妻が結核で亡くなった後、子供らに向けて書いたもの。若干熱に浮かされたような雰囲気を感じないでもないが、父である自らの弱さにも率直に触れ、なおかつ母を失った子供たちの背を力強く押す名文である。 『カインの末裔』は北の大地に生きる荒くれ男の物語。カインは旧約聖書の登場人物で、兄アベルを殺したため、楽園から追放され、耕作を行っても作物はできないという罰を受ける。男はいわばその子孫である。厳しい北の自然と、運命に咆哮するような男の荒みぶりが衝撃的ですらある。 裕福な家に生まれ、当時としては珍しくインターナショナルスクールに通い、長じて留学もする。キリスト教に入信するが、後、信仰からは離れる。札幌農学校に学び、農場を入手するも、後年これを小作人らに開放する。ジグザグとした道のりは、最後には夫ある女性編集者との情死に終わる。2人の遺体は死後、1ケ月を経て腐乱状態で発見されたという。 才もあり、理想もあり、しかしそれらすべてを以てしても、筆を折り、最終的には非業の死を遂げるという結末を迎えたのか。 何だかそのことに愕然とするのだ。
Posted by
- 1