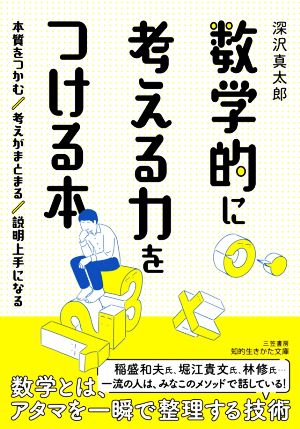数学的に考える力をつける本 の商品レビュー
公式を使ったりしなくとも、物事を論理的に筋道立てて簡潔に分かりやすく話す際に数学力は必要だと知り、なるほどなと思った。 簡潔に分かりやすい説明、間を空けることによって理解しやすくするプレゼンの仕方など、実生活で使えそうな数学的物事の考え方が沢山載っていて参考になった。
Posted by
個人的に大好き! 数学を論理的に考えて 数学は計算するものではなく 【数学は語学】と捉えている 計算は数学の中の【作業】でしかなく 数学の得意な人間はその【作業】をこなすのが得意になっているだけ…の人が多く 説明してみてと言うと 机の上ではスラスラ解けるのに 説明できない病...
個人的に大好き! 数学を論理的に考えて 数学は計算するものではなく 【数学は語学】と捉えている 計算は数学の中の【作業】でしかなく 数学の得意な人間はその【作業】をこなすのが得意になっているだけ…の人が多く 説明してみてと言うと 机の上ではスラスラ解けるのに 説明できない病が大半らしい 学校での数学の教育は 作業を教えてるだけ… 【円周率は?】と質問すると 3.14!!と答えるのがほとんどらしい… 聞かれてるのは~円周率の定義~なのに… 答えは円周の直径と円周の比率が…と言った話になるはず こんな感じで 数学は言葉にどう影響をもたらすか 物の見方をどう数学的に見れるか といった本です ま…俺 勉強出来ませんが(笑) ※だから結局俺が何を言いたいかって言うと… 【俺が個人的にこの人と仕事したくないな…って思うのはペン先をグリグリ潰すほど筆圧が強い人や、糸ミミズ?ってくらい筆圧弱い人って、なんか見てて不安になるよ】って事!!
Posted by
数学的に、というのが、なぜなら、つまり、かつ、などの接続詞で文章をつなげること、といったよくわからない理論が展開される。無理に数学に繋げているだけで、飛ばし読みで十分。
Posted by
小さなことからコツコツと→小さな成功の積み重ね。これに気づけたのがよかった。数学的かどうかはいまいちよく分からなかったけど、書かれていることを実行、訓練すると考える力が本当につくと思う。
Posted by
数学的に考えるとはどういうことか、を考えられる良い本でした。 結論として「数学的に考える=論理的に考える」であり数式を使って考える、ではないということ。 数学ができる人は作文が上手と言うのは数学的な思考(論理的な思考)で接続詞を適切に使って言いたいことを導くことができるからで...
数学的に考えるとはどういうことか、を考えられる良い本でした。 結論として「数学的に考える=論理的に考える」であり数式を使って考える、ではないということ。 数学ができる人は作文が上手と言うのは数学的な思考(論理的な思考)で接続詞を適切に使って言いたいことを導くことができるからであるという内容に大変納得した。 また、ある事柄をうまく説明できない理由は自分が納得しておらずその事柄の構造が把握できていないからという内容にも納得した。 私は文系で数学が苦手だと思い込んでいたが、本書を読んで改めて数学ということの大切さを知った。 この数学的な思考を学んだ上で、その思考のトレーニングとして中学数学を学び直すと面白そうと感じた。 改めて、この本は論理的に考えるために(話すために)とてもためになる本だった。
Posted by
構造化して考えるということが苦手な私には、とても分かりやすいテキストだった。構造化されてるからですね。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ビジネスパーソンや人と関わりのある人にはもれなく読んでほしい本です。 この本で紹介されている接続詞の使い方は大学で習った論理学にも近しいと思いました。(日本語を記号化する方法) また、数学的に物事を考える力を養うということは、それと同時に物事の本質を捉える力を養うことであると思いました。 私は文系女子ですが、そんな私にとってもこの本は非常にわかりやすく面白かったです。(そもそも計算は不要) この本は著者の「仕事で数字を使うとはこういうことです」を読んだ時に感じた「なるほど納得!」が至る所に散りばめられているので、一つ一つを理解した上で安心して読み進めれます。 人事として採用での質疑応答ではどのような考え方ですれば良いかも教えていただき、感謝です。
Posted by
「数学ができる人は、作文が上手い」と聞くが、その理由をまさに構造化して説明してくれた本。なぜなら、数学言語を活用して、物事を構造化し順序立てて考えることを数学的思考と説いているが、文章の組み立て方にも当てはまることだからである。さらに、物事を構造化する作業は、抽象化ゲームに似てい...
「数学ができる人は、作文が上手い」と聞くが、その理由をまさに構造化して説明してくれた本。なぜなら、数学言語を活用して、物事を構造化し順序立てて考えることを数学的思考と説いているが、文章の組み立て方にも当てはまることだからである。さらに、物事を構造化する作業は、抽象化ゲームに似ているなと感じた。「メモの魔力」にも、この作業の重要性について記してある。ゆえに、日々、物事を構造化する作業を繰り返せば、思考力も上がると思った。従って、数学を正しく学べば、思考力も上がり、説明も上手くなる。
Posted by
少し残るモヤっと感。数学コトバを使って物事を構造化し、わかりやす説明する。一言で言うとこんなことが言いたい本だと解釈したんだけど、とても表面的な印象で、軽い本だったかな。接続詞の使い方、に近い本かも。
Posted by
学校で習ってきた数学のイメージを一転する内容で、おもしろかったです。 以下、印象に残った事項です。 ①ものごとの構造を把握する ②矛盾なく論証する ③わかりやすく、簡潔な説明ができる ★構造把握→論証→説明 ① ストレスで太るは嘘→ストレスはノーカロリー ※食べたい欲求をコン...
学校で習ってきた数学のイメージを一転する内容で、おもしろかったです。 以下、印象に残った事項です。 ①ものごとの構造を把握する ②矛盾なく論証する ③わかりやすく、簡潔な説明ができる ★構造把握→論証→説明 ① ストレスで太るは嘘→ストレスはノーカロリー ※食べたい欲求をコントロールできないから食べてしまう ★ビジネスは四則演算 ・立ち上げる…足し算 ・軌道に乗せる…掛け算 ・不要なものは排除する…引き算 ・第三者に仕事を振り分ける…割り算 この繰り返し。 ② ・行動ができる人が少ない。 →納得をつくるスキルが足りない。 ・小さな一歩+それを続ける構造→大きな成果 これは、数学的帰納法の考え方である。 ・まず、定義する。 自分の仕事は何かを定義すると、やるべきこと、やらなくても良いことが見えてくる。 ③ ・カーナビは数学的な伝え方をしている。 ・以上ですは大切な数学ことば。
Posted by
- 1
- 2