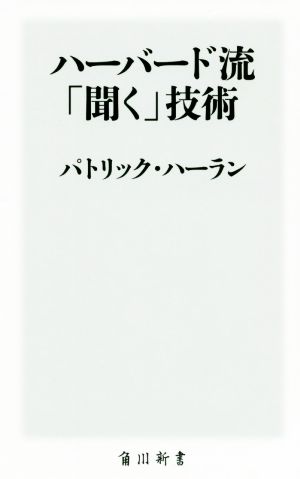ハーバード流「聞く」技術 の商品レビュー
参考にはなったけど、 時折り挟み込まれるハーバードジョークが 少し邪魔。本人はネタのつもりだろうけど。 そういった意味では、 相方さんのアドバイスはとても適切だった、 のだと思います。
Posted by
パックン初読。 うんうん、そうだよね、とスラスラ読めました。 「アメリカでは○○」というお国柄エピソードが面白かったので、パックンの他の本も読んでみようかなと思いました。 こういう本、もちろん自分のためにもなるんだけど、どっちかと言うと夫に読んでもらいたい、そして実践してもら...
パックン初読。 うんうん、そうだよね、とスラスラ読めました。 「アメリカでは○○」というお国柄エピソードが面白かったので、パックンの他の本も読んでみようかなと思いました。 こういう本、もちろん自分のためにもなるんだけど、どっちかと言うと夫に読んでもらいたい、そして実践してもらいたいのです。 が、どれだけ勧めても夫は本読まない人なので、もう諦めてますが・・
Posted by
パックンは毎週金曜日の朝、モーサテで拝見していて、その時は、パックンは十分日本語が流暢と思いつつも、コメントが時間内におさまるかよくハラハラしてしまうのだけど、この本のパックンの文章は、構成も言葉選びも本当によく練られていて、日本人より上手に書けているのではと感心してしまう。笑い...
パックンは毎週金曜日の朝、モーサテで拝見していて、その時は、パックンは十分日本語が流暢と思いつつも、コメントが時間内におさまるかよくハラハラしてしまうのだけど、この本のパックンの文章は、構成も言葉選びも本当によく練られていて、日本人より上手に書けているのではと感心してしまう。笑いも、正直申し上げて、トークよりも文章においてのほうが、置かれる位置も内容も的確でちゃんと笑えるし(ちょっと失礼かな…)、今度は「書く技術」も出版したらいいのにと思った。 もちろん、本題の「聞く技術」について参考になることは多かったし、以前読んだ「ツカむ話術」ももう一度読み返したくなった。 ただ、ところどころ引用されている他書(「ハーバード式交渉術」、「予想通りに不合理」等)については、私も含め既に読んでいる読者は多いと思われ、その既読者からすると、ちょっと引用が甘すぎると感じられる部分も。読者がこれらの本を読んでない前提だったとしたら、ターゲットを間違えてるんじゃないかなあ…。パックンの本をタレント本のつもりで手に取る人は少ないように思います。この点、ちょっと残念でした。
Posted by
質問できる環境を作るのは、本来、親、先生、上司の仕事。 アメリカには70/30ルールがある。相手に7割話てもらい、自分は3割。 コミュニケーションの基本は聞くこと。 バカな質問はない。唯一バカな質問は、きかなかった質問だけ。という掲示がアメリカの学校にはある。 聴き方は、リフ...
質問できる環境を作るのは、本来、親、先生、上司の仕事。 アメリカには70/30ルールがある。相手に7割話てもらい、自分は3割。 コミュニケーションの基本は聞くこと。 バカな質問はない。唯一バカな質問は、きかなかった質問だけ。という掲示がアメリカの学校にはある。 聴き方は、リフレクション。相手のワードを繰り返す。サマリー。要約。そして、エンパシー。共感。 様々なものと比較することで、情報を精査することができ、データが指し示す意味を深掘りできる。 批判的思考のコツとして、極端に膨らませて考える。という手法がある。 エトス。人格と著者は訳している。 この人は信用に足る人だと相手に思わせる要素全般。 パトス。感情を使って相手を動かす力。 ロゴス。言葉による説得。 聞くことが第一歩であることがよく分かった。
Posted by
20220320読了(2時間半くらい) ・ 今、興味ありありのことだったのでとても面白かった❗️ 読書って、自分で考える時間の確保にもなるから意義があるんじゃ無いかなあ。と、読書の効能も感じた。
Posted by
生まれながらの日本人よりも日本語の文章を上手に書きこなす。 これだけでもパックンの凄さを感じてしまう。 そもそも外国人が最も苦手と言われている同音異義語が本書の主題なのだから恐れ入った。 そこそこ国語に自信のある人であっても「聞く・聴く・訊く・効く」の違いを正確に説明できるだろう...
生まれながらの日本人よりも日本語の文章を上手に書きこなす。 これだけでもパックンの凄さを感じてしまう。 そもそも外国人が最も苦手と言われている同音異義語が本書の主題なのだから恐れ入った。 そこそこ国語に自信のある人であっても「聞く・聴く・訊く・効く」の違いを正確に説明できるだろうか。 これを明快に日本人に対して論じるのだから、大したものである。(私が言うのも憚られる) アメリカの教育では幼少期から、常に議論することを叩き込まれるそうだ。 多民族国家のアメリカでは、自分の考えを主張することはもの凄く重要。 そこは、英語だろうが日本語だろうが言語の違いは関係ないところなのだろう。 アメリカでは意見が異なるのが前提。その上で、どうやって議論を重ね、よりよい解決策を見出すのか。 そういう手法を会得することが、生きていく上で必要な術なのだから、日本とはだいぶ状況が異なる訳だ。 日本人は勿論議論が下手であるが、本書を読むと「訊くことが出きてないから」ということに改めて気付かされる。 議論をする前提は、相手の話をよく聴くこと。 注意深く聴き、さらにそこでの疑問点を訊きだす。 それが出来て初めて相手の主張を理解することになる。 自分が主張したいことがあるならば、まずは相手の主張を理解する必要があり、それは「訊く」以外に他ならない。 日本語としてこれら「キク」についても、「聞く・聴く・訊く・効く」とあるくらいだから、昔からこれらの違いは認識されていたはずなのだ。 それなのに、現代日本人はサラッと「聞く」だけに留まっている。 言葉として「訊く」という文字が当てがわれている以上、その意味は昔から存在しているはずなのに、日本国内ではそれは活かされていない。 実に勿体ない話ではないだろうか。 歴史を紐解くと、日本人は勤勉で、海外の新しい技術や学問を積極的に取り入れてきたという。 その時には必ず相手に対して「訊いて」いたはずなのである。 積極的に質問し、その意図を掘り下げて、自分の中に取り込んでいたはずなのである。 その中で自分自身の中から湧き出た疑問は相手にぶつけてみる。 質問があれば聞いて、議論を重ねていく。 そういうことを繰り返して、国として発展してきたのではないだろうか。 現代日本人は、まさに訊けていないというのは正しい指摘だ。 忙し過ぎるという側面も確かにある。 自分個人のことで手一杯で、他人の話まで訊けないということもある程度は理解できる。 しかし、果たしてそれで良いのだろうか。 むしろ積極的に訊くために、心に余裕を持つ必要すらあるのではなかろうか。 私個人も積極的に話を訊けるように。 まずはそれを意識して、訓練するしかないのである。 (2022/2/21)
Posted by
書かれていることの一つひとつは、きっと聞いたことがあるものばかり。「分かっちゃいるけどそれができないんだよなあ…」となる。 でも、それが集まればとにかく深い。話すより聞く方が断然難しい!と思い知らされる1冊。 …それは置いておいて、パックンの書きっぷりがすごい!駄洒落や自虐...
書かれていることの一つひとつは、きっと聞いたことがあるものばかり。「分かっちゃいるけどそれができないんだよなあ…」となる。 でも、それが集まればとにかく深い。話すより聞く方が断然難しい!と思い知らされる1冊。 …それは置いておいて、パックンの書きっぷりがすごい!駄洒落や自虐を連続で繰り出しつつ、理路整然と、分かりやすい言葉で説明をしてくれる。 途中で挫折かなと思っていたけれど、ギャグの量が豊富だったこともあってか、読み始めたらさくさく進んでいった。 この方頭の回転早いんやなあー…としみじみさせられるので、パックンの凄さやギャグの滑りっぷりを楽しみたい人におすすめ。
Posted by
パックン 。ハーバード流というよりは、ハーバード卒のパックン流。パックンの体験談からの聞くということがおおく書いてある。 「聞、聴、訊」けば、人生に「効」く C0295
Posted by
ハーバード大学の比較宗教学部を首席で卒業して、神様を信じなくなったというのが、少し笑えましたが、軽い文体でコミュニケーションの聞くことに焦点を当てた本です。騙されない為に聞くは参考になったな、と。
Posted by
まぁ、当たり前と言えば当たり前のことが書いてあるのだが、とてもよくまとまっている。自然にあの口調を思い起こさせて読ませる。確かに、世の中ひとの話を聞かないがゆえにまさしく「生産性を落としている」ことがよくある。広く読まれるとよい本。
Posted by
- 1
- 2