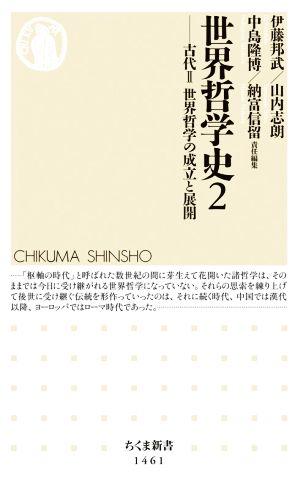世界哲学史(2) の商品レビュー
2020/6/14読了予定。 キリスト教、仏教からゾロアスター教、マニ教まで。宗教的思索の起源に迫る。 2000年あまり前の時代を振り返る事で、人類の哲学の歴史に新たな視野が開たのではないかと感じる。(あとがきより) 哲学史で見るグローバル化である。
Posted by
「古代Ⅱ 世界哲学の成立と展開」の副題をもつ第2巻はローマ哲学、キリスト教の成立、大乗仏教の成立、古典中国の成立、仏教と儒教の論争、ゾロアスター教とマニ教、プラトン主義の伝統、東方教父の伝統、ラテン教父とアウグスティヌスの各章が並ぶのをみてわかるように「宗教と哲学」、そしてその世...
「古代Ⅱ 世界哲学の成立と展開」の副題をもつ第2巻はローマ哲学、キリスト教の成立、大乗仏教の成立、古典中国の成立、仏教と儒教の論争、ゾロアスター教とマニ教、プラトン主義の伝統、東方教父の伝統、ラテン教父とアウグスティヌスの各章が並ぶのをみてわかるように「宗教と哲学」、そしてその世界的な広がりを捉えようとする。 後半はほぼ知らないことばかり。ゾロアスター教って何? マニ教?聞いたことはあるけど重要なの? といった感じ。ニーチェの「ツァラストラはかく語りき」は読んだことあっても、そのペルシャ語読みがザラスシュトラというのははじめて知った。 そんなド素人が読んだ第2巻全体の印象は、善悪二元論と超越とは何か?という観点から宗教を哲学として捉え、その洞察のありようを世界哲学史に位置付けようとしているんだなということ。三位一体論や最終章で語られたアウグスティヌスの哲学についてはとくに面白かった。 第4章の「大乗仏教の成立」はそうした観点から言えば、やや異質な印象だが、テクストとしての大乗経典と歴史研究という視点は非常に面白く読んだ。
Posted by
西欧中心の「哲学史」を世界的な「哲学史」に再構成しようというチャレンジの2巻目。 1巻目では、ギリシア、インド、中国などの文明において、ほぼ時を同じくして立ち上がってきた「哲学」が並列的に(といってもやっぱギリシャ〜ヘレニズムの記述が多いが)紹介された。 この同時性に驚くとこ...
西欧中心の「哲学史」を世界的な「哲学史」に再構成しようというチャレンジの2巻目。 1巻目では、ギリシア、インド、中国などの文明において、ほぼ時を同じくして立ち上がってきた「哲学」が並列的に(といってもやっぱギリシャ〜ヘレニズムの記述が多いが)紹介された。 この同時性に驚くところはありつつ、最後の方ではギリシャ思想とインド思想のコミュニケーションの話はでてくるものの、各地域における哲学は基本独立した動きであった。 まあ、こんなものかなと思って、第2巻にはいると、途端に「世界哲学」な議論が増えて、とてもスリリング。 それは、文明間の交流が盛んになったということなのだが、 ・ギリシア哲学がローマでどう受容されていったか ・キリスト教がギリシャ哲学とどう対峙しつつ、その知恵を受け入れていったか ・キリスト教がマニ教などにどう影響したか ・仏教と中国思想との対立と受容 ・さまざまな思想があるなかで、なぜ儒教が中国思想の支配的イデオロギーになったか などなど なるほどな議論が盛りだくさん。 こうした文明間の対話という視点に加えて、面白かったのは、現代哲学という視点からの哲学的な対話の部分。1章の「哲学の世界化と制度・伝統」は、2巻全体の議論へのイントロなのだが、そこには、フーコーやデリダの議論が下敷きになっていて、古代・古典とポストモダーン思想との対話が展開される。 そういう流れを踏まえつつ、具体論で面白かったのは、第4章の「大乗仏教の成立」。われわれは、なんとなく、大乗仏教の教団が上座仏教とは別に存在していたのだろうと想定してしまうのだが、そうしたものは存在しない。大乗仏教とは、まずは経典を書くという活動であったということ。 う〜ん、デリダっぽい。面白いね〜。 各章は、それぞれのテーマに詳しい人が分担して執筆していて、本当にたくさんの人がこの「世界哲学史」に参加しているわけなのだが、各著者が、全体としてのプロジェクトの主旨と全体の議論の構成をよく理解したうえで書いていることが伝わってくる。 日本の悪いところばかりが目につく今日この頃だが、こうして、この「世界哲学」プロジェクトを進めることができるということは、世界のいろいろな哲学を研究してきた日本らしいことで、ちょっとすごいじゃないかと元気がでてきた。
Posted by
- 1
- 2