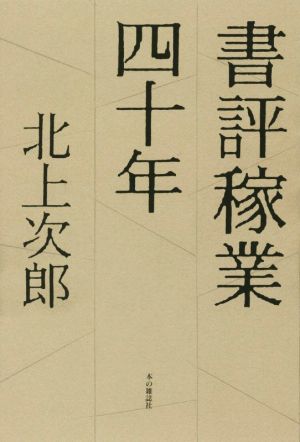書評稼業四十年 の商品レビュー
『本の雑誌』発行人を引退して悠々自適の読書人生を歩む著者の昔語り。若かりし時代の三橋暁、新保博久、大森望らとの思い出、中間小説全盛時代の記録的記述、名物編集者の思い出など業界の昔話の数々を思い出すを幸い…とばかりにめった切りに開陳する。 日本も豊かな国になって、誰もが自分が好き...
『本の雑誌』発行人を引退して悠々自適の読書人生を歩む著者の昔語り。若かりし時代の三橋暁、新保博久、大森望らとの思い出、中間小説全盛時代の記録的記述、名物編集者の思い出など業界の昔話の数々を思い出すを幸い…とばかりにめった切りに開陳する。 日本も豊かな国になって、誰もが自分が好きなことだけをやって(何とか)食べていける時代になったが、北上次郎はその嚆矢ではなかったか。
Posted by
巻末 「たまに何も予定のない休日、書棚の前に座って何を読もうかと選ぶだけで終わってしまうことがあるが、あれ以上の至福はあり得ない」
Posted by
40年間のエピソードが詰まった一冊。 面白く読み進められたのはさすがは北上次郎。 書きたいことを面白く書く。 簡単そうでそうではない。 大森望との絡みはまた、素晴らしい。
Posted by
北上次郎さんのプライベートなことを書いてるのでどうしたって面白い。へーとかニヤニヤ。最初は書評稼業について。交友関係。横柄タメ口の大森望が楽しい。他の人にはキチンと尊敬語を使っているのでびっくりしたとか。 書評家は大きく分けると3つに分けられるそうで 評論家タイプ(杉江松恋)...
北上次郎さんのプライベートなことを書いてるのでどうしたって面白い。へーとかニヤニヤ。最初は書評稼業について。交友関係。横柄タメ口の大森望が楽しい。他の人にはキチンと尊敬語を使っているのでびっくりしたとか。 書評家は大きく分けると3つに分けられるそうで 評論家タイプ(杉江松恋) 書斎派型の研究家(新保博久、日下三蔵) 煽り書評(北上次郎、霜月蒼、村上貴史) なるほどワタシたちは煽り書評で煽られていただけなのか。「人間が書いたものではない」と書いた人がいるというのもおかしい。煽りは、言葉に慣れてくると煽られなくなるので、難しいとのこと。それと実がないと信用されなくなる。その点で北上次郎は素直に書いたら煽ることになった。これが彼の書評稼業が40年続いた秘訣ですね。 中間小説誌を昔は学生が競い合って読んでいたという話も面白い。 文学VS大衆小説という区分がある中で、文学作家に大衆的な小説を書かせた中間小説が誕生、人気を博す。今のエンタメ小説の登場ですね。 「高校に入学するまで、私は一冊の本も読んだことがない。中学を卒業する春休みに、少年野球の仲間たちと最後の練習をした帰り道、歩きながら小説の話をしているチームメイトがいて、その話がとても面白そうに聞こえてきたので、どうやったらそれを読むことが出来るのか尋ねると、お前の家の近くにも貸本屋があるはずだからそこで借りればいいと教えられた」その時は松本清張なんですね。そして黒岩重吾、笹沢左保、源氏鶏太と読み進めていく。それが昭和37年。五木寛之が「さらばモスクワ愚連隊」でデビューするのが昭和41年とか。これに野坂昭如が加わり中間小説誌ブームがやってくる。オール読物が最高部数を記録したのが昭和44年の41万冊とか。他に小説現代、小説新潮が売れた。1960年代後半は中間小説誌御三家で百万部を超えていたと思われる。この後に台頭してきたのはミステリで、中間小説とは言われなくなり、エンターテイメントの時代が始まる。日本の現代エンターテインメントは、1960年代後半から1970年にかけて、大きく変化した。北方謙三、志水辰夫、大沢在昌、逢坂剛などがリードしていく。そして冒険小説などがもてはやされる。このあたりの流れはあまり認識してなかったが、それに乗って「本の雑誌」などが誕生して、ワタシたちも乗っかっていくんですね。 書評や解説の裏側文学賞の下読みをしたり、座談会をまとめたり 本を読むだけでは生活できない。そのくらいはわかっていた。だから、働く必要がある。ここまではわかるのだが、そこから先がわからない。働くことのイメージが何もないのだ。つきたい職業が一つもなかった。それが二十歳のときの正直な実感である。(あとがきより)
Posted by
漫画家を志望するも画力が及ばず原作者に、外科医を目指すも手術が苦手で研究医になったというのは時々耳にする。ただ書評家が小説家になったというのは未だ聞いたことがない。 日夜、数多の本を読み、該博な文芸知識を背景に「読みどころ」を論評する書評家は、「いつかは自分も小説を!」と思って...
漫画家を志望するも画力が及ばず原作者に、外科医を目指すも手術が苦手で研究医になったというのは時々耳にする。ただ書評家が小説家になったというのは未だ聞いたことがない。 日夜、数多の本を読み、該博な文芸知識を背景に「読みどころ」を論評する書評家は、「いつかは自分も小説を!」と思ってるのだろうか?あるいは一編の小説を書くことの難しさを知悉している書評家は、あくまでも芝居で言うところの「見巧者」として、読者に作品の秀逸性を説くことに「矜持」を抱いているのだろうか? そんな思いを抱きつつ、本書を開いた。著者名の北上次郎は書評する際のペンネーム。本名は目黒考二。 書評家 北上次郎誕生以前の目黒考二が書評家になった理由を述べている。「『本を読んで暮らしたい』。それが私にとっては、一番重要なことで、それ以外はどうでもよかった。とはいえ、それでは生活できないことはよくわかっている。だから働く必要がある。ただ、そこから先がわからない。働くことのイメージが何もない。就きたい職業がひとつもない。それが二十歳の正直な実感。自分には将来に対するビジョンがひとつもない」。 著者の抱くこの思いは、一切揺らぐことなく、明大卒業後就職するも、いずれの会社も3日と続かず即退社。退社理由は「本が読めないから」。その理由で退社すること8回。ようやく9社目の出版社に落ち着く。そこで6年間働き、1976年椎名誠らと書評誌「本の雑誌社」を刊行するに至る。 ただ、その本の雑誌に対しても、別に情報誌を作りたかったわけではない。学生時代、本好きの仲間と語り合っていたように、感想を放出したくて、コピー用紙に書評を書いていた。それが、やがて「本の雑誌」になったに過ぎない。 著書は本の雑誌の編集発行人となる傍ら、編集長 椎名誠が売れっ子作家となったことにより、実質上、編集長も兼務し2001年まで長らく務めた。 そんな本好きの著書であるが、読書の愉しみを知ったのは遅い。高校入学前の春休み。近所の貸本屋でたまたま読んだ松本清張「点と線」に大衆小説の面白さに魅了され、以後、黒岩重吾・笹沢左保・源氏鶏太らの作品を片っ端から読破していく。 その自己の読書体験を下敷きに、1960年代後半に、大衆小説(中間小説)が勇躍する転換点があると考察した「書評家になるまで」「中間小説誌の時代」の稿が面白い。ちなみに大衆小説を牽引したのが、五木寛之・野坂昭如・松本清張であると指摘。 書評家としての40年の来し方について、生来記憶力に乏しく、また日記や日誌をつける習慣がない中での古い記憶を掘り起こす難儀さに、悪戦苦闘・七転八倒している様子が伝わってきた一冊であった。
Posted by
- 1