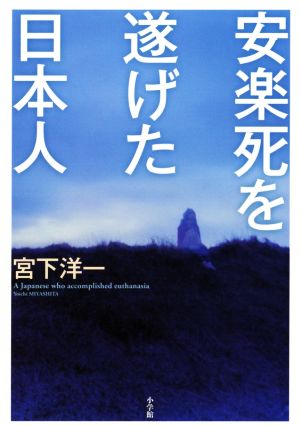安楽死を遂げた日本人 の商品レビュー
「安楽死を遂げるまで」を読み、寝たきりになる前に自分の人生を閉じることを願いますという内容のメールを著者の宮下洋一さんに送ったのは、小島ミナさん…彼女は多系統萎縮症という神経難病を罹患しており、正常な判断能力を有したまま寝たきりになるという残酷な経過を辿るという…。彼女は努力家...
「安楽死を遂げるまで」を読み、寝たきりになる前に自分の人生を閉じることを願いますという内容のメールを著者の宮下洋一さんに送ったのは、小島ミナさん…彼女は多系統萎縮症という神経難病を罹患しており、正常な判断能力を有したまま寝たきりになるという残酷な経過を辿るという…。彼女は努力家で明るく誰からも慕われており、その介護も彼女の姉が当然のことと引き受けてくれたのだったが…。彼女は、日本では合法化されてないがために、スイスに渡り安楽死することを希望したのだった…。 私はこのNHKスペシャルを観ていました。ただ、ただ衝撃を受けて、悲しい気持ちになったのを覚えています。でもこの作品を読んで、悲しいだけじゃなかったことがわかりました。だって、そこに至るまでの苦しみはとても辛いものだったから…。 著者の宮下さんは、小島さんの最期にも立ち会いその様子を本作に収めています。小島さんが生きていた、愛されていた証…彼女を愛した人たちへも届いていることでしょう。こうした実際を知ると、日本でも安楽死が合法化されたらよいのかな…という思いも抱きますが、安楽死を希望していたけれどその意思を変え、日本で家族に看取ってもらった方もいました。ここ最近は、自分の望む生き方と望む最期を当事者と家族、それを支える専門職で共有するという人生会議(ACP)や、エンディングノートとか事前指示書の必要性も取り沙汰されています。まずは、そこからかな…って感じました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
スイスでの安楽死を希望し、実際に安楽死を遂げた方、安楽死を希望しながらも最終的には天寿を全うした方について、筆者が取材した内容が主に書かれていた。 スイスでの安楽死の現実についてこの本を通じて知ることができた。脊髄小脳変性症の小島ミナさんの闘病中のお話は本当に辛く、泣きながら読んだ。最期の家族との別れは、私にはとても理想的に感じられた。ただ、彼女は、スイスまで行ける体力があるうちに安楽死しないといけないと考えており、もし日本で安楽死が出来たならもっと後でも良かったとも言っていた。 病気は多くの人にとって避けられないものであるし、本を読んだ上でもやはり安楽死という選択肢が必要だと感じた。「苦しくても命があればいいのでしょうか」という彼女の言葉がとても刺さった。 私自身は学生時代に母親を癌で亡くしたが、治療中はずっと死にたいと言っていたし、死にたいと言う母を励ます時間が何よりも辛かった。余命を言われた時の母はむしろ嬉しそうだった。最期は緩和ケアという選択をしたが、最後までしんどそうだったし、安楽死という選択肢があれば母親自身も家族もこんなに体と心に傷を負わなかったのにとどうしても思ってしまう。 命があれば、生きてさえすればなんでもいいのか、色々な人が改めて考えることができる本だと思う。海外での安楽死について色々な人に知ってもらい、日本においてももっと議論してほしいと思った。
Posted by
前作の日本人の実例。 本人の意志、周りの理解つまりそれだけの信頼と理由がないとわざわざ外国まで行って行うのは難しい。
Posted by
安楽死にはかねてから興味があった。本書は宮下洋一氏の「安楽死を遂げるまで」の続編である。前作は未読ながら、本作をのめり込むように読んだ。 身体の機能が衰えていく難病を患う50歳の日本人女性、小島さんは安楽死を希望している。著者は前作を読んだこの女性から連絡をもらい、彼女が日本人と...
安楽死にはかねてから興味があった。本書は宮下洋一氏の「安楽死を遂げるまで」の続編である。前作は未読ながら、本作をのめり込むように読んだ。 身体の機能が衰えていく難病を患う50歳の日本人女性、小島さんは安楽死を希望している。著者は前作を読んだこの女性から連絡をもらい、彼女が日本人としてライフサークル(スイスの安楽死団体)での安楽死を目指していることを知り、取材をする。 興味深かったのは、安楽死を希望する理由が欧米と日本では違うということだ。日本では、介護で周りに迷惑を掛けたくないから早く人生を閉じたいと考える人が多く、欧米では、自分の人生および死ぬタイミングは自分で決めたいから安楽死を選ぶ、という人が主流なのだという。よく理解できるし、自分が排泄まで人の介助を借りる立場になったら、同じように感じる確信がある。シモの世話をして欲しい人なんていない。 私は義母が同様の難病を患い、晩年はやはり病に苦しみ、スイス行きを希望していた。緩和ケアに自信をもつイギリスでは安楽死は違法である。結局経済的な理由や体力のなさから断念せざるを得なかったが、彼女の姿を重ねながら読むことになった。 本書では著者は安楽死の是非についてはあえて述べていない。そういう選択肢があったら、患者の心が安らぐだろうとは言っている。難しいのは、いくら条件に当てはまっても、安楽死をすべきでないケースが多々あるということ。そして、安楽死をするにあたり一番必要なのは、家族の理解だ。 本人の希望と、残される家族の心の傷のどちらを重視すべきなのか、それは患者の家族とのつながりによる。本書に出てくる小島さんは、とても明るく理性的な女性で、テレビのディレクターも取材をしているうちに好きになってしまうほど魅力的な人だ。 安楽死に行きつかなかったがん患者の例もいくつかあり、また安楽死の代替としてのセデーション(鎮静)を知り、本当にいろいろ考えさせられた。 途中から涙が止まらなくなり、泣きっぱなしのまま最後まで読んだ。切なかった。
Posted by
前作である、【安楽死を遂げるまで】は読まずに手に取った本です。 18歳からアメリカに行き、人生の半分以上を欧米文化で生きてきた筆者の主観を通して、安楽死に向き合う一冊です。 安楽死に賛成か、反対か、その意見を決める土壌が日本人には無いのではないか?と言う筆者の思いが、若年層とズレ...
前作である、【安楽死を遂げるまで】は読まずに手に取った本です。 18歳からアメリカに行き、人生の半分以上を欧米文化で生きてきた筆者の主観を通して、安楽死に向き合う一冊です。 安楽死に賛成か、反対か、その意見を決める土壌が日本人には無いのではないか?と言う筆者の思いが、若年層とズレてると感じながら読んだのですが、安楽死を理解した上(安楽死と尊厳死の違いを知っている、実際に安楽死を行う人・安楽死を望む人を取材している)で反対の立場を取る筆者が、できるだけ公平に真実を書こうとしていることが伝わってきました。 作中にも出てきますが、テレビなど動画や音声で伝えられると、受け取り手がテーマによるインパクトの強さに思考が影響を受けがちになります。 その点、文章で読めたことが評価のポイントかと思います。
Posted by
ここ数年で読んだ本の中で一番気分が重たくなる。ただ、読んでよかった。 【感想】 audiobook.jpで読了。「安楽死を遂げた日本人」小島ミナさんが安楽死に至るまでの過程が、著者の取材によって描かれる。その内容がとにかく重たい。救いがない。読んでいて、「これなら、安楽死を望...
ここ数年で読んだ本の中で一番気分が重たくなる。ただ、読んでよかった。 【感想】 audiobook.jpで読了。「安楽死を遂げた日本人」小島ミナさんが安楽死に至るまでの過程が、著者の取材によって描かれる。その内容がとにかく重たい。救いがない。読んでいて、「これなら、安楽死を望んでも仕方ない。自分も同じ環境にいたら、そう思うかもしれない」と感じた。小島さんを安楽死に向かわせるのは多系統萎縮症という難病である。この難病が恐ろしい。正常な思考力は保ったまま、身体の動作、筋肉が全て弱っていき、最終的にねたきりになってしまう。難病であるから、発症のメカニズムや治療方法も分からない。発症したら、最後、である。もう、「何でこの世には難病なんてものが存在するんだ」と思ってしまう。 小島さんが難病を発症してから、姉夫婦に介護され、その過程で自殺未遂を繰り返すエピソードがしんどい。自殺行為を止めて泣きじゃくる小島さんと姉...。それも年代を50歳も超えてである。姉夫婦も小島さんも悪くないのに、なぜあんなに苦しい思いをしなければならないのか...。難病の恐ろしさたるや。いつどこの誰に起きてもおかしくないのである。ここが一番読んでいて恐ろしく、かつ読んでよかったと思う点である。読んでいて、「確かに安楽死したほうが周囲にとっても本人にとっても幸せだ」と思えなくものない、迫力がある。実際に、小島氏と信頼関係を築いて、家族と共に、自殺ほう助の現場に立ち会い、そのプロセスを詳細に記述している。なかなか知り得ることができるものではない。読みながら涙した本は久しぶりだった。 また、本を読んで勉強になったのは「自殺ほう助」を巡る様々な論点が存在する、ということ。日本のマスコミにおける自殺ほう助を巡る議論のレベルは高くなく、一律に自殺ほう助を認めるのは、この社会においてはリスクが高い、という著者の主張にもある程度納得がいった。最終的に、自殺ほう助を認めることに賛成 or 反対するにしろ、双方のメリット、デメリットは知っておくべきであろう。
Posted by
著者の前作もNHKの特集も知らない状態での読了です。 内容について興味があったので読みました。 安楽死というものを漠然と逃げ道の様に捉えており、きちんと理解しようとしたことはなかった自分に気づかされました。 自分の健康状態は、今はまだ終わり方を具体的にイメージできる段階ではない...
著者の前作もNHKの特集も知らない状態での読了です。 内容について興味があったので読みました。 安楽死というものを漠然と逃げ道の様に捉えており、きちんと理解しようとしたことはなかった自分に気づかされました。 自分の健康状態は、今はまだ終わり方を具体的にイメージできる段階ではないです。しかし、いつか必ず向かい合わないといけないときが来ます。(向かい合う時間もなく終るということもありますが。) そんなときに知識不足で視野が狭くなるということは避けたいです。安楽死だけでなく、セデーションや緩和ケアといった方法への理解も深めておきたいと思いました。 内容は面白かったのですが、著者の文章は自分には単調で少し押し付けがましく感じました。記者らしい文章というか、客観的でないといけないのは解りますが人を寄せ付けないような一歩離れた文章でした。 内容に興味がある方は読んでみてもいいかもしれません。NHKの特集の方は機会があれば見たいと思います。
Posted by
読み進めながら、この本に出てくる小島ミナさんのこと、知っているような気がしていた。NHKの番組を観たことがあるんだと思う。 たまたまついていたのを、引きこまれて観た記憶がある。 安楽死、尊厳死、セデーション、私はどれもちゃんとわかっていなかった。そして筆者が書くように、本の中で色...
読み進めながら、この本に出てくる小島ミナさんのこと、知っているような気がしていた。NHKの番組を観たことがあるんだと思う。 たまたまついていたのを、引きこまれて観た記憶がある。 安楽死、尊厳死、セデーション、私はどれもちゃんとわかっていなかった。そして筆者が書くように、本の中で色々な人が言うように、日本では「死」について議論があまりなされていない。 自分が同じような状況になったときに同じ選択をするかはわからない。 けど、選択肢があることでそれが光になる人もいるし、簡単には決められない問題なのだろうなぁ。 とここまで感想を書いたものの、モヤモヤまとまらないので追記。 幡野さんの言うように、患者の気持ち優先という気持ちもわからなくはない。でも筆者の言うように、残された家族側の気持ちも完全に無視していいものだとは思わない。 自分が患者の立場だったら……自分が家族の立場だったら……といろいろ考えたけど、結局こう言うことを自分だけで考えて終えてしまうからダメなのかな。会話にしにくいけど、私はこうしてほしいと伝えておくのも大事だし、家族がどうされたいのか聞いておくのも大事だなぁ。あと、自分の希望を伝えた後、それについてどう思うか聞くのも大事なのかもしれない。こういうことを含めて、日本は話し合う機会が少ないんだと思う(海外事情は知らないけども)
Posted by
安楽死と尊厳死の違いなどはっきりしてなかったことが良くわかると共に考えさせられることも多かった.実際自分だったらどうするだろうと思いながら読み進んだ.日本も法律が変わらない限り選択肢が限られるが,生きる権利が大切なら死ぬ権利も大切なので,この本がもっと読まれて欲しいと思った.
Posted by
衝撃。こんなにも死ぬことに、精力を尽くしてしっかりと準備していく心情。 生きるのは苦しい。けれど、衝動的にではなく自分で終わらせることを決めるという心情。 良いとか悪いとか、まだ考えられないな。 ただ、生きていきたいと思ってもらえるような繋がりを作れるようにしたいとは、思う。決し...
衝撃。こんなにも死ぬことに、精力を尽くしてしっかりと準備していく心情。 生きるのは苦しい。けれど、衝動的にではなく自分で終わらせることを決めるという心情。 良いとか悪いとか、まだ考えられないな。 ただ、生きていきたいと思ってもらえるような繋がりを作れるようにしたいとは、思う。決して、簡単なことではない。
Posted by