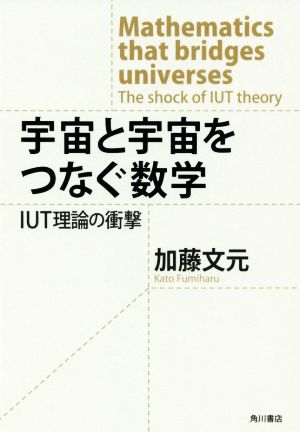宇宙と宇宙をつなぐ数学 の商品レビュー
912 宇宙と宇宙をつなぐ数学 IUT理論の衝撃 (角川学芸出版単行本) by 加藤 文元 望月教授が博士論文を書いて大学院を卒業したのは1992年のことで、このとき彼はまだ 23 歳でした。博士号を取得してすぐに、京都大学数理解析研究所に助手として採用されました。その後、...
912 宇宙と宇宙をつなぐ数学 IUT理論の衝撃 (角川学芸出版単行本) by 加藤 文元 望月教授が博士論文を書いて大学院を卒業したのは1992年のことで、このとき彼はまだ 23 歳でした。博士号を取得してすぐに、京都大学数理解析研究所に助手として採用されました。その後、1996年に 27 歳の若さで助教授に昇任し、2002年に 32 歳という驚異的な若さで教授になられて、現在にいたってい 数学の世界で、大学教授になる平均の年齢がどのくらいなのかも、おそらくそういう統計はないものと思いますので、よくわかりません。しかし、 40 代前半ですでに教授だったら、そこそこ早い方でしょう。 32 歳で大学教授というのは驚異的な早さ ここで望月さんが意外にも時事問題に詳しく、それらに対して常に鋭い考察をしていると感じることが多かったと記憶しています。政治的な問題について話し始めると、ついつい盛り上がって長話になってしまうこともしばしばでし
Posted by
いやあ面白かった。確か中学校の時に群論を元にしたルービックキューブの解法の本を買って、それ以来40数年群論に対して理解したいなーと思ってたんだけど、今回、初めてとてもわかりやすく概念を理解させていただきました。そして、タイヒミューラーと言う言葉をこれからは知ったかぶりで使っていき...
いやあ面白かった。確か中学校の時に群論を元にしたルービックキューブの解法の本を買って、それ以来40数年群論に対して理解したいなーと思ってたんだけど、今回、初めてとてもわかりやすく概念を理解させていただきました。そして、タイヒミューラーと言う言葉をこれからは知ったかぶりで使っていきたいという所存です。
Posted by
「宇宙」とは天文学の宇宙ではなく、数学における「宇宙」のこと、つまり、足し算とかかけ算とか、自然数とか複素数とかそういった数学をするのに必要な道具一揃いのことをいいます。もしかしたら違う平行世界にはわたしたちの想像しないような計算方法で(違う宇宙で)計算しているかも知れません。京...
「宇宙」とは天文学の宇宙ではなく、数学における「宇宙」のこと、つまり、足し算とかかけ算とか、自然数とか複素数とかそういった数学をするのに必要な道具一揃いのことをいいます。もしかしたら違う平行世界にはわたしたちの想像しないような計算方法で(違う宇宙で)計算しているかも知れません。京都大学の望月新一教授はそのような異なる宇宙の間で数式をやりとりする方法を調べたところ、もちろん計算結果がずれてくるのですが、そのずれを不等式で評価する方法を見いだしました。それが宇宙際タイヒミュラー(IUT)理論です。国際が国と国との間を表すように宇宙際とは宇宙と宇宙の間、という意味です。 これを調べることによって長いこと未解決問題だったABC予想(ヨビノリさんの動画を貼りますhttps://www.youtube.com/watch?v=PIUCfN08p8M)という問題が解けてしまいました(証明については現在も議論中?一応論文掲載に至ったが、新しすぎて世界でも理解できる人が少なくて合ってるのかどうかわからない)。 この本は一般向けの科学書であり、これを読んでも理論の詳細は理解できないのですが、本書は望月教授の親友であり、もっとも近くでこの理論が出来る過程を見てきた加藤氏が望月教授の人となりを紹介しているという側面もあり、数学の研究ってこういう風にやるのか~ということを純粋に楽しむことも出来ます。 数学好きの中には厳密な証明こそが大事でアナロジーやお気持ちなどは不要という人もいると思いますが、この本を読めばアナロジーで発想を豊かにすることも大事なのだ、とわたし自身は元気づけられました。
Posted by
いやごめん、多分面白いねん。 でも、肝心の理論の部分で無理やった。 構成も変で、IUT理論とは何か、ABC理論とは何か、そもそも、提唱者の望月新一先生って何者なのかってのが全く出てこない。 いきなり、数学を語る言語が違うとか、数学業界ってこういうもんだとか、数学者にしては文章は...
いやごめん、多分面白いねん。 でも、肝心の理論の部分で無理やった。 構成も変で、IUT理論とは何か、ABC理論とは何か、そもそも、提唱者の望月新一先生って何者なのかってのが全く出てこない。 いきなり、数学を語る言語が違うとか、数学業界ってこういうもんだとか、数学者にしては文章は上手いし面白いんだが、何を読まされてるんでしょうか。 IUTとかを少しでも知ってる人じゃないと、入り口でつまずく。知らない人との人的紐帯を自慢されても、で?って感じだった。 ので、他に読みたい本もあるので、遠慮しました。
Posted by
7章までは懇切丁寧に分かりやすく導入が書かれていたが、いざ8章に突入するとすごい勢いで分からなくなった。宇宙間の対称性通信という概念は面白いし、何かしら工学系にもデフォルメして応用できそうな気がした。(暗号分野では応用の検討もされている?)非常に抽象的で新しい数学的枠組みなのかと...
7章までは懇切丁寧に分かりやすく導入が書かれていたが、いざ8章に突入するとすごい勢いで分からなくなった。宇宙間の対称性通信という概念は面白いし、何かしら工学系にもデフォルメして応用できそうな気がした。(暗号分野では応用の検討もされている?)非常に抽象的で新しい数学的枠組みなのかとは思うが、新しすぎて、その考え方をどう数学的に正しいと論文中では証明しているのだろうと気になった。 動画がやばい。κコア的関数から復元された数体の情報がポロポロと対数殻に零れ落ちていく…https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/research-japanese.html
Posted by
本編の大半がIUT理論ならびにABC予想などの概要をイメージさせることに徹底していて、かなり分かりやすかった。と言ってもコレが分かってやっと入口が見えた!って程度の話だと思う。どうせ詳しく聞いても分からないくせに、こんなところで終わっていいの?って思うくらいスッキリした内容。数学...
本編の大半がIUT理論ならびにABC予想などの概要をイメージさせることに徹底していて、かなり分かりやすかった。と言ってもコレが分かってやっと入口が見えた!って程度の話だと思う。どうせ詳しく聞いても分からないくせに、こんなところで終わっていいの?って思うくらいスッキリした内容。数学の入口のその先、深淵にこそ感動や興奮はあるんだろうけど、入口から数学の世界をなんとなく眺めるられるようになるだけでもワクワクした。奥が深い。ミレニアム懸賞問題解いて人生一発逆転しようと思ってたけど諦めました。あとは任せた。
Posted by
最終的にコアな部分のイメージはよく出来なかったが、どのような道筋でどんなことを考えてIUT理論に行き着いたのかを知ることが出来た。 群や対称性は物理でも出てくる考え方で、そこのイメージが出来たことも良かった。
Posted by
『だれも歩いたことのない土地をまっすぐ歩こうとするとき、次の一歩だけを見て歩き続ければ、まっすぐに歩けるとは限りません。しばらく歩いて後に振り返ってみると、ぐにゃぐにゃに曲がりながら歩いていた、ということの方が多いでしょう。しかし、自分の歩いている進路を、GPSなどを使って全体的...
『だれも歩いたことのない土地をまっすぐ歩こうとするとき、次の一歩だけを見て歩き続ければ、まっすぐに歩けるとは限りません。しばらく歩いて後に振り返ってみると、ぐにゃぐにゃに曲がりながら歩いていた、ということの方が多いでしょう。しかし、自分の歩いている進路を、GPSなどを使って全体的に鳥瞰できれば、まっすぐ歩くのは難しいことではありません。そして、多くの場合、数学の新しい理論を構築する上でGPSの役割を果たすのが、「自然であること」についての鋭敏な直観なのだ、というわけです』―『第3章 宇宙際幾何学者』 馴染みの言葉の英語での表現を知って元の日本語の意味を再確認するというようなことを時々経験する。例えばそれが英語をカタカナにしただけのインターハイのような言葉ならなおさらだが、それが「inter(-)college」を真似た「inter」と「high school」を合わせた合成語で高校総体(高校総合体育大会)を指しているという理解の元、「inter」が英語では「中、間、相互」という意味だと知ることで、なるほど「inter high school」の「inter」は、学校「間」を表しているのか、と理解が進むように。 「際」は「きわ」という読みの方が強く印象があって、例えば「窓際」のような使われ方では何かと何かの「接するところ」というよりは「端っこ」という意味が強い。なのに「国際」となると「inter(-)national」と急に「間」という意味で使われる。なんでこんな話をするかといえば「Inter-Universal Teichmüller Theory(IUT)」の日本語訳が「宇宙間タイヒミュラー理論」ではなく「宇宙際タイヒミュラー理論」となっているからなのだけど、例えば「宇宙間通信」のように、宇宙と宇宙のあいだを繋ぐなら「際」じゃなくて「間」でもいいんじゃないか、と読み始める前はぼんやりと思っていた。 もちろん、元の論文が500頁を超える大著で、かつ、そこへ至るまでの積み重ねの論文の総量が1000頁を超えるような理論を、この一冊で理解できることなど到底出来ないだろうし、著者の加藤文元氏が述べているように、その理論の技術的概要を一般向けに解説することは本書の意図ではないのかも知れない。実際、高度な数学上の議論を抜きにした本書の解説を読んでも当然のことながら門外漢の自分にはその概要が掴めたとは言える筈もない。けれど、何故これが「宇宙間」ではなくて「宇宙際」と訳されなくてはならないのかということは、ぼんやりと解ったような気にはなる。 考えてみれば「際」には「きわ、はて(際限)」という意味がありつつ「さかい、接して交わるところ(学際、国際)」という意味もある。「はて」という否定的な意味合いで用いられる「窓際」もよくよく考えれば「窓を越えた世界」との繋がりを強いた場所とやや肯定的な意味合いも考えられなくもない。水際(みずぎわ)だって現(うつつ)の世界では越えられないけれど、浦島太郎のように夢や幻の世界では易々と越えて行ける「さかい」だ。二つの数学(宇宙)を繋げることによる不定性を測るというIUTは、なるほど越えがたい二つの世界を結ぶという離れ業をやっているのだと知れば、これは同じ物理法則の成り立つ単に遠く離れた銀河の間を繋ぐような「宇宙間(interspace)」ではなくてどうしても「宇宙際(Inter-Universal)」とならざるを得ないだろうな、と妙なところで得心する。
Posted by
宇宙本コーナーにあったので手に取ったのだが、ゴリゴリの数学だった。が、読むうちにどんどん引き込まれ、結果として宇宙本を読むより何倍も面白かったと思う。加藤先生は本当にすごい!難解な理論を喩えを用いてこんなにもわかりやすく説明できるとは。加藤先生自身もIUT理論に熱狂しているんだろ...
宇宙本コーナーにあったので手に取ったのだが、ゴリゴリの数学だった。が、読むうちにどんどん引き込まれ、結果として宇宙本を読むより何倍も面白かったと思う。加藤先生は本当にすごい!難解な理論を喩えを用いてこんなにもわかりやすく説明できるとは。加藤先生自身もIUT理論に熱狂しているんだろうなあと思わせる熱い文章で、画期性、有用性、イメージ感が伝わった。本書には数式はほとんど出てこないので置いていかれずワクワクが持続したが、論文だけなら意味不明すぎて興味を持つことすらなかっただろう。出版に本当に感謝。加藤先生は他にも一般向けのライトな数学本を執筆しているようなので、そちらも読みたい。 (どうでもいいけど、inter universeと日本語訳の宇宙際ってわりと受ける印象が違う気がする。。inter universeの方がしっくりくる。)
Posted by
IUT理論=宇宙際タイミヒュラー理論を提唱する望月教授の人となりと理論提唱の経緯、そして理論の概要がわかる。 読み進めるほど難しくなる。大局観が分かれば何を説明しているか分かるがディテールの理解は難しい。 個人的にはこの世界が何次元かという話とリンクした。いま近くできている3...
IUT理論=宇宙際タイミヒュラー理論を提唱する望月教授の人となりと理論提唱の経緯、そして理論の概要がわかる。 読み進めるほど難しくなる。大局観が分かれば何を説明しているか分かるがディテールの理解は難しい。 個人的にはこの世界が何次元かという話とリンクした。いま近くできている3次元の世界が全てではないのと同様、数学の世界も今近く出来る感覚以上のことが起こり得るということ。 新しい世界つくっちゃえよ、そことこっちをつないじゃえよ。 カッコイイ。
Posted by