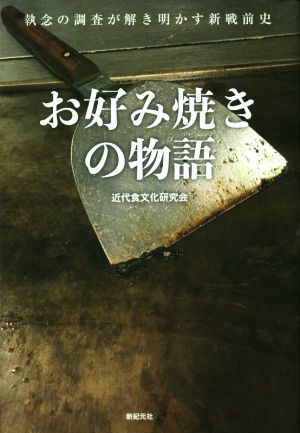お好み焼きの物語 の商品レビュー
「はじめに」の質が高い。筆者の背景や本書の執筆に至る経緯などが非常にわかりやすく記載されている。本編の内容自体も知らないことが多く、面白かった。ただ、本筋と関係ないトピックを延々と説明したり、別のトピックですでに説明した内容を再度引用付きで説明したりと、冗長に思える箇所はちょっと...
「はじめに」の質が高い。筆者の背景や本書の執筆に至る経緯などが非常にわかりやすく記載されている。本編の内容自体も知らないことが多く、面白かった。ただ、本筋と関係ないトピックを延々と説明したり、別のトピックですでに説明した内容を再度引用付きで説明したりと、冗長に思える箇所はちょっと読んでいてつらかった。あと、結局東京でお好み焼きが廃れてもんじゃ焼きが主流になっていった経緯が何だったのかと読んでいて気になったのだが、本書で説明されていなかったのが残念。あくまで本書は戦前までの解説で、このトピックは戦後の話になるからなのかな。
Posted by
実は大阪でなく東京でお好み焼きは生まれた。それは遊女との会食(自分で作るため擬似夫婦イベント)のためだった。大阪ではそれがなくなり、店員が焼くようになった
Posted by
お好み焼きがどのようにして成立したのかを文献調査から明らかにする。お好み焼きはなぜ「イカ天」「豚天」などと「天」がメニュー名になるのかといったことをはじめ、掘っていくといろいろと興味深い。もともとは屋台で「文字焼き」として水溶き小麦粉を子どもに焼かせるものに端を発し、洋食のパロデ...
お好み焼きがどのようにして成立したのかを文献調査から明らかにする。お好み焼きはなぜ「イカ天」「豚天」などと「天」がメニュー名になるのかといったことをはじめ、掘っていくといろいろと興味深い。もともとは屋台で「文字焼き」として水溶き小麦粉を子どもに焼かせるものに端を発し、洋食のパロディとして鉄板でソース味のものを提供するようになって「お好み焼き」というジャンルが成立したという説を本書はとっている。「もんじゃ焼き」は「文字焼き」から派生して、天ぷら系お好み焼きの影響を受け、キャベツやソースを導入し、戦後に発展したものだという。ソースがもともとは(イギリスの本家を含め)しょうゆベースのものだったという発見や、ソースさえかかっていれば「洋食」の扱いだったという習慣だとか、なかなかおもしろい。
Posted by
昔、Kindle限定で出ていてプライムで無料で読んで面白かったものが大幅な加筆修正されて出てきたので購入して再読。大昔のことを少ない資料から類推して記述していくのと真逆で膨大なお好み焼きに関する資料を踏まえてその発展の歴史を紐解いたもの。ソースの変遷などもあってかなり面白い。そし...
昔、Kindle限定で出ていてプライムで無料で読んで面白かったものが大幅な加筆修正されて出てきたので購入して再読。大昔のことを少ない資料から類推して記述していくのと真逆で膨大なお好み焼きに関する資料を踏まえてその発展の歴史を紐解いたもの。ソースの変遷などもあってかなり面白い。そして何より感心させられるのは本作が、恐らく今日的な手法なのだろうけどネットなどを中心に資料を読み解き整理していくことで成立していることでいわゆる従来型の取材などは行われていない、ということだろう。ノンフィクションというと関係者の取材の量がまずは、みたいなところがあるように思うけども極端にいうと引きこもりでもできる、という点で新しいノンフィクションなのかなという気がする。もちろん内容もかなり面白くておすすめできます。
Posted by
私は、野菜を作ったりするが、野菜があまり好きではない。そのため、中国で自炊していたときは、おでん、カレーとお好み焼きを代わり番こに食べていた。お好み焼きは、キャベツをたっぷり食べるからである。お好み焼きのフライパン返しもできるようになった。 お好み焼きの物語という題名に惹かれて読...
私は、野菜を作ったりするが、野菜があまり好きではない。そのため、中国で自炊していたときは、おでん、カレーとお好み焼きを代わり番こに食べていた。お好み焼きは、キャベツをたっぷり食べるからである。お好み焼きのフライパン返しもできるようになった。 お好み焼きの物語という題名に惹かれて読んだ。 お好み焼きの系統だった研究や本がないことから、2500冊近くの本を読み、徹底的なお好み焼き研究調書。とにかく、文献をあたり時代考証をする。しかし、文献だけでこれを構成するのは少し惜しい感じもする。また、視点を変えることで、同じ文献が出てくることで、繰り返し感が強いのは残念。もう少し、スマートに編集できないかなと思う。 お好み焼きとどんどん焼きについて調べる。どんどん焼きは、子供の食べ物で、お好み焼きは、大人の食べ物だったという。そこから、子供のこずかいはいつから発生したのかを考察する。 1820年頃(文化文政期)から、人口増加が始まり、江戸の様々な食べ物が生まれた。「食文化豊かな江戸」となり、大道芸的食べ物屋台で、文字焼きが生まれたという。もんじゃ焼きは、文字焼きのことだった。当初は、子供相手に、銅板に小麦粉を溶かしたものを文字を書いたり、亀の形を焼いた。それを文字焼きといった。屋台は動かなかった。そこから、屋台が動くようになり、鉄板となっていく。文字焼きから、人形焼などが派生していた。洋食屋台となり、レパートリーが広がっていく。イカ天、エビ天、あんこてん、牛天などが生まれていく。なぜ「天」というのか?①天かすを入れる②具をてっぺんにのせる③天ぷらから由来する。どうも、天ぷらから来ているらしい。天ぷらとは、その頃はさつま揚げの練り物のようなものだった。 なぜお好み焼きは洋食なのかといえば、ソースを使うものが洋食とされていた。ソースは、イギリスから来たが、ベースは醤油だった。戦後になって、今のソースの形ができていく。 それまでは、東京中心であったが、大正期に全国に広がった。大阪焼き、広島焼きと根付いていく。 お好み焼き店は、大阪が一番多いが、広島は人口に対して多く、2000店舗あるという。お好み焼き数を推定すると約2500万枚以上と言われる。ここでは、たこ焼きについて考証がないのが残念である。
Posted by
文字焼->お好み焼きは、なるほどと思う。しかし、引っ掛かるところもあり、全体に鵜呑みにはできない。 「天もの=天ぷらのパロディ」という言い方が、一番引っ掛かる。作者自身認めているように(p.23他)お好み焼きの、xx天と、本物の天ぷらは似ていない。著者は、似ていないのを楽し...
文字焼->お好み焼きは、なるほどと思う。しかし、引っ掛かるところもあり、全体に鵜呑みにはできない。 「天もの=天ぷらのパロディ」という言い方が、一番引っ掛かる。作者自身認めているように(p.23他)お好み焼きの、xx天と、本物の天ぷらは似ていない。著者は、似ていないのを楽しむのがお好み焼きと主張してすり抜けているが、そうなのか? お好み焼きで、天ものの代表格は豚天、肉天などであろうが、天ぷらに肉類はあまり無く、それなら、本書でも触れられている、西日本でいう「天ぷら=さつま揚げ」の方がよほど近い。それなのに、天ものは東京の天ぷらのパロディと言うのは、どうなのか。 Worcester SauceのLea & Perrinsをずっと「リーアンドペイリン」と書いているのも、すごく気になる。どうしてPerrinがペイリンになるんだよ。
Posted by
本文中でも注釈入ってたけど「お好み焼きの【新歴史】」ではなく「お好み焼きの【新戦前史】」なんですよね。 大タイトルで興味引いたんで、読前に抱いていた期待とは違った方向だったけど面白かった。 「お好み焼き」ではなく、そこへ至るまでの歴史。 これまでの通説には数々の誤りや間違いがあっ...
本文中でも注釈入ってたけど「お好み焼きの【新歴史】」ではなく「お好み焼きの【新戦前史】」なんですよね。 大タイトルで興味引いたんで、読前に抱いていた期待とは違った方向だったけど面白かった。 「お好み焼き」ではなく、そこへ至るまでの歴史。 これまでの通説には数々の誤りや間違いがあって、そこを指摘し改めるまでに戦前史を必要としたための【新戦前史】なんですよね。 本文を読むと分かるのですが、そもそも「お好み焼き」というメニューは無くて、料理のひとつだったという。 そういう誤解を紐解くに、料理ジャンルに限らず多岐に渡って市井の風俗を指摘していくのですよ。 「お好み焼き」に興味があって手に取った本ですけれど、しかしそれ以外の風俗について説明が多かったのが楽しかったですねえ。 子供のお小遣いの額とか、車輪文化の広まりとか。 そういったことが「お好み焼き」の始まりに繋がっていくとは、本当に世界は面白い成り立ちをしますよねー! 何が何に繋がっていくかは、結果を見ないと分からない。 これまで誤解や間違いを与えてきた通説を取り上げ、通説の何が誤っているか何故誤っているか、その指摘する様が痛快。 大体においてはその間違いの原因は資料の読み違えや、記憶違い、自分勝手な推測を現実だと語る…とか。 この辺り、昨今のSNSで流行るデマと似てるなぁ…と思います。 人間、変わらないんだなぁ(苦笑)。 本書において筆者は、そうした人達へのアンチテーゼとしてか自分を律してか、推測は推測として記し、更にはその推論には拘泥していない風を覚えます。 あくまで筆者の一意見。 通説の間違いを指摘する場面や、真に歴史として挙げるときは必ず複数の資料を挙げてその論拠を示してます。 当然といえば当然なんですけど、大きな声を出す人はこういう部分を隠してるかもなぁ…。 もちろん本書が絶対だと賛同するだけでは、自分もそうした誤読をする人と同じになるでしょう。 本書をもとに更に自分で知識を集める行為が必要。 否定をするなら感情論でも記憶に頼るのではなく、新しい証拠を示す。 そういう姿勢が大切なんだよなー。
Posted by
膨大な資料をもとにした戦前期のお好み焼きの歴史。描き出される歴史は鮮やか。こういうのが面白いと思ってしまうから資料調査が好きになってしまうんだろうなあ。これでここまで言えるかな、とか、体系性とかの問題はあるけど補ってあまりある。
Posted by
へー、ほー、ふうん、の連続。 面白い本だった。 ネットでちょちょいと調べればなんでもわかる世の中でも、ほんとのところをしっかり知ろうと思うと本になる。それがしみじみと感じられた。 わりかし演繹法というか、先にこうであるという結論を出しておいてなぜならば〜と根拠を挙げていく手法...
へー、ほー、ふうん、の連続。 面白い本だった。 ネットでちょちょいと調べればなんでもわかる世の中でも、ほんとのところをしっかり知ろうと思うと本になる。それがしみじみと感じられた。 わりかし演繹法というか、先にこうであるという結論を出しておいてなぜならば〜と根拠を挙げていく手法をとって書かれているため、お好み焼きとどんどん焼きの名称の部分のみ疑問は残った。そこだけ断言するには根拠が弱いように感じられたのだけど、資料を読み解く中で確信に至るものがあったのか?あったのだろうな。ということで納得しておく。
Posted by
- 1