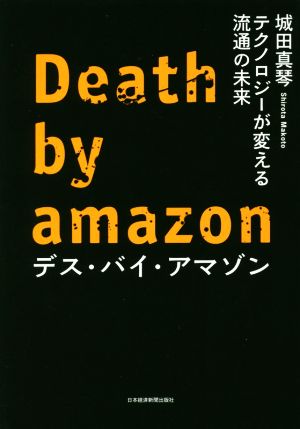デス・バイ・アマゾン の商品レビュー
積読してたらタイミングを逸してしまった感がある、出来るだけ早く読みたかった本。 ただ、5年経ってもAmazonの参入が多くの企業にとって破壊的であることには変わりないのではないかと思われる。 Amazonはもちろんのことリテールの現在と今後の概要をつかむには良い本だと思った。
Posted by
2018年の作品。流通小売業においてアマゾンの進出によって事業を継続できなくなる企業が続出する中、どのような企業が生き残れるのかを説いている。ターゲットをずらす、サービス性を磨く、サブスクリプション型にするなど、要するにアマゾンとは異なる土俵で戦うことが必要としている。しかし、ア...
2018年の作品。流通小売業においてアマゾンの進出によって事業を継続できなくなる企業が続出する中、どのような企業が生き残れるのかを説いている。ターゲットをずらす、サービス性を磨く、サブスクリプション型にするなど、要するにアマゾンとは異なる土俵で戦うことが必要としている。しかし、アマゾンがここまで巨大になると、どれもやがてはマネされ、飲みこまれる可能性は消えない。 本書の最後に出てくるように、アマゾンを超えるとしたら中国企業だろう。巨大な自国市場を持ちつつ、国の制度のおかげで膨大な個人データ、購買データを活用できる。後発の利で、新たに最先端の販売チャネルを構築することができる。欧米を含めグローバルに中国企業が拡大するのは難しいとは思うが、それでも十分かつ効率的な事業を展開できるだろう。 日本の場合は、既に構築された複雑な商流があり、また、旧態依然としたビジネスでもそれなりの事業規模があるため、新しいモデルに移行できない。このジレンマは、一度、グローバル市場で大きく後退し、かつ、人口が減り、再び若者の比率が増える時代まで改善されないのではないかとも考えてしまう。
Posted by
デスバイアマゾンという、アマゾン恐怖銘柄指数にまつわる、アマゾンに殺されないためにはどうすればいいのかが書かれている。 刊行は2018年でありやや古いが、EC業界の話はもちろん、流行りのサプスクリプションなど多岐に渡る。 ECの課題として、現物に触れない、配送の手間があげられるが...
デスバイアマゾンという、アマゾン恐怖銘柄指数にまつわる、アマゾンに殺されないためにはどうすればいいのかが書かれている。 刊行は2018年でありやや古いが、EC業界の話はもちろん、流行りのサプスクリプションなど多岐に渡る。 ECの課題として、現物に触れない、配送の手間があげられるが、これらの課題解決に様々な企業が取り組んでいる。 アパレル業界からは、試着の代わりに30日間返品無料の制度であったり、家具インテリア業界からは、AR技術を使ったイメージングなど。 企業のアイデアは本当に素晴らしいと思う。
Posted by
2020/10/12広島市図書館 ● デス・バイ・アマゾン=アマゾン恐怖銘柄指数 ●アマゾンの台頭によって窮地に陥るであろう上場企業銘柄の株価を指数化したもの ●アマゾン・サバイバーへの3つのポイント 1圧倒的な商品力で差をつける 2カスタマイズ・パーソナライズの徹底 3痒いとこ...
2020/10/12広島市図書館 ● デス・バイ・アマゾン=アマゾン恐怖銘柄指数 ●アマゾンの台頭によって窮地に陥るであろう上場企業銘柄の株価を指数化したもの ●アマゾン・サバイバーへの3つのポイント 1圧倒的な商品力で差をつける 2カスタマイズ・パーソナライズの徹底 3痒いところに手が届くサービスの提供 ユーザエクスペリエンス
Posted by
Amazonの野望と殺されないための方法。 Amazonはもはや全ての王に君臨しており、同じ土俵で戦ってはいけない。 Amazonと戦えるのは、 『ホームデポ』のような専門業者向けや パーソナルな価値を提案できるもの(オーダーメイド)である。 今後どのようなサービスと物流で迫って...
Amazonの野望と殺されないための方法。 Amazonはもはや全ての王に君臨しており、同じ土俵で戦ってはいけない。 Amazonと戦えるのは、 『ホームデポ』のような専門業者向けや パーソナルな価値を提案できるもの(オーダーメイド)である。 今後どのようなサービスと物流で迫ってくるか分からないが、今後もAmazonにより、購買のハードルはどんどん下げられるであろう。
Posted by
Amazonの取り組みとライバルのまとめ。 d2c direct to consumer ショールーミング 小型店舗展開、在庫を持たない ショップエクスペリエンス Amazonと同じ土俵に立たない バルク契約 フォトサーチ ドロップシッピング ディスラプター 破壊者 オネストカ...
Amazonの取り組みとライバルのまとめ。 d2c direct to consumer ショールーミング 小型店舗展開、在庫を持たない ショップエクスペリエンス Amazonと同じ土俵に立たない バルク契約 フォトサーチ ドロップシッピング ディスラプター 破壊者 オネストカンパニー ジェシカアルバ カスタマイズ パーソナライズ ニューリテール アリババ 3km以内30分着 リアル店舗在庫=ec在庫 注文→ピックアップ 店内にいけす その場で調理→飲食 オムニチャンネル 手軽さ、便利さ、体験、撒き餌、敷居、心理的障壁、選択疲れ、現状維持バイアス、顧客の課題解決、ファン獲得、選択と集中、付加価値、トータルサービス アメリカは法整備も同時進行で早いな。日本が遅すぎるのかもしれないが。全部後手だから首相官邸にドローンが来たりする。 ウォルマートのジェットブラック、いいなぁ。何かわからないものを検索するって大変なんだよね。探してくれるのありがたいね。軽量のリサイクルバッグってどんなのなんだろう。 Googleエクスプレス、Googleショッピングアクションを知らなかった。日本にもぜひ。元会長が言うまでもなく、どう考えてもGoogleの最大のライバルはAmazonでしょう。 でもそれならショッピング検索の精度や検索のしやすさをもっと上げてくれればいいのに。商品のサイズ検索とか。
Posted by
小売について知ろうとすれば、Amazonが何をしているかを把握すれば凡そ把握できるという世の中になったと感じさせる本です。 内容的には情報の羅列であり、既知の情報も多いです。 真新しさや、新たな考察を求めると、期待とは違う感じになります。 総じて情報の整理には良い本です。
Posted by
Amazonの取り組みとそれに対抗する各社の取り組みを纏めたもの。 驚きはないが、情報収集のためと考えれば⚪。
Posted by
「Amazon恐怖指数」とは、Amazonの株価に反比例する株価指数。そんな指数が存在するほど、Amazonは既存の小売業で強大な存在になっている。 ・Amazonがリアル店舗に進出している。それはAmazon Primeへの導線でもある。 ・Amazon Goは赤字かもしれない...
「Amazon恐怖指数」とは、Amazonの株価に反比例する株価指数。そんな指数が存在するほど、Amazonは既存の小売業で強大な存在になっている。 ・Amazonがリアル店舗に進出している。それはAmazon Primeへの導線でもある。 ・Amazon Goは赤字かもしれないが、顧客のオフラインのデータを集める位置づけの投資。それを可能にしているのはAWS事業で利益を稼いでいるから。 ・ECにも参入し、Echo Lookも合わせて投入している。 一方でAmazon Surviverも存在する。 ・顧客層のすみ分け ・課題解決型のソリューション提供 →かゆいところに手の届くサービス提供 ・商品力、ブランド力の強化 →カスタマイズ&パーソナライズ などの特長を持っている小売りは駆逐されずに残っている。
Posted by
面白かった。著者はシンクタンクの研究員ということで、着眼点が良く考察が鋭いなと思った。恐ろしさ半分この先のAmazonの展開が大変気になる。
Posted by
- 1
- 2