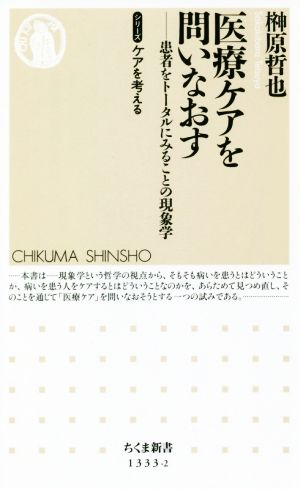医療ケアを問いなおす の商品レビュー
医療ケアを現象学の視点から捉え直した本。疾病と病、癒し癒される関係。安らぎとしての健康の回復と増進。非常に腑に落ちながら読みました。現象学の言葉を丁寧に解説してくださっているけども、聞き慣れない言葉なので、なかなか読むのに骨が折れました。繰り返し読むと味わいが深まりそうです。
Posted by
医師と看護師等で、患者の捉え方が異なるのはなんでだろう。と考えていたところ、この本に出会った。現象学という手法を通じて、患者と医療者のやりとりを解き明かし、ケアとは何か、ケアの目的とは何か、今求められているものとは何かを、病と病気の違いなど、ベナーの看護論を援用しつつ一つ一つわか...
医師と看護師等で、患者の捉え方が異なるのはなんでだろう。と考えていたところ、この本に出会った。現象学という手法を通じて、患者と医療者のやりとりを解き明かし、ケアとは何か、ケアの目的とは何か、今求められているものとは何かを、病と病気の違いなど、ベナーの看護論を援用しつつ一つ一つわかりやすく解説した本。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
フッサール、ハイデガー、メルロポンティの哲学を丁寧に引いていって、最終的にはベナーの看護論へ。看護に必要な気遣い。若い病棟Nsへの勉強会で一部引用して使いたい一冊でした。
Posted by
フッサールの言っていることがほんのちょっと分かったような気がした。自然科学全般について言っていることを本書では医療の分野に置き換えて書いているわけだが、患者のデータばかり見て、患者が訴えていることをきちんと聴こうとしない姿勢を憂えている。私にも何度も同じような経験がある。こちらは...
フッサールの言っていることがほんのちょっと分かったような気がした。自然科学全般について言っていることを本書では医療の分野に置き換えて書いているわけだが、患者のデータばかり見て、患者が訴えていることをきちんと聴こうとしない姿勢を憂えている。私にも何度も同じような経験がある。こちらは痛いと思っている。長期にわたるし、そうそうがまんもできないので、みてもらいに行く。検査をする。何も見つからない。医者は言う。どこも問題ないです。・・・というようなことがあるかもしれませんが、まあ様子を見ましょう。それでおしまい。何の解決にもなっていない。長男が微熱が続いて心配で病院に連れて行ったこともあった。そのときも、どこも異常が見つからない。風邪薬だけもらって帰って来る。時間とお金の無駄。もっとも、安心がほしくて検査をしてもらうという意味もあるので、大きな疾患がかくれているわけではないというのは安心材料ではある。要するに心の問題なんだろうと思う。それはふつうの医者では何ともならないんだろうか。患者の訴えに耳を傾ける、患者をトータルにみる、そういうことができる医療従事者が1人でも増えればいいと思う。ハイデガーやメルロポンティについては結局何も頭に残っていない。
Posted by
さすが榊原先生。クリアで中身の充実した解説でした。 内容をまとめると・・・ ○現象学の知見による人間理解すなわち<ある人の生きられる現実、そしてその意味は、意味経験を成立させる意識の志向性や関心、身体にもとづく>という理解をベースに、医療現場において「患者をトータルでみること」に...
さすが榊原先生。クリアで中身の充実した解説でした。 内容をまとめると・・・ ○現象学の知見による人間理解すなわち<ある人の生きられる現実、そしてその意味は、意味経験を成立させる意識の志向性や関心、身体にもとづく>という理解をベースに、医療現場において「患者をトータルでみること」について、看護の現象学の代表的議論を紹介しながら解説 ○「患者をトータルでみること」は、医師が行う客観的な「疾患」把握(自然科学的態度)だけではなく、それぞれの患者の具体的状況に応じた「病い」経験(自然的態度)に目をむけてよりそうことがポイントになってくる。 クリアな解説はもとより、著者が実際に現場に出て取材してきた事例なども取り入れているので、ぐっと説得力が増しています。 私個人の感想としては、現象学の知見をこんなふうに応用できるというのがわかっておもしろかったです。これは医療現場だけに限らず、制度を所管する側とそれを利用する側が、それぞれの状況や態度のちがいを有しているような現場ではおしなべて応用できることなのかもしれないと感じました。 あと、『イスラーム哲学の原像』のときはハイデガーの神秘主義的部分を念頭に置きながら読んでいましたが、今回はハイデガーの現存在分析を念頭に置きながら読みました。そう考えると、ハイデガー研究の応用範囲というのはものすごく広いような気がしてきました。(2018年7月14日読了)
Posted by
- 1