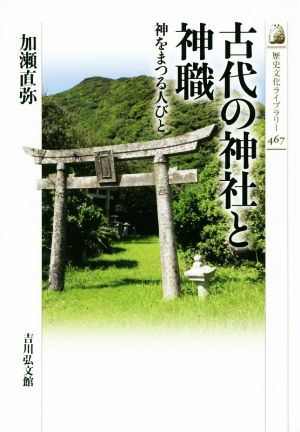古代の神社と神職 の商品レビュー
祀りの多様性、外来方式の受け入れ、 山の神社=山全体or高所 田の神社=領域の端or水域 河の神社、海の神社 祝部、氏族によるマツリ。
Posted by
古代の朝廷と神社との関わり方について書かれた本 大まかな内容は、立地や境内に焦点をあてそこから神社の重要性を考察、次に神職の役割がどう変化していったかの二部構成になっている。 残っている資料だったり、そもそも神社各々で成り立ちが違ってたりするので一部は比重が軽く、神職と朝廷との...
古代の朝廷と神社との関わり方について書かれた本 大まかな内容は、立地や境内に焦点をあてそこから神社の重要性を考察、次に神職の役割がどう変化していったかの二部構成になっている。 残っている資料だったり、そもそも神社各々で成り立ちが違ってたりするので一部は比重が軽く、神職と朝廷との関わり方を中心とされている印象。 神格だったり把笏などの服制だったりと、朝廷が神社をどう掌握しようとしていたかが興味深い本だった。
Posted by
多様なる古代の神社と共通する神職の姿勢―プロローグ 古代神社の立地と社殿の役割 平安時代前期の神社とその維持 古代神職の職掌 笏と神職 古代神社の女性神職 神社と神職にとっての転機―エピローグ 著者:加瀬直弥(1975-、神奈川県、神道学)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・加瀬直弥「古代の神社と神職 神をまつる人びと」(吉川弘文館)の執筆目的は、「あとがき」によれば以下の如くである。「神社の様子はそれぞれ個性がある。(中略)だが、それら神社がひとまとまりとして見られる。そう受け止められるきっかけを探るために本書を書いた。(原文改行)着目したのは、一元的な神社制度がまとまった形で整備されはじめたのはいつかというところである。(中略)神職制度に焦点を絞って、少し広めに神社を見ることとした。(原文改行)奈良時代末期から平安時代前期、特に平安時代初期の制度整備は、神社の公的性格を高める、あるいは独立採算のしくみを確かにするといったもので、現代の神社の特色にも通じる。」(215~216頁)つまり、一括りに神社とされるのは特に平安時代初期の制度整備によるところが大きいから、そこを中心に本書を書くといふことである。実際にはこれ以前の記述も多くある。始原の神社の姿はといふやうなことにも触れる。これらはおもしろいのだが、個人的にはその書きぶりが気になる。本書はこれまでの著作をまとめたものであるらしい。歴史文化ライブラリーの1冊であるから一般向けの書である。必要以上に専門的にならない。それは良いのだが、それにしても、記述に味も素つ気も無いのである。さう、無い。これを事務的と言へるかどうか。もう少し書きやうがありさうなものだと思ふところがいくつもある。これらは更に書きたいところをここまでしか書かなかつたからかうなつたのかもしれない。それならそれで書きやうがありさうだと思ふ。本書を読みながら最も強く感じてゐたのがこの点であつた。 ・内容はといふと、さすがに始原の神社についてはほとんど触れられないのだが、史料の残る神社について触れ、そこから古代の神社について述べる。これを一言で言へば、「神社の様子はそれぞれ個性がある。」に尽きさうな気がする。「古代の人びとが考える神とは、現代よりも多様であった。」(7頁)から、蛇体の神もゐたりした。その神を祀る神社は、山の神の場合、山上、山麓に偏らず、「立地の決め手は神社それぞれの事情によった。ただ、どちらからも『神を隔てる意識』が垣間見られる。」(25頁)しかも、「それは場所が変わっても同じだったと理解でき」(同前)るから、田の神や水の神でも同じらしい。ただし、その社殿に関しては、「奈良時代には、伊勢大神宮のような社殿のある神社が特別で、社殿のない神社もそこそこあったのではないかという見立てができる。」(75頁)もちろん社殿はなくとも「神を隔てる意識」はあるので、「社殿は神のためのものであるならば、そこに人が出入りすることは本来的ではない。」(64頁)から、現代でも本殿は開放されてゐないのである。社殿がなければその仕切り、注連縄(?)から先には入れないだけのこと、今も昔も変はらない。平安時代初期に社殿が一般化していくらしい(98頁)が、それ以後でも「神社の現場の状況で、社殿を作るかどうか判断できる余地があった」(99頁)といふから、本来的には、神社には必ずしも社殿は必要ないのであるらしい。実はこの社殿の有無の問題、個人的に気になつてゐた。常識的には社殿は後からだらうと思つてゐた。さうであつたらしい。しかも、そこに時の朝廷の意向の反映があるらしい。現代の神社はかなりが人家の中にある。だから社殿は必要であらう。奈良平安といふ時代にもそのやうな事情もあつて社殿が必要とされたのかどうか。社殿の問題が分かつただけでも、文体を我慢すれば、読むに値する書であつた。今も昔も「神社の様子はそれぞれ個性がある。」のである。
Posted by
- 1