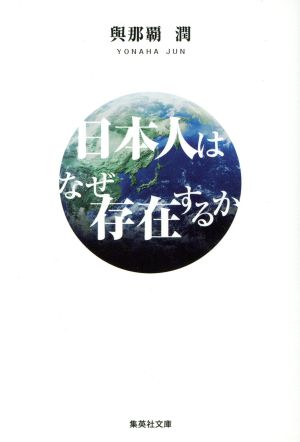日本人はなぜ存在するか の商品レビュー
著者の『中国化する日本』という本がめっぽう面白かったので、勢いで買っておいていた一冊が、たまたま履修した外国書講読の授業でナショナリズムに関する本を読むことになったときに理解の一助となった。ナショナリズム(学術的な意味)に関する本だと思って読むとこの本もめっぽう面白い。ナショナリ...
著者の『中国化する日本』という本がめっぽう面白かったので、勢いで買っておいていた一冊が、たまたま履修した外国書講読の授業でナショナリズムに関する本を読むことになったときに理解の一助となった。ナショナリズム(学術的な意味)に関する本だと思って読むとこの本もめっぽう面白い。ナショナリズムの話の射程の広さがわかる一冊とも言えるかもしれない。
Posted by
http://www5e.biglobe.ne.jp/~utouto/uto01/yoko/kikay.html
Posted by
読み終わってあまりの感動に何度も何度も読み返して、その後もまた一年毎にに読み返している本。私にとっては「これぞ教養」という見事なお手本。 基本的には「再帰性」という概念を軸に、日本人とはだれかを、様々な学問分野の手法を用いて探っていく。 根拠を国籍に求めても見つからない。民族に...
読み終わってあまりの感動に何度も何度も読み返して、その後もまた一年毎にに読み返している本。私にとっては「これぞ教養」という見事なお手本。 基本的には「再帰性」という概念を軸に、日本人とはだれかを、様々な学問分野の手法を用いて探っていく。 根拠を国籍に求めても見つからない。民族に求めても見つからない。言葉でも文化でも歴史でも領土でも同じ。 日本人とは誰か:日本国籍を持っている人。 日本国籍は誰に与えられるのか:日本人。 日本人とは誰か:日本語を喋る人。 日本語とは何か:日本人が話す言葉。 キリがない。これでは定義したことにならない。「ここに書いてあることは嘘である」が真とも偽とも決められないように、循環参照している言説は無効である、というのがロジカルな考え方だが、本書はそうではない、むしろありとあらゆるものが再帰的にしか定義できないのが近代だという。 この無限ループは息苦しい。だからニーチェは神は死んだといいフーコーは人間の終焉を予言した。だけど、再帰性の循環参照のどこかに綻びを見つけてそこから新たな可能性を開くことは可能で、そのためにもこの再現性のメカニズムをしっかりと学んで欲しい。そんな著者のメッセージが感じられる本です。 ■目次(章レベルまで。節レベルは◯◯学で考えるとついたもののみ抜粋) introduction グローバル時代の「教養」とは何か Part1 入門編 日本人論を考える 第 1 章「日本人」は存在するか 見る人がいなくても「夕焼けは赤い」か?−−哲学で考える 「日本人は集団主義的」は正しいか?−−心理学で考える 私たちはどんな時代に生きているのか−−社会学で考える 第 2 章「日本史」はなぜ間違えるか 戦後の「民主化」で選挙権を失った人たち−−メタヒストリーで考える 第 3 章「日本国籍」に根拠はあるか 「血のつながり」が指す範囲も文化によって違う−−民俗学で考える 「死んだ人が子供を作れる」ルールとは−−文化人類学で考える 第 4 章「日本民族」とは誰のことか ウルトラシリーズの歩みは、いつも沖縄とともに−−地域研究で考える 第 5 章 「日本文化」は日本風か 『蛍の光』で愛国心を歌った国−−カルチュラル・スタディーズで考える Part2 発展編 日本人論 で考える 第 6 章「世界」は日本をどう見てきたか 「イメージ」は現実を支配する−−比較文学で考える 「日本人論が好きなこと」が日本人の個性−−比較文化で考える 第 7 章「ジャパニメーション」は鳥獣戯画か 手塚治虫が泣いた戦時国策アニメ−−新歴史主義で考える 日本のアニメは「中国起源」?−−ポストコロニアリズムで考える 第 8 章 「物語」を信じられるか 「日本史」がなくなれば、日本人もいなくなる?−−ナラトロジーで考える 第 9 章「人間」の範囲はどこまでか 「神は再帰的だ」と喝破したニーチェ−−ポストモダニズムで考える 第 10 章「正義」は定義できるか 近代西洋が選んだ「自己決定」と「功利主義」−−思想史で考える 臓器移植のための「公正な殺人」はありえるのか?−−倫理学で考える 解説にかえて 平成のおわりから教養のはじまりへ
Posted by
「中国化する日本」に続いて二冊目。 今回のテーマは、私の理解では「再帰性」。「必ずしも自明には存在しないものが、思い込みをつうじて本当に実体を持ち始めてしまうこと」と解釈してみる。つまりは著者は「日本(人)って当たり前に存在していると思っているひとが多いが、では日本(人)とはなに...
「中国化する日本」に続いて二冊目。 今回のテーマは、私の理解では「再帰性」。「必ずしも自明には存在しないものが、思い込みをつうじて本当に実体を持ち始めてしまうこと」と解釈してみる。つまりは著者は「日本(人)って当たり前に存在していると思っているひとが多いが、では日本(人)とはなにか正確に答えられますか」、ということを言っているのだと思う。戸籍、歴史観、伝統文化などを取り上げながら、「現代の当たり前」を問い直していく。 もちろん、「日本の伝統なんて幻想」といったリベラル論もまた再帰的であることもこの著者特有の皮肉っぽい調子で指摘している。実際、再帰的であることは悪いことなのか、という問いも立てねばならないだろう(そもそも究極に再帰的な存在は「神様」)。 万物は神が作った、という西洋の世界観は科学によって書き換えられた。「近代には『この世界が再帰的であること』を知ることは、伝統からわれわれを解放してくれる喜びに満ちた体験でした。しかしポスト近代のいま、私たちはむしろ『すべてが再帰的であり、すなわち私たち自身の責任であること』を知って、苦しんでいる」(文庫版P168)。「あれもこれもしょせんは再帰的」と相対主義の無限ループに陥っている、ということだろうか。 「君の名は。」や「シン・ゴジラ」を考現学的に論じる本書終盤の議論は前半ほどの迫力は感じられず(ほんとはここが楽しみだったのに・・・)、まさに「なんでも相対化」のループに入っているようにも思えた。ただ、そうしたことも含めて考える素材に満ちたエキサイティングな本であった。
Posted by
再帰性という考え方を初めて知りました。世の中のあらゆることにそれを見つけてみることから始めたいと思います。
Posted by
人文社会系の基礎編総ざらいといういかにも教養科目っぽい内容を与那覇カラーでやるというだけで惹かれる人は惹かれると思う。期待通りの揺さぶる内容。
Posted by
「再帰性」をキーワードに日本人、日本史、日本文化を捉える。再帰性とは認識と現実のあいだに生じるループ現象のこと。著者は、現実の社会を見るには「再帰性」の相互連関を見なくてはいけない、という姿勢に徹している。 また、特定の文脈を超える力としての教養が目指されていて、社会学、メタヒス...
「再帰性」をキーワードに日本人、日本史、日本文化を捉える。再帰性とは認識と現実のあいだに生じるループ現象のこと。著者は、現実の社会を見るには「再帰性」の相互連関を見なくてはいけない、という姿勢に徹している。 また、特定の文脈を超える力としての教養が目指されていて、社会学、メタヒストリー、文化人類学、民俗学、カルチャルスタディーズなどが次々と簡潔に紹介される。
Posted by
- 1