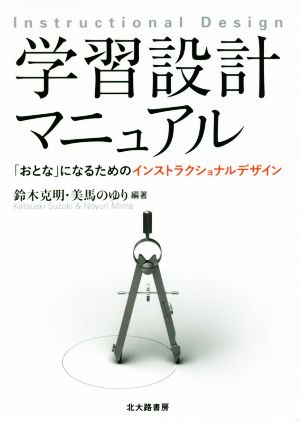学習設計マニュアル の商品レビュー
第1部 自分の学びと向き合う 第2部 学びの場をつくる 第3部 学び方を工夫する 第4部 これからの学びを考える
Posted by
情報科学科 稲葉利江子先生 推薦! 学び方を学ぶための一冊。「学ぶ」ことはどういうことか、「学ぶ」方法とは…を大学1年生にも分かりやすく書かれています。
Posted by
第一部:自分の学びと向き合う <図表はEvernote> 第二章:学習スタイルの把握 ①アドラーよりライフスタイルを4つに分け、何を各人が優先しているかを明らかにすることができ、コミュニケーションのトーンを決めることができる。 ・対人関係優先か課題達成優先 ・受動的か能動的か ...
第一部:自分の学びと向き合う <図表はEvernote> 第二章:学習スタイルの把握 ①アドラーよりライフスタイルを4つに分け、何を各人が優先しているかを明らかにすることができ、コミュニケーションのトーンを決めることができる。 ・対人関係優先か課題達成優先 ・受動的か能動的か ②学習スタイルVAKTモデルに着目 →自分のスタイルを把握することで、書き写して勉強するのがいいかなど判断できる。 Visual:視覚型学習者 Auditory:聴覚型学習者 Kinesthetic:運動感覚型学習者 Tactile:触覚型学習者 第三章:学び方を振り返る ①認知主義的か非認知主義的か? 認知主義的:学びの質に重きをおいている学び方 非認知主義的:学びの過程を重視せずに、学びの量や結果を重視 メタ認知が学習の深さにおいては重要になるため認知主義的な比重を増やす ②普段の学習で心がけることはそれに対する構えを持つこと! ・読む目的をはっきりさせ、そこから得られうことを予想して、メモの形で書き出しておくこと ・呼んでいる最中に、書いてあることは本当か、何故そうなったかなど批判的に読んだり、自分の生活や感情、知ってることと関連付けるべし。 ・誰かに説明するつもりでメモを書く←自分の思考の外に出すことで評価できる。 第4章:学びの深さを考える ①知識は3種類ある ・個人的知識:直接体験を通じて得られる知識(間違ってることも大いにある) ・手続き的知識:やり方を知っているタイプの知識、例えば泳げるとか ・命題的知識:学校などで習う、本当のことだと認められている事象 ←これは将来的に変わる可能性もある。暫定的に事実なだけ。 ②知識の信憑性を見極めるための問い バカロレアディプロマプログラム:知の理論で紹介されてる⑧つの問 1.誰にとって真実なのか? 2.どんな根拠から真実だと主張されているのか 3.知識に関する主張は、私が以前から真実だと信じている知識に関する主張と一致するか、矛盾するか? 4.どの程度社会はこの真実を事実だと信頼しているのか? 5.どの程度私は、同上? 6.この主張が真実だと認めるとどういう結果になるのか? 7.この主張は確かだとみなすかみなさないかで、どんな違いが生じるか? 8.私が、この主張の真実性を認めなければどんな結果に直面するか? ←知識の具体的な中身を学ぶのではなく、知識とはなにか、股どう作られており、どのような手続きとしてその正当性を認めるかを学ぶ。 ③ペリーの認知的発達段階説:4段階で発達する 1.絶対主義的段階:正解は存在し、誰かが教えてくれたらいいと思っている 2.相対主義的段階:専門家が正解を知らない場合は、誰もが「誤り」とは断定されないから自分の考えも主張されるべきだ(根拠の強さによらず) 3.評価主義的段階:知識は質的であり、意見を支える論証の中身によっては同じ重要度で評価されないのは当然だ。視点そのものが有用だ 4.コミットメント段階:個人的な意義が大事。成績なんぞの評価を飛び越え、自分ごととして捉えている 第5章:学問分野の特色を把握する ①自然科学と社会科学の違い ・自然科学 ←「事実」「法則」「理論」の3種類がある 科学知識の暫定性(5日否定されるかもしれないこと)があるうえで現場のベストな内容を学ぶというスタンス ・社会科学 可謬主義(人が行うことは間違う可能性が常にある)があるべきスタンスであるため、多角的味方が本質的。誤りを犯しうるから、お互い意見を聞いて討論しましょう、勝敗を決めるためではなく、色んな可能性を見つけるためにやりましょうという思想。 ・概念形成のために使った個別事象はどっちでもいいけど概念形成が大事! ・ある領域の学びから多くの収益を得るための8つの問 1.この科目を学ぶゴールはどこか? 2.この領域の人たちが達成しようとしていることはなにか? 3.彼らの問題提起はなにか?どんな問題を解こうとしてるのか? 4.彼らはどのような情報データを集めているか 5.彼らの領域に特有の情報収集方法はなにか? 6.その領域で最も基本的な考え方概念理論はなにか? 7.この領域を学ぶことで、自分自身の世界の見方にどう影響するか? 8.この領域からの成果が日常生活に使われているか? ・
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
大学の新入学生向けに書かれた大学教育における学習者の立ち位置を学ぶという体だが社会人も読むべき内容である。 教える人、教えられる人と二分して考えがちであるがもともと学習とは学ぶ側当人がデザインしたした方が効率的である。大量消費・大量生産と同じ理屈で暑中等教育に放り込まれてしまうとその点について見落としがちである。 この書籍は学習に関する研究等を引用し学ぶ人自身がカスタマイズして学びを作っていくための手引き=マニュアルになっている。 書籍自身がこの学びのあり方を実践しているので「教科書」「教材」として参考にする価値もある。一粒で二度美味しい。
Posted by
自身の大学の授業に,インストラクショナル・デザイン視点を入れてから,15年がたった。当初は,教材設計マニュアルを利用し,今は,自分が分担執筆者にもなっている授業設計マニュアルを活用している。「教え方」を学ぶための本として活用しているわけだが,やっていると,「これは学び手である自分...
自身の大学の授業に,インストラクショナル・デザイン視点を入れてから,15年がたった。当初は,教材設計マニュアルを利用し,今は,自分が分担執筆者にもなっている授業設計マニュアルを活用している。「教え方」を学ぶための本として活用しているわけだが,やっていると,「これは学び手である自分に置き換えてみると,学習の手引となる」ということを実感できるようになり,大学の講義においてはそうしたことを伝えようとしてきた。 そうしたなんとなくの思いが学習設計マニュアルという書籍には,見事に反映されている。自分の学びをデザインするという視点から,章立ては比較的細かく用意されている。大学での導入教育等で活用することを意図しており,非常にわかりやすい。それだけではなく,大学院生にもおすすめしたいと思った。 本書は,教育工学を研究するという立場からも,興味深い書籍である。教授ー学習デザインを考える際に,どの点から考えればよいか,その視点を提供してくれる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
【書評】急速に変化する社会を生き抜くためには、自身の学び方をまず知ることだ『学習設計マニュアル』 本書は自分の「学び方」について振り返り、今後学んでいくにはどうしたらいいかを考えさせてくれる。 「学び」というとつい学校教育を想定し、自分はもう大人だから関係ないと思いがちだ。 しかし急速に様々な物事が変化する世の中では、 一生学び続けなければ取り残されてしまうだろう。 本書を読めば、様々な教育理論の観点から「得意な学習スタイル」と「苦手な学習スタイル」が浮き彫りになる。 そうすることで自分がより伸ばすべきところや、克服すべきところが見えてくる。 そしてゴールは「アクションプランを立て、行動に移す」ことである。 よく「あの人みたいになれたらなぁ」と語る人も多いが、決して今の自分から変わることは不可能なことではない。 自分自身の足りないところがあるのであれば、そこが足りるようにアクションすればいい。 その助けとなる学び方は、本書に書いてあることをヒントにすればいいのだ。 また本書では章ごとに「最初に考えてみよう」「もう一度考えてみよう」「練習」と自身のアウトプットの場が用意されている。 読みっぱなしではなく、しっかりと学んだことや整理したことをアウトプットできる部分が本書のポイントだ。 私は自身の将来に不安を覚えている。 自身の着想力が乏しいことに気づいたからだ。 ただ、今気づけたことが何より幸いだ。 乏しいこと=伸び代であり、自分の今後のアクションに気づくことができたから。 これからの厳しい社会を生き抜くために、 本書を参考に日々学んでいきたい。
Posted by
学術的な要素が強く、体系だった構成。 最初に章立てを図で表していたが、それだけで、本の構成、学習計画の立て方の流れがとても分かりやすい。
Posted by
- 1