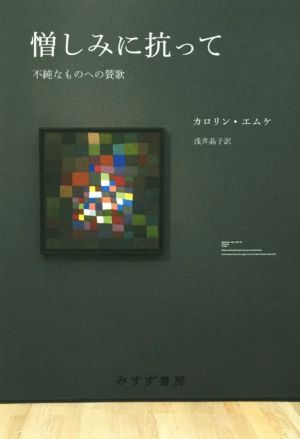憎しみに抗って の商品レビュー
世に蔓延る差別に対する指南書 多様性なんて言葉が流行りとして使われてるうちはダメなんだろうなぁ そして皆にこの本をお勧めしたいが、まず読むのが(内容的にも)面倒くさいと感じるであろうと察するので、まずはその面倒くささを取っ払う活動しようっと
Posted by
2018年18冊目。(再読) 〉2018年17冊目。 〉読み始めてすぐに心臓がばくばくし、読み終えてすぐに「もう一度読まねば」と急き立てられた。 の通り、初読の直後にもう一度読んだ。思うところが多すぎて、それでもまだうまくまとまらない。長く付き合うことになる一冊。 =====...
2018年18冊目。(再読) 〉2018年17冊目。 〉読み始めてすぐに心臓がばくばくし、読み終えてすぐに「もう一度読まねば」と急き立てられた。 の通り、初読の直後にもう一度読んだ。思うところが多すぎて、それでもまだうまくまとまらない。長く付き合うことになる一冊。 ========== 2018年17冊目。 読み始めてすぐに心臓がばくばくし、読み終えてすぐに「もう一度読まねば」と急き立てられた。 近年悶々と考えていたことが、物凄い密度の言葉で語られていた。 言葉の力が強過ぎて、「陶酔して盲目にならぬよう、気をつけて読まねば」とも思うくらいに。 流入する難民、異なる人種、性的マイノリティ... 制度化・内面化された「基準」とは異質とみなされる者たちへの「憎しみ」は、どのように生まれるのか。 著者は、「憎しみ」は個人的で偶然の産物ではなく、集合的・歴史的に形成されてきたイデオロギーという下地の上に生まれるものだととらえている。 侮辱に用いられる概念や、レッテルを貼るのに用いられる知覚パターンは、歴史の中で繰り返され、固定化され、再生産されてきた。 だからこそ、憎しみに駆られた個人を断罪する以上に(それが必要な場面もあるが)、その裏にあるメカニズムを正確にとらえよう、と主張する。 第一部の「可視 - 不可視」では、マイノリティの立場にある者たちが排除されるプロセスを、 ①一人ひとりの個性が見過ごされ(不可視化) ②過度に一般化した集団として作り上げられる(可視化) と分析している。 続く第二部「均一 - 自然 - 純粋」では、差別をする側の立場の者たちが利用する3つのモチーフが語られる。 それぞれに共通するのは、ファナティスト(狂信者)たちが重要視するものは「一義性」だということ。 「異質」「敵」「虚偽」な者たちを想定し、それを排斥することを前提として、純化した共同体を作ろうとしていること。 純化された狂信的な教義に、別の純化された狂信的な教義で対抗してはいけない、と著者は語る。 こちらまで狭義的にならず、多様で不純なものを受け入れる姿勢を貫くこと。 その想いは、サブタイトルにも表れている。 ... 「憎しみ」とは、一つの誘惑だと感じる。 「憎しみ」は、不明瞭な個人を明瞭に見ようとする労を省いてくれる。 単純化したレッテルを貼り、疎外すべき集団として単純化・明瞭化してくれる。 不明瞭な事態に対する忍耐力として「ネガティブ・ケイパビリティ」という概念がある。 決して分かりやすくはない多様なものを受け入れる力として、それがいま強く求められている気がする。 不正なことに対して、「それは不正だ」と反対の声をあげることはとても重要。 そして、それを信念を持って表現している著者への敬意を強く感じる。 同時に、その声のあげ方一つで、お互いの考える正義感の衝突が強まり、分断がより深くなってしまうこともあるのでは、という懸念もある。 そうした分断のしわ寄せは、まさに守りたかったはずの社会的弱者たちに押し寄せる。 マイノリティに対して憎しみを抱く側も、憎しみを抱く者たちに反対の声をあげる側も、ネガティブ・ケイパビリティを失わず、自分たちの見方に常に考慮の余地を持っておくことを忘れてはいけないと思う。 確かに「人権を守る」ということは普遍化してきた概念で譲歩できないことでもあるのだけど、相対している者たちとの接触の中では、「自分の考えは常に暫定的である」という自覚を持ち、お互いに想像を広げていく余地は持たなければ、建設的な対話は生まれないと感じる。 頑なな正義の押し付けが、必ずしも不正を正してくれるとは限らない。 ある意味で、正義感は常に不安定でなければならないのかもしれない。 「憎しみに抗う」気持ちが高じ過ぎて、「憎む者たちへの憎しみ」に陥らぬよう、安直な正義に頼りすぎず、分かりやすさに逃げず。 そんな自戒を持ちつつ、この本は繰り返し何度も読みたいし、読んでみて欲しい人たちが多い。 まだ日本で訳されていなかったこの著者の本を出版してくれたことに感謝。
Posted by
- 1
- 2