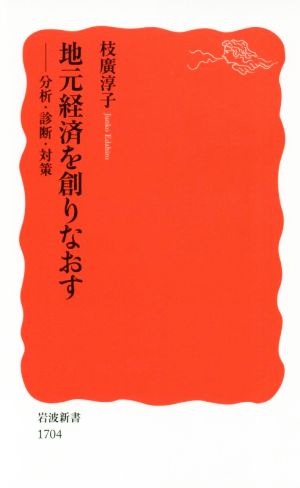地元経済を創りなおす の商品レビュー
人は生活をする上で安くて便利なものを選択したがる、世の中もテクノロジーの発展によりどんどん便利になってくる中で、人も合理的にその流れに則って流動していく。そもそもこのままの将来を辿った時にどんな問題が生じていくかの問題認識や危機感を持つことが大事であると感じる。そういう意味では国...
人は生活をする上で安くて便利なものを選択したがる、世の中もテクノロジーの発展によりどんどん便利になってくる中で、人も合理的にその流れに則って流動していく。そもそもこのままの将来を辿った時にどんな問題が生じていくかの問題認識や危機感を持つことが大事であると感じる。そういう意味では国策としての対応が必要。一方で地域に貢献したい、地元を助けたい、活性化させていきたいと考える人も少なからずいる、そういった人達の地道な地域貢献が影響を及ぼし、地方分散型の地域経済モデルを復興させていくことに繋がる。 地域経済の課題とそれに対する解決策の事例が紹介されており、参考になった。 ・人口減少→消費力低下→地域経済の縮小→人工現象の悪循環 ・人口減少を止めるためには地域経済を土台として強くすること、流入ではなく流出をどう食い止めるかが重要。 ・地域の外に出てしまっている消費やお金の流れに注目する、どこが問題になっているか原因を特定する、分析がまず必要。 ・ローカルインベストメント
Posted by
『地元経済を創りなおす』 枝廣淳子著 1.著者 東京都市大学環境学部教授。 「執筆に3年を要する。実務につながることを目的に執筆。」 2.著書ポイント 地元経済を創りなおすとは? 『域際収支』を把握し、改善すること。 経済産業省/地域経済分析システム「REASAS」の使い方...
『地元経済を創りなおす』 枝廣淳子著 1.著者 東京都市大学環境学部教授。 「執筆に3年を要する。実務につながることを目的に執筆。」 2.著書ポイント 地元経済を創りなおすとは? 『域際収支』を把握し、改善すること。 経済産業省/地域経済分析システム「REASAS」の使い方、メリットの説明。 →「地域経済循環図」 =自治体の収支率がわかる。 https://resas.go.jp/#/13/13101 3.所感 実務活用度 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 自治体への理解⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ データ活用の未来⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 事業所情報と国勢調査を組み合わせることで、自治体の ①現状収支把握 ②収支改善への道筋(4.③.④) まで展開出来ること。 恐らく、地方銀行のビジネスマッチング(4.④)にも展開できうる要素があるのでは? 4.学べる内容 ①域際収支とは? 稼いだお金が可能な限り、地元の外への流出を減らし、地元に残すこと。 ②地元経済の現状 1)減り続けるJA 1960年 1.2万拠点→ 2016年 700拠点未満 2)1)の影響 ガソリンスタンドを始めJA主体の事業の撤退 ↓ 不便 ↓ 過疎化に拍車 3)減り続ける人口 2040年 3分の1の市町村→人口1万人未満 ③域際収支を改善するには? 【収入】 地元事業会社が生産していて、地元外で売れている製品の流通を増やすこと。 【所得分配】 地元事業会社の支払人件費のうち、地元居住者割合を高めること。※住民税そして【支出】の要素につながるため。 【支出】 地元居住者の生活費の拠出先が首都圏本社の小売とかではなく、地元事業会社が運営する店舗中心とすること。 ※地元会社がゆえ法人税が期待できるため。 【設備投資】 地元事業会社の設備投資の購買先ならびに外注先が地元事業会社である割合を高めること。 ④自治体が目指している「6次産業化」とは? 自治体地域に本社がある(納税義務のある)事業会社が 1)農、林、漁業の1次産業の材料を出荷。 2)製造、加工の2次産業が製品を生産。 3)流通の3次産業で販売。 出来ている状態、割合を高めること。 ※ 1次×2次×3次=6次 ⑤国内の具体的な取り組み 1)国内給食 給食の食材全体に対する地域生産の食材割合を高めること。 2006年時点26%→目標30% 2)北海道下川町 (参考ページ) https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/2020/01/post-92.html 地元消費で域外へ高い割合で外部流出しているのが電力。 そこで、林業が盛んなため、木材チップでのバイオマス発電所を建築。 自給率60%へ。 3)岐阜県郡上市石徹白村 (参考ページ) https://greenz.jp/2016/12/19/itoshiro/ やはり外部流通が高いのが電力。水量が豊富なため、水車発電を建築。 建築は補助金と住民の出資で実現。 ------------ ※国内再生エネルギー割合 2020年20% https://www.psinvestment.co.jp/small_talk/renewable-energy/ ------------ ⑥海外の取り組み イギリス トットネス地方 (参考ページ) https://www.amita-oshiete.jp/column/entry/015303.php 1)食費の10%は地元の小売店で。 2)承継土地を地元が安く譲り受け。 市場価格の7割で分譲または賃貸。 所得理由で住めない人向けに住める街づくり。 ほか。
Posted by
・人口3万人未満自治体954で総人口の8%、面積は48% ・年間10万人が東京に移住 ・どのように地域経済の好循環を作り出すか ・RESAS:地域経済循環マップ ・地消地産 ・小水力発電 ・合同会社あば村 ・学習する地域:客観的な報告書が共通基盤、継続新プロ・起業支援の場、アイデ...
・人口3万人未満自治体954で総人口の8%、面積は48% ・年間10万人が東京に移住 ・どのように地域経済の好循環を作り出すか ・RESAS:地域経済循環マップ ・地消地産 ・小水力発電 ・合同会社あば村 ・学習する地域:客観的な報告書が共通基盤、継続新プロ・起業支援の場、アイデア発射台
Posted by
地域の循環を見えるようにする、そのやり方があるというのが知れて良かった。何がどう変わるかがわかるのはとてもワクワクすることだなと思った
Posted by
2020.29 ・地域の消費実態を把握した上で、生産計画を作ることでギャップがなくなる。 ・トットネスが前進し続ける2つの前提と3つのポイントがある。 ・地方からの新たな物語が必要。
Posted by
生産年齢人口の減少が顕著な地方都市において、地域一体となって取り組むべきコンパクトシティの在り方のヒント。
Posted by
・人は「動いているところ」に惹きつけられる。 ・いったん地域に入ったお金を、どれだけ地域内で循環し、滞留させるかが大切。 ・あなたがお金を渡した相手が、どこでそのお金を使うかも重要。地域内乗数効果。 ・「地消地産」地域で消費しているものを地域で作る。 ・買い物の10%を、地元産に...
・人は「動いているところ」に惹きつけられる。 ・いったん地域に入ったお金を、どれだけ地域内で循環し、滞留させるかが大切。 ・あなたがお金を渡した相手が、どこでそのお金を使うかも重要。地域内乗数効果。 ・「地消地産」地域で消費しているものを地域で作る。 ・買い物の10%を、地元産に切り替える。 ・年1回の地元起業家フォーラムで、町民に売り込み、地元の皆が応援してくれるプロジェクトへと展開させる。
Posted by
●イギリスのトットネスという町では、地域経済を守るため、全国チェーンのコスタ・コーヒーの進出を阻止する反対運動が起こった、という。以前、鳥取にスタバがないということが話題になったが、日本では地域経済を守るという視点が抜けているがゆえに話題になったと見るべきなのかもしれない。
Posted by
本書では産業連関分析をキー概念として、地域経済における「漏れ」を如何になくしていくか、について理論と事例から説明している。 地域の人々による問題把握と課題設定、そして具体的な行動に移していくことが重要だ。そのためのノウハウは…自分たちで自分たちに合うようにしなければならないという...
本書では産業連関分析をキー概念として、地域経済における「漏れ」を如何になくしていくか、について理論と事例から説明している。 地域の人々による問題把握と課題設定、そして具体的な行動に移していくことが重要だ。そのためのノウハウは…自分たちで自分たちに合うようにしなければならないということが重要だ。
Posted by
タイトル通り、地元経済を活性化させるためのコンセプトや取り組みを紹介する一冊。地域からカネが流出することを「漏れバケツ」に例え、いかに漏れを少なくするのか考える、という発想は面白い。 最大の流出源がエネルギーというのは盲点だった。再生可能エネルギーでカネの流出を阻止できるなら、...
タイトル通り、地元経済を活性化させるためのコンセプトや取り組みを紹介する一冊。地域からカネが流出することを「漏れバケツ」に例え、いかに漏れを少なくするのか考える、という発想は面白い。 最大の流出源がエネルギーというのは盲点だった。再生可能エネルギーでカネの流出を阻止できるなら、それに如くは無いだろう。再生可能エネルギーが自給自足できて、電気自動車も導入できれば、地域の姿は一変するかもしれない。 カネの循環については、地元の信用金庫の活用なども紹介していて、地域に根ざした金融のあり方を考えるヒントになる。その点では、頼母子や無尽のような地域の相互扶助金融が脚光を浴びる時も来るかもしれない。 一方、地域にカネを蓄積するには本書冒頭でも触れている「地産外商」が欠かせないと思う。カネの流出を防ぐのは当然として、カネの流入を増やす必要もあるはず。その点についてはあまり触れられておらず、詳しく知りたかった。
Posted by
- 1
- 2