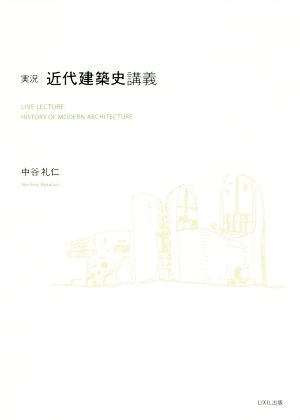実況 近代建築史講義 の商品レビュー
まったく入門書に相応しくない。学部1年生への講義なので、入門だろうと思うだろうし、語り口もだいたい入門みたいな様子なのだけれど、筆者によって大幅に解釈され編纂された、比較的イレギュラーな建築史なのである。と、いうことに気づくのに5年ほどかかった。やっと「一般的な」建築史の通史が頭...
まったく入門書に相応しくない。学部1年生への講義なので、入門だろうと思うだろうし、語り口もだいたい入門みたいな様子なのだけれど、筆者によって大幅に解釈され編纂された、比較的イレギュラーな建築史なのである。と、いうことに気づくのに5年ほどかかった。やっと「一般的な」建築史の通史が頭に描けるようになってはじめて、この講義がどういう意図をもって編纂されているのかがわかるのだ。やっとわたしにも通史がうっすらとイメージできるようになったのだな、と思った。 というわけで、この本は、「歴史とはなんたるか」という歴史そのものの定義を問いかけるようなものであって(だれかによっていとも簡単に書き換えられる、というアイロニー)、「一般的な」「入門書的な」「わかりやすい」「当たり前」の建築史書ではないと思う。 特に映画の引用が多いけれど、これが初学者を惑わせている。ブレードランナーに折衷主義的な建築が出てくるのではなく、折衷主義とはどんなものかという概念をブレードランナーで説明しようとしているからだ。いったいなぜこの映画を見せられているのかわからないことが往々にしてある。 この講義を通して、「歴史ってなんかおもしろそ〜」と思った記憶はあるが、やっぱりどう考えても「建築史を学んだぞ」とは思えなかった。ただ単にわたしに事前知識だとか学がなかっただけかもしれないけれど。そういうわけで、この本は初学者向けではないと思う。 装丁はとても好き
Posted by
近代とは何か、をルネサンス期から定義しなおした上で、日本の近現代建築を再構成した本。講義録なので、臨場感を感じながら、分かりやすく読める。ポストモダニズムの整理か明確であり、現代を再考するために読む歴史本としておすすめ。
Posted by
中谷先生の講義録。教科書というのとはちょっと違う。実況と銘打たれている通りのライブ版。でも志ん朝の落語の聞き書きのようなものとも違う。中谷さんの声は聞こえてくるようである、が、入念に手が入れられていることも同時に感じる。時間をかけて作られたストーリーなのだろう。 取り上げられる...
中谷先生の講義録。教科書というのとはちょっと違う。実況と銘打たれている通りのライブ版。でも志ん朝の落語の聞き書きのようなものとも違う。中谷さんの声は聞こえてくるようである、が、入念に手が入れられていることも同時に感じる。時間をかけて作られたストーリーなのだろう。 取り上げられる事例が少ないな、と思う。あれもこれもとスライドで物品を紹介したりはしないのだろう。その代わり、ブレードランナーやマレーなんかがスッと差し挟まれていて、ストーリーが輻輳する瞬間がある。 学生へのフリが滑るのも微笑ましい。そういう時、講師はとても寂しいものなので、学生はなんとか食い下がるようにして欲しい。
Posted by
(01) 本書の愉しさはどこからやってくるのか.もちろん,それ単体でも魅入られてしまうような図版,講義として語りかけられるようなライブ性(実況性),建築と相互引用される映画など大衆文化との連関といった,そのときどきの学生とひとりの教員とで工夫を積み重ねた講義(*02)という成果で...
(01) 本書の愉しさはどこからやってくるのか.もちろん,それ単体でも魅入られてしまうような図版,講義として語りかけられるようなライブ性(実況性),建築と相互引用される映画など大衆文化との連関といった,そのときどきの学生とひとりの教員とで工夫を積み重ねた講義(*02)という成果であるから,読んでいても愉しいのかもしれない. が,建築の近代性,あるいは近代の顕著な空間的表現である建築が,そもそも批評性(それは批評する権利とともにあるヒューマンな愉悦をともなう近代的な行為)の方へ空間的にも言説的にも開かれていた(*03)からこそ,建築を語ることの近代的な愉しさがあるようにも感じる. (02) 1章(1回)を読むのに1時間はかからないだろう.おそらく講義の実際は1.5時間であるだろうから,この差分の約0.5時間の間に現場で何が起こっていたのかを考えることは興味深い.映画の部分や動画の上映に充てられた時間でもあるだろうが,おそらく建築の初学生は,この約0.5時間のうちに,空間や時間のあり方に隠された秘儀と豊穣を味わっていることと思う.そこには実況の行間に打ち込まれた間(ま)の謎があるに違いない. (03) あるいは,自然や技術にオープンすぎる近代日本建築以降(近代+日本+建築+以降)が「クリティカル・グリーニズム」として紹介されているのにはどういった事情があるのだろう.世界観,地球感,宇宙観と建築との橋渡しを外構や造園が担っていることは本書にも示唆されている. バロック以前からのグロッタ,バークの崇高やイングランド庭園以前からの廃墟趣味,クリスタルパレス以前からの水晶がもつ象徴性,擬洋風を手掛けた棟梁たち以前からの変な木彫技法や石工技法など,近代が操作するために相対化した技術にはいまだ不可解な中世,古代,原始が潜み,その潜勢力もまた近代の糧であったのかもしれない. 霊魂の問題が本書の終盤に数多く漂い始めるが,オープンであるゆえに近代の視覚に納まりきらずに揺らいでいる存在というのは,近代の建築を揺さぶり続けているようにも思う.
Posted by
- 1