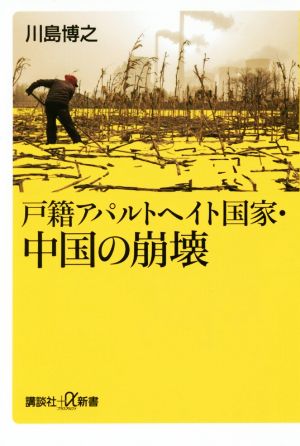戸籍アパルトヘイト国家・中国の崩壊 の商品レビュー
すげ〜な中国、あからさまに国民の中に差別を設定してるのかよ。しかしこれは小麦文化のせい、科挙のせい、は根拠がわからんなあ鵜呑みにしづらい。人口ピラミッドの例みたいにちゃんと数字を見せて欲しい。数多くの根拠薄めの著者の意見が多くて、それぞれそれなりに説得力はあるんだけど、読者として...
すげ〜な中国、あからさまに国民の中に差別を設定してるのかよ。しかしこれは小麦文化のせい、科挙のせい、は根拠がわからんなあ鵜呑みにしづらい。人口ピラミッドの例みたいにちゃんと数字を見せて欲しい。数多くの根拠薄めの著者の意見が多くて、それぞれそれなりに説得力はあるんだけど、読者としては捉え方に困るかな。これ読んでたら中国株とか買う気失せたんだけど、2017年の本なのだけど全く中国のテック企業について触れてないのでそこもなんとなくアンバランスな気もした。警部補ダイマジン読んでたら中国の農村戸籍と都市戸籍の事が出てきたので全く知らなかったので読んだみた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
タイトルに釣られた・・。(次作も既に買っちゃった) 著者が東大の准教授とのことだったので買ってしまった訳だが、まあ謂わゆる中国ディスの本であった。何かのイシューにシングルアンサーで答えるモノが多く、そんなに単純ではなかろう。ニコラス・クリストフが「新中国人」の中で、外国人が中国に来て、自分たちの国の問題は棚に上げて、中国ばかりを非難するジャーナリストと中国人に非難されるというような表現があったが、それを思い出した。 それでも所々面白い発言があったが、裏付けが乏しいので、著者の個人的な感想といったレベルを出ていない気がする。 確かに国策として、都市と農村の戸口を分けては来たが、実際に中国に住んでみた時の肌感覚では、都市部の人間も農村部の人間もあまりに当たり前のものとして捉え、都市部の人は平気で差別的な目で見るし、農村部の人等もそこに対して何かアクションを取るという様子も見えなかった。この辺りの意識の中に普通に階層の違いが存在してしまっていることが、今後もすぐに解消されていくとは到底思えない。。 P.67 中国の都市は、城壁で守られています。国という感じは、旧字(國)では、囲いの中に戈があることを示しています。囲いのなかで兵士が守りを固めている、という姿です。(中略)囲いの外にいる人々は、敵が攻めて来たときにまもられることはありません。自分で逃げる必要があります。そして、その多くは農民・・・支配者が農民を守ることはありませんでした。 P.111 近年の尖閣諸島や南シナ海への進出、そして歴史認識に関する中国政府の言動には、朱子学の影響を強く受けているとおもうところがあります。そう、現状認識が主観的なのです。そして一度、自分が正しいと思うと、周囲の状況を見てその考えを改めることはありません。負け犬の遠吠えではありませんが、かなりヒステリック。聞く耳など持ちません。 P.114 中国人が最も恐れるのは、呉三桂のような行動をする中国人です。中国は、内部に敵に内通する者が現れたときにほろびるからです。そして、そのような人物を漢奸(中国を裏切った中国人)と呼び、毛嫌いします。 P.172 一九世紀のイギリス外交をリードしたヘンリー・パーマストン子爵は、「イギリスには永遠の友人も永遠の敵もいない。あるのは『永遠の国益』だけだ」という趣旨の発言をしています。これは国家戦略の基本を述べてたモノで、不朽の真理だと思いますが、「永遠の国益」を判断することは、かなり難しい作業になります。 何が国益か、それを冷静に判断することは難しい。なぜなら多くの場合、国益は国民感情の沿線上にはありません。そのため未熟な政治家が国民感情に迎合し、激情のおもむくままに突っ走り、失敗するケースが後を絶たないのです。 P.180 なぜ中国の対外戦略は稚拙なのでしょうか?その最大の原因は、海外に関する情報の不足にあります。なぜ中国は、海外の情報を収集しないのでしょうか?それは、海外に興味がないからです。小さな島国に住みながら世界を制覇したイギリス人は、他国の文化に対し、大いに興味を持ちます。その好奇心が大英博物館を作り出しました。しかし中国には、大英博物館に相当するものはありません。
Posted by
長らく中国に駐在していた知人が、上海戸籍を持っている人と地方戸籍の人との差別が激しい、とは言っていたが、この事だったんだな。 私もあまり中国を好きではないが、この著者がハナから中国を見下しているスタンスが気になる。
Posted by
都市と農村で戸籍が違う、と言うのは聞いたことがあるが、大きな格差が存在しているのは知らなかったので、衝撃的だった。 中国は12億人では無く、4億人の国家と捉えるべき、という筆者の意見は、本書を読めばとても説得力のある考えだ。 また、コメか小麦のどちらかを主食にするかにより、国民性...
都市と農村で戸籍が違う、と言うのは聞いたことがあるが、大きな格差が存在しているのは知らなかったので、衝撃的だった。 中国は12億人では無く、4億人の国家と捉えるべき、という筆者の意見は、本書を読めばとても説得力のある考えだ。 また、コメか小麦のどちらかを主食にするかにより、国民性が変わるという話はとても面白くて、これも説得力があった。農業に精通し、かつ、中国現地に赴いて知見を得た筆者ならではの見方だと思う。 また第二次世界大戦後の中国共産党による為政や、現在の政権構造、中枢や幹部に関する記載も、見聞きすることが無かったので、新鮮で面白かった。 しかし、筆者のこれまでやこれからの中国の見方は厳しいと思う。 ある程度豊かになり、成長が鈍化した国の政治家・官僚の腐敗や対外膨張政策、貧困層の不満増大などは全世界共通の問題であり、中国に限った話では無い。 また、時に歴史に学ばない行動もしてしまうのも同様。どのような政治体制でも、大勢の民衆が支持すれば、間違ったことでも実行してしまう、これは民族国家の弱点だ。 翻って、国民が多すぎて団結が困難、しかし、辺境地域を除いては分離独立の気運が無い中国は、為政者にとってコントロールしやすく、これからも大きな影響力を行使する国として存在し続けると思う。 あと、帯に「9億人の農民奴隷は2020年に蜂起する」とあるが、2020年と断定する根拠は読み取れなかった。恐らく、筆者では無く出版社による誇張だと思いますが。
Posted by
小関アパルトヘイト国家中国、日本多くの都市戸籍と9億の農民戸籍の区分 中国奥地のような風景、9多くの農民から搾取する、4多くの都市住民。 中国人民解放軍が世界一弱い理由、良い人間は軍人にならない、漢奸を最も恐れる理由、明の滅亡、満洲族の勃興、中国は内部に的に内通するものが現れた...
小関アパルトヘイト国家中国、日本多くの都市戸籍と9億の農民戸籍の区分 中国奥地のような風景、9多くの農民から搾取する、4多くの都市住民。 中国人民解放軍が世界一弱い理由、良い人間は軍人にならない、漢奸を最も恐れる理由、明の滅亡、満洲族の勃興、中国は内部に的に内通するものが現れたときに滅びる。 共産党が都市住民だけ恐れるわけ、農民の犠牲で達成した経済成長、年の4億が農民工さんを食を奴隷に、次の天安門事件が起こらない理由、 アメリカへの挑戦が早めた崩壊、空母の建造で崩壊を早めたソ連、アメリカはその覇権のため、第2のものを叩く。戦後のソ連、日本、続くのは中国か?
Posted by
中国人が中国人を見下す。この表現を、中国人に言うと、頷きます。正確にいうと、都市戸籍所有者が、農村戸籍の者を見下すということは、中国では常識です。差別と言っていいかもしれません。 よって、農村戸籍の者は、否が応でも、都市戸籍を持ちたいと思う。 中国で、大学入学試験が激烈である...
中国人が中国人を見下す。この表現を、中国人に言うと、頷きます。正確にいうと、都市戸籍所有者が、農村戸籍の者を見下すということは、中国では常識です。差別と言っていいかもしれません。 よって、農村戸籍の者は、否が応でも、都市戸籍を持ちたいと思う。 中国で、大学入学試験が激烈である一つの面は、 大都市にある大学に入学すれば、農村戸籍から、 都市戸籍に切り替えることが可能だからです。 中国は近年目覚ましい、発展を遂げました。 GDPは日本のGDPの2倍以上になっています。 11年に抜かれて、僅か数年で倍の経済規模になっています。 その発展の中で、多くの人民の生活は以前と比べて格段によくなりました。一方、その発展の恩恵を得られていない層も、まだいます。 格差社会は、日本なんかの比ではありません。 その格差社会の中で、絶望を感じている層もいます。 この数十年で中国が失ったものは、大きいと思います。 一党独裁による権力の集中は、ある面では成功しましたが(物事をスピーディーに進める上で)、 取り残された層もいます。中国は、これからも、パクスチャイナの道を突き進んでいきます。 それは、国内の問題が非常に多く、拡大するしか、その問題を覆い隠すことができないからです。 中国の夢は、これからも、犠牲を伴いながら、果てしなく続くでしょう。
Posted by
- 1