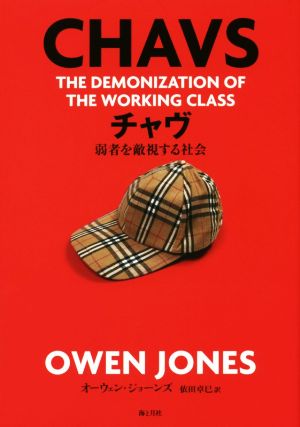チャヴ の商品レビュー
イギリスの労働者階級が敬意を払われなくなったことについて書いた本。「チャヴ」とは、白人労働者階級に対する蔑称めいたもの。 いわゆる英国病の一側面として労使紛争の多発があり、サッチャリズムは労働組合活動を制限する方向に舵を切った。国営企業の民営化などで失業者が増えたこともあり、労...
イギリスの労働者階級が敬意を払われなくなったことについて書いた本。「チャヴ」とは、白人労働者階級に対する蔑称めいたもの。 いわゆる英国病の一側面として労使紛争の多発があり、サッチャリズムは労働組合活動を制限する方向に舵を切った。国営企業の民営化などで失業者が増えたこともあり、労組の力は衰えた。 国際競争力のない産業に対する政府補助を減らして社会保障も削減したので、労働者階級そのものが弱体化することとなった。 労働者階級を弱体化するのはサッチャーの意図的なものであり(保守党政権は労組に苦しめられていた)、本書の表現で言えば「上からの階級闘争」である。 したがって、本来の意味での(下からの)階級闘争によって対抗するということもあり得たのだろうが、それを抑制する機能を果たしているのが「チャヴ」なのだろう。 ・ズルして社会保障をもらっているやつがいる。 ・仕事もしないでブラブラして子供ばっかりつくっている。 ・頑張れば中流階級になれることもあるのに、怠けて不平ばかり言っている。 のような非難をし、そのレッテルとして「チャブ」という語がある。労働者階級全体のイメージを貶め、また労働者階級の中で批判し合う風潮を作ることにも資するレッテルだ。 このあたり、本書ではそんなことは書いていないが、「大英帝国お得意の分割統治策を自国民にも使うのか」と私は思った。 そうしたことに加担しているのは保守党支持者だけでなく、マスメディア(労働者階級の出身者は少ない)もだし、本書が強く唱えているのは「ニューレイバー」だ。 本来なら労働者階級の代表であるはずの労働党が、トニー・ブレアに代表される「ニューレイバー」達が主流として政権奪還したものの、労働者階級への非難を食い止めることなく黙認したような格好になっているという。 労働党は「労働者が支持するのはわれら労働党」という意識が少なからずあるようだが、見切りをつける人々もいて極右的な政党が支持を集める原因になっているというのが本書の見立てだ。 大雑把にこんな感じで受け止めたが、これをイギリスだけの話ととらえるのは難しい。 新自由主義と一般化してよいのかはわからないが、少なくとも日本についていえば思い当たることはたくさんある。 たとえば本書の中の次の一節は固有名詞を隠したら「日本のことか?」と思えてしまう。 政府が後援する富裕層の蓄財はどのように正当化されたのか。サッチャー派は「トリクルダウン」について語った。頂上で増えた富があたかも水のようにあふれて、ゆくゆくは最下層まで滴るのだと。だが、そういうことは明らかに起きなかった。そこでサッチャリズムは、失敗した経済政策の犠牲者たちを攻撃しにかかった。彼らが苦しんでいるとしたら、それは自己責任である、と。(83ページ)
Posted by
第52回ビブリオバトルinいこまテーマ「ワル」で紹介された本です。チャンプ本。 2017.11.26
Posted by
チャヴとは、イギリスでもっぱら労働者階級(特に若年層)を侮辱する言葉。 本書はそのチャブがなぜ生まれたのか、イギリスでどのようなかたちで扱われているのかを政治、経済、文化等の各視点からを考察し、イギリスの闇を深くえぐった内容となっている。 個人的にはBBCのコメディ「リトル・...
チャヴとは、イギリスでもっぱら労働者階級(特に若年層)を侮辱する言葉。 本書はそのチャブがなぜ生まれたのか、イギリスでどのようなかたちで扱われているのかを政治、経済、文化等の各視点からを考察し、イギリスの闇を深くえぐった内容となっている。 個人的にはBBCのコメディ「リトル・ブリテン」に典型的なチャブが登場する(本書でも言及あり)のでイメージがつかめたが、これは他人事ではなく、日本においてもあてはまる内容ではないかと強く感じた次第。 本書ではチャブが生まれた根本原因として、サッチャー首相時代の経済政策の大失敗を挙げているが、いかに政治の失敗が国を危うくするかがあらためて良く分かった。日本も既にイギリスと同じ道をたどり始めているのかも・・・。全ての為政者必読の本。
Posted by
所得の高い層に政治とマスコミが占領されると、当の貧困層までが福祉給付の削減に賛成するように世論誘導されてしまう点が、なんというか権力者は邪悪でグロテスクだと思った。日本にも他人事ではない。
Posted by
水道再公営化の本を読んでいたら、著者の名前が出てきて、本書のことは知っていたので、読んで見る。 資本主義の限界に達したイギリスで、社会が壊れ始めているをの見ると、とても暗澹たる気持ちになるが、目をそむけてはならない。
Posted by
2011年に出版され世界的ベストセラーになった本書。1970年代後半のサッチャー政権による労働者の権利を奪い去る法律改正、さらには徹底した個人主義・能力主義によって概念としての階級が消し去られ、保守党だけでなくニューレイバーを掲げる労働党(トニー・ブレア以降)によっても現実の階級...
2011年に出版され世界的ベストセラーになった本書。1970年代後半のサッチャー政権による労働者の権利を奪い去る法律改正、さらには徹底した個人主義・能力主義によって概念としての階級が消し去られ、保守党だけでなくニューレイバーを掲げる労働党(トニー・ブレア以降)によっても現実の階級制度が強化されていくという、戦後のイギリス史にもなっている。 階級は存在しないという階級を否定する階級政治ではそもそも中流階級以上の議員によって進められ、全ての人が中流を目指すべきで社会の底辺にいるのは自業自得だとするという徹底した個人主義に基づく。個人の人生を決めるのはその人の態度であり、物理的な貧困と人生のチャンスとは関係ないとする自己責任論に転嫁していくことで社会保障費を削減していくが、それによってより階級社会が強化されていく。政府やメディアは補助金を受けた野蛮人の群れが門のすぐ外で暴れているという中流階級の不安感を積極的にあおり続け、イギリス政治の中心にチャヴの作り話を置き、国中のコミュニティに無責任、怠惰、暴力的で性的に堕落したどうしようもない連中がはびこっているという考えを浸透させていく。つまり、かつての誇り高き労働者階級はイギリスの中流以上に向けた政治の中で犠牲となり、忘れ去られ、お荷物の烙印を押され、公然と差別の対象となっていった。 階級政治はやがて移民問題へのすり替えとなるアイデンティティ政治へ変化をしていくわけだが、2011年には世界的なオキュパイ(占拠)運動が起こり、労働者階級の連帯が生まれるなど微かな希望を見せる。格差の問題は世界的な問題であることを改めて理解した。世界的な流れを理解することで、日本で起きている事にも当たりたい。
Posted by
イギリスには「チャブ」と呼ばれる,公営住宅に住み,十代で子どもを作り,働かずに生活保護を受ける粗暴な人たち,という階層があるらしい。 それを,本書では権力者側が意図的に作ったイメージにすぎないことを説く。 イギリスのことなのに,日本でも思い当たるフシがたくさんあって,怖ろしくなる...
イギリスには「チャブ」と呼ばれる,公営住宅に住み,十代で子どもを作り,働かずに生活保護を受ける粗暴な人たち,という階層があるらしい。 それを,本書では権力者側が意図的に作ったイメージにすぎないことを説く。 イギリスのことなのに,日本でも思い当たるフシがたくさんあって,怖ろしくなる。
Posted by
CHAV(Council Housed And Violent)という言葉を聞いたことがあるだろうか?「公営住宅に住んで暴力的」の頭文字が使われていて、チャヴと読む。 本書は、現代のイギリス社会では、貧困層があたかも階級制度時代のように最下層に位置しており、不公平で理不尽なほど虐...
CHAV(Council Housed And Violent)という言葉を聞いたことがあるだろうか?「公営住宅に住んで暴力的」の頭文字が使われていて、チャヴと読む。 本書は、現代のイギリス社会では、貧困層があたかも階級制度時代のように最下層に位置しており、不公平で理不尽なほど虐げられ、貧困から抜け出すことが限りなく不可能に近い環境に置かれている現状を描き出したノンフィクションだ。 しかも、メディアや政治家は彼らを”働く意欲もない自堕落で、社会保障制度にたかる寄生中”のごとく扱っている。貧困となっているのは自己責任であり、働く気のないお前が悪いという風潮だ。こうした人たちをチャヴといっている。一般的にジョークのネタにも使われ、使っている人は、悪いことを言っている意識すらない。だが、冷静に考えると、とても差別的な言葉だ。 本書を読むと、そうさせているのはイギリス政府が施行してきた政策によるものだということがわかる。サッチャー政権から始まった政策により、労働組合は弱体化し、労働者たちが虐げられ続けてきたことや、社会保障を徹底的に削減してきた歴史をみせてくれる。 私は日ごろからイギリスでどんなことが起こっているのかを気にしている。それは日本と同様島国であるし、人口減少が明確になっている日本は移民についても考えていかなければならない点等から。 我が国の実態は、どうだろうか?自己責任という名のもと、国外にいる日本国民を切り捨てたり、生活保護を受けている人たちの実態も把握しないまま、受給者の人数だけで物事を考えていたりしていないか?外国人が日本で暮らしている実態も理解せずに、ひとくくりにレッテルを張り付けていないか? 社会を見る、視座を問われた一冊となった。
Posted by
読みながら、これはイギリス各地で貧困層を中心とする暴動がいつ起こってもおかしくないのではないかと思っていたが、富と権力を牛耳る少数の集団は、そんな貧困層の格差憎悪を巧妙に仕組まれたスケープゴートに向けさせることで、自分たちには向けさせないように企むのだろうという絶望感も感じた。 ...
読みながら、これはイギリス各地で貧困層を中心とする暴動がいつ起こってもおかしくないのではないかと思っていたが、富と権力を牛耳る少数の集団は、そんな貧困層の格差憎悪を巧妙に仕組まれたスケープゴートに向けさせることで、自分たちには向けさせないように企むのだろうという絶望感も感じた。 しかし、イギリス社会もこのままで推移するとは考えられない。コップに溜まった水は、いつか表面張力を越えて溢れ出す。それはそう遠い未来のことではなかろう。 日本もジニ係数は決して低くはない。今のように、自民党を中心とする政権が権力をほしいままにし、一部の富裕層を優遇するような政権運営をしていくならば、そう遠くない未来にイギリスと同様のことが発生することであろう。
Posted by
「そろそろ左派は経済を語ろう」で紹介されていた。 出版は2011年で少し前になるが、サッチャー政権以降、英国で労働者階級が没落し、貧富の差が拡大した結果、白人労働者階級が社会全体から(同じ労働者階級からも)差別されるようになる様子が克明に描かれる。 炭坑労働者から発生した労働...
「そろそろ左派は経済を語ろう」で紹介されていた。 出版は2011年で少し前になるが、サッチャー政権以降、英国で労働者階級が没落し、貧富の差が拡大した結果、白人労働者階級が社会全体から(同じ労働者階級からも)差別されるようになる様子が克明に描かれる。 炭坑労働者から発生した労働党が、労働者を疎外するようになるとは。 それにしても英国の政治家、マスコミ、コメンテーターは言いたい放題だ。問題箇所だけ切り取っているということはあるのだろうが、差別意識を隠そうともしない。
Posted by