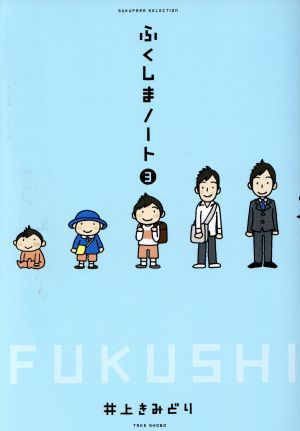ふくしまノート コミックエッセイ(3) の商品レビュー
学習マンガリストから。自分の不勉強を嘆くしかないんだけど、今更ながら、福島の人にとっては、今回のコロナ渦って既視感満載だったんだろうな、と。ここ数年、全国規模で起こった諸々と、驚くほど似た状況が綴られている。極端に限定的な公助に対し、多くを自助に押し付ける体質とか、根本的な部分は...
学習マンガリストから。自分の不勉強を嘆くしかないんだけど、今更ながら、福島の人にとっては、今回のコロナ渦って既視感満載だったんだろうな、と。ここ数年、全国規模で起こった諸々と、驚くほど似た状況が綴られている。極端に限定的な公助に対し、多くを自助に押し付ける体質とか、根本的な部分は変わらないんだな、と。当事者であれば常識としての放射線知識も、自身には圧倒的に不足している事実も明らかになり、勉強の必要性を再確認。どんな問題に対しても、傍観者でいてはいけない。改めて、自戒の念と共に。
Posted by
『温故知新3.11 #3 コミック③』 ー井上きみどり さん『ふくしまノート3』ー 内容は、全7話+番外編+その他のふくしまノート①〜④。前作からさらに2年、東日本大震災から6年経過し、当時幼かった子どもたちが語り始め、大人はとうに諦めてしまった人、懸命に動き続...
『温故知新3.11 #3 コミック③』 ー井上きみどり さん『ふくしまノート3』ー 内容は、全7話+番外編+その他のふくしまノート①〜④。前作からさらに2年、東日本大震災から6年経過し、当時幼かった子どもたちが語り始め、大人はとうに諦めてしまった人、懸命に動き続けている人の姿がありました。 第2巻から2年間というよりは、6年間の取材の積み重ねによる「福島の本音」が詰まっている感じです。 『ふくしまノート』が、紙の本として「次世代に描き残す」という役目を担うのは本作が最後とのことですが、竹書房のサイト『すくパラ倶楽部』のエッセイコーナーで今も連載が続いている! このことに大きな意味を感じます。もっと広く知らしめる必要性を実感しました。 そして「福島の今」を伝え続けようと、自分の得意な形で継続している井上きみどりさん。何よりも、「福島の人たちから言葉を預かっている」「外に発信しなくなったら内側だけの問題になってしまう」と語る井上さんに敬意を表しながら、その強い想いに心動かされました。 改めて思いました。忘れてはいけない、過去のことにしてはいけないと。深刻さ故に立ち入りづらい福島の人々のことを、自然に気付かせてくれました。高校生など若者が動き始める、その先の未来を心から信じたいと思います。
Posted by
借りたもの。 最終巻。 結局、全てが手探りで解決はなく、正しいことなど何もない。 徐々に生活基盤が定着してきた福島の人々。しかし、それを“復興”というかはわからない。 県外避難をしてそこに生活基盤を移した人、福島と新しい環境を行き来する人、今も福島に居続ける人――三者三様の価値...
借りたもの。 最終巻。 結局、全てが手探りで解決はなく、正しいことなど何もない。 徐々に生活基盤が定着してきた福島の人々。しかし、それを“復興”というかはわからない。 県外避難をしてそこに生活基盤を移した人、福島と新しい環境を行き来する人、今も福島に居続ける人――三者三様の価値や歩む道が紹介されていた。 それをコミュニティの瓦解というのだろうか……? 被災した上に原発事故でそれまでの生活が破綻した町の人々が、形式じみたお役所仕事としか思えない対応に、不信感を募らせているのもわかるし、個人の能力を超えた災害にあったからこそ行政の力が必要としているというのも理解できる。…が、現実の行政の能力など、限界がある。 被害が大きすぎる事もあってか、地方のお金の無さも原因か。 住んでいる地域毎にケース・バイ・ケースの対応ができないため出てくる不公平があった。 それを書類上で一括に片づけてしまうとしか思えない対応への不満が垣間見える。 原発事故で、即健康被害は出なかった。しかし、掲載されている事例で父親が癌になった人が居るようだが、生活習慣が原因だったのか分からない事で不安を抱えている――という事例まで。 被災した当事者たちの声を、井上きみどり氏はよく取材されたと思う。 できれば、行政文書の実態の方と照らし合わせて欲しかった……(批判だけ鵜呑みにしてしまっているような気がするから。行政に携わる人の時間をとるのは難しいし、そういう事は本来、ジャーナリストがすべきことなんだろうけれど。) 竜田一人『いちえふ 福島第一原子力発電所労働記』( https://booklog.jp/item/1/4063883183 )とも併読。
Posted by
- 1