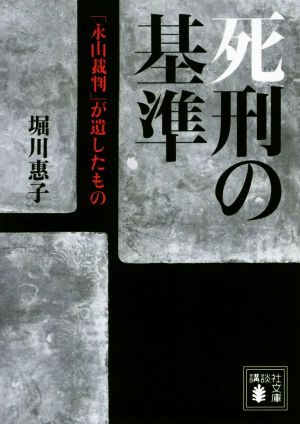死刑の基準 の商品レビュー
永山則夫、初めて知った。 家庭環境が劣悪だと、犯行に及ぶ可能性は高くなる。無知でいるしかなかった。お金もないし、家族も敵だ。怒りが社会に向いても仕方ない、永山が悪いのではなくそれを救えなかった社会が悪い、そうは思うが遺族のことを考えると簡単に頷けない
Posted by
連続射殺間・永山則夫の裁判から、死刑の基準とは何かを探るノンフィクション。永山裁判の記録を読み込み、死刑とした地裁判決、それを覆して無期懲役とした高裁判決、さらにそれを差し戻した最高裁判決、それぞれで永山は何を訴え、裁判官は何を考え、そして世論はどう動いたか、綿密に検証した。特に...
連続射殺間・永山則夫の裁判から、死刑の基準とは何かを探るノンフィクション。永山裁判の記録を読み込み、死刑とした地裁判決、それを覆して無期懲役とした高裁判決、さらにそれを差し戻した最高裁判決、それぞれで永山は何を訴え、裁判官は何を考え、そして世論はどう動いたか、綿密に検証した。特に、最初は社会を弾劾していた永山が、伴侶のミミさんを得て被害者の慰藉のために生きたいと願う姿は感動的だ。それを受けて、究極の刑罰である死刑には、裁判官の誰もが一致する基準が必要との考えから無期懲役とした画期的な高裁の船田判決が生まれた。しかし、世の懲罰感情は根強く、最終的に死刑となる。その判決文にあった基準が「永山基準」として独り歩きを始めた。その経緯は、私たちに、死刑は本当に必要かを問いかける。
Posted by
永山則夫をこの本で初めて知った。罪は罪だが、育った環境とネグレクト、家庭内暴力…彼を救えなかった社会にも責任があると感じた。無知の涙を読まねばならない、そう思った。
Posted by
恥ずかしながら、自分は永山則夫について、「貧困育ちの少年が4人を殺害した。獄中て作家になった」くらいの情報しか知らなかった。 永山則夫はちょうど自分の父母の時代で、母は彼より年上だが、東北の兄弟の多い家庭の下から二番目で、同じように集団就職で15で東京にきている。これまた同じよ...
恥ずかしながら、自分は永山則夫について、「貧困育ちの少年が4人を殺害した。獄中て作家になった」くらいの情報しか知らなかった。 永山則夫はちょうど自分の父母の時代で、母は彼より年上だが、東北の兄弟の多い家庭の下から二番目で、同じように集団就職で15で東京にきている。これまた同じように先に東京にいた兄を頼り生活し…母の上京物語は、オリンピックやらなにやら、楽しい話が多い。 事件を起こすまで、彼の人生は誰にも知られず誰にも気にかけられず、透明人間のようだった。 捕まってはじめて、彼はやっと人間になる。 獄中で結婚した和美さんという人がいることをはじめて知った。献身的な彼女との交流はあまりにも静謐で、ほんとうの人生を彼はやっと生きられたのだと思う。 最後の判決をむごいということはいけないのかもしれないけれど、意地を張らずに最後の日々を彼女と過ごせばよかったのに、と思わずにはいられない。
Posted by
著者の堀川恵子氏は、広島テレビの報道記者等を経て、独立したノンフィクション作家。本作品は、2009年に発表され、講談社ノンフィクション賞を受賞し、2016年に文庫化された。また、2015年発表の『原爆供養塔』は大宅壮一ノンフィクション賞を受賞している。 本作品で取り上げられた永山...
著者の堀川恵子氏は、広島テレビの報道記者等を経て、独立したノンフィクション作家。本作品は、2009年に発表され、講談社ノンフィクション賞を受賞し、2016年に文庫化された。また、2015年発表の『原爆供養塔』は大宅壮一ノンフィクション賞を受賞している。 本作品で取り上げられた永山則夫連続射殺事件とは、1968年に東京都・京都市・函館市・名古屋市で発生した、拳銃による4件の連続殺人事件で、犯行当時19歳だった永山則夫は、最終的に死刑判決を受け、1997年に死刑が執行されたが、この事件・裁判は様々な点で異例のものであった。 永山は、裁判が始まる直前から独房で大学ノートに自分の思いを綴り始め、それを基に編集された『無知の涙』はベストセラーとなり、1970年代前半は、その本を持ち歩くことが「反権力」を通す若者にとってある種のファッションだったのだともいう。 裁判については、第一審は「死刑」であったが、その後、『無知の涙』を読んだ女性(和美さん)と獄中結婚することにより、永山の人生・裁判への姿勢が変化し、控訴審では「無期懲役」となる。控訴審を担当した裁判官は、後に和美さんに「私たちはね、あなたに、あなたと永山さんに、1%の可能性を見たんです。それに賭けて、あの判決を下したんです」と語ったという。しかし、検察は上告し、最高裁は控訴審の無期懲役を軽すぎるとして破棄する(こうした事例は永山事件が初めてだった)。その判決は、今日に至るまで司法界の歴史に残る判決となっており、そこで示された「犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状」という9つの要素が、その後、「死刑の基準」と捉えられてゆき、いわゆる「永山基準」は死刑判決に際してたびたび引用されることになるのである。 本書では、永山の生い立ちから事件まで、一審、控訴審、最高裁の経過と結果を、和美さん、一連の裁判に関わった裁判官らへの取材を含めて、克明に辿っている。 著者は、なぜ今「永山基準」を取り上げたのかについて、2008年の山口県光市母子殺害事件の裁判に関する過熱報道に違和感があったことを挙げ、更に、2009年に「裁判員裁判」が開始されたことにより、自分たち一般市民が刑事裁判にどのように関わっていくべきなのか、今まさに問われているのだと語っているが、「人が人を裁くとはいかなることか」を改めて考えさせる一冊であった。 最高裁判決の際に調査官を務めた稲田氏が、その後自らの意思で刑事裁判官を辞めた理由を、「一つには刑事事件の審理が怖くなったからです」と語り、「逆に自分が裁かれているような気持ちになった・・・真実を知っているのは、目の前にいる被告人だけであり、裁判官である自分が読み上げている判決が正しいのか、間違っているのか、逆に被告人に裁かれているような気持ちになった」ということは、非常に重たいものである。。。 (2017年4月了)
Posted by
「死刑の基準」いわゆる「永山基準」の虚構を暴いた衝撃作 「永山基準」として名を留める、十九歳の連続射殺犯・永山則夫。本書は、彼が遺した一万五千通に上る膨大な書簡と、獄中結婚した妻や元裁判官への取材から、永山基準の虚構を暴く。講談社ノンフィクション賞受賞作。
Posted by
- 1