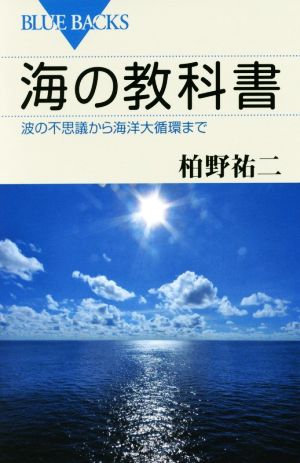海の教科書 の商品レビュー
学問的な内容。すなわち専門的すぎる。 例えば海洋探査船で用いられる測定器具を詳細に紹介されても、一般読者には響かない。 読了35分
Posted by
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057411
Posted by
関連講義@夢ナビ: 海洋の息吹「南極深層水」を追え https://douga.yumenavi.info/Lecture/PublishDetail/2021000960
Posted by
●海の教科書というだけあって、波や海流、海水の性質、エルニーニョ現象など豊富なテーマを解説している。
Posted by
地球環境と海洋研究を専門とする著者による海の話。海について、全般的によくまとまっておりわかりやすい。勉強になった。 「日本は、6852もの島からなっており、これだけの多くの島からなる国は、世界では他にインドネシア、フィリピン以外にはありません」p25 「(海洋地球研究船 みらい...
地球環境と海洋研究を専門とする著者による海の話。海について、全般的によくまとまっておりわかりやすい。勉強になった。 「日本は、6852もの島からなっており、これだけの多くの島からなる国は、世界では他にインドネシア、フィリピン以外にはありません」p25 「(海洋地球研究船 みらい)前身は原子力船「むつ」です。「みらい」は、「むつ」の船体の後部と原子炉を取り除き、新造された後部と「むつ」の前部とを接合して作られました」p58 「(4℃で密度最大)湖の淡水が冷たい空気で冷やされると、4℃に冷えるまでは湖面で冷やされた水は重くなって、対流により沈んで底のほうにたまります。さらに4℃より冷えると、冷やされた水の密度は4℃の密度より小さいため底に沈まずに、湖面で結氷します。海水の場合は、密度が最大になる温度も海水が凍る温度も、塩分の増加に伴い下がる傾向があります。通常の塩分値では、氷ができる温度で密度が最大になります。海水は冷やされるとどんどん重くなり、その密度に釣り合う海水が存在する深さまで沈みます。このため、海を冷やして氷を作るには海面の水だけを冷やせばよいのではなく、海面よりもっと下の水まで結氷温度に冷やさなければなりません。つまり、海は淡水の湖に比べて大変凍りにくいのです」p92 「(黒潮の左右で海水温が違う)密度が小さいということは同じ質量であれば体積が大きいことから、黒潮をはさんで南側では北側に比べ海が膨らんでいる、すなわち海面高度が高くなっています。実際、黒潮を越えて南に行くと、海面高度が約1m高くなっています。この海面の高さの違いは人工衛星の海面高度観測で検出できることから、海面高度の変化を観測すれば黒潮の流れている位置やその強さをモニタリングできます」p128 「(潮汐)起潮力は地球外天体(月、太陽)の引力と地球が月(太陽)との共通重心の周りを回転していることによる遠心力(地球と月との共通重心は、地球の内部)」p226 「太陽の起潮力は月の0.46倍で平均25cm」p231 「最大の潮汐周期は、主太陰半日周潮(M2)」p232 「満潮と干潮の潮位が1日で異なっている日潮不等は、月の公転面と地球の赤道面が一致していないために起こる」p233 「日本で最も潮差が大きいのは有明海の奥で、最大6mもあります。世界ではカナダのファンディ湾で15mにもなる(湾の固有振動とM2との共鳴が原因)」p243 「(エルニーニョ)平均0.5℃以上高い状態が6ヶ月以上続いた場合」p258 「エルニーニョ現象が起こると日本では冬は暖冬、夏は冷夏となる傾向があります」p272 「南極周極流は世界最強の海流で、その流量は黒潮の3倍近い」p309 「(海氷と氷山)よく間違われるのですが、南極で見られる氷山は海が凍ってできたのではなく、大陸の氷床が海にはみ出して棚氷となり、それがちぎれて海に流れ出たものです」p311 「南極周辺では海氷が作られますが、海氷ができる際に塩分のすべてを氷の中に取り込むことはできません。海水は凍る際、2~3割程度の塩分を氷に取り込みますが、残りの塩分は海に排出されるのです。この排出された塩分により濃縮された密度の大きい海水は、海底に沈み込んでいきます」p311 「長期的な観測の結果によれば、南極全体では海氷の面積はわずかながら増加傾向となっています」p315
Posted by
☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21399882
Posted by
波や潮汐などのごく身近な現象から、海流、海洋大循環(海の水が大きなサイクルで地球を一周すること)、エルニーニョ現象などの地球の気候変動に与える現象に至るまで、海に関する現象について出来る限り平易に解説した本です。 それらの現象のメカニズムを理解するために必要な海水の物性(温度、密...
波や潮汐などのごく身近な現象から、海流、海洋大循環(海の水が大きなサイクルで地球を一周すること)、エルニーニョ現象などの地球の気候変動に与える現象に至るまで、海に関する現象について出来る限り平易に解説した本です。 それらの現象のメカニズムを理解するために必要な海水の物性(温度、密度、PH、比熱)の説明や、物理法則の一部(コリオリの力、波動など)の説明も適度に盛り込まれ、まさに教科書という印象でした。 物理法則の部分の理解が辛いならば、そこは読み飛ばしても、それ以外の現象の紹介だけでも十分な情報量です。一言で「海」と言っても、こんなにも複雑な構造や挙動をしているのかと再発見できる一冊です。
Posted by
161008 中央図書館 海の化学、動態、波、津波、氷、渦、気象、気候など、なんでも書いてあるように見える。観測に手間のかかる対象であるだけに、解明されるべき課題が山積であると。海流についての易しい記述がありがたい。
Posted by
海洋物理学への入門にうってつけの本。 あとがきもなく唐突に終わるのも,いかにも「教科書」的で悪くない。 地震国かつ海洋大国なのに地学の位置付けが低く,その地学さえ地質や天文メインで,海洋について無知な国。そんな日本だけど,海を舞台にしたフィクションとか人気だし,Nスペなんかで海洋...
海洋物理学への入門にうってつけの本。 あとがきもなく唐突に終わるのも,いかにも「教科書」的で悪くない。 地震国かつ海洋大国なのに地学の位置付けが低く,その地学さえ地質や天文メインで,海洋について無知な国。そんな日本だけど,海を舞台にしたフィクションとか人気だし,Nスペなんかで海洋生物について特集したりするし,みんな海の科学にもちゃんと興味はあるんだと思う。 だからこそ,初歩を体系的にやっとくのが良いっていうのはホントそう。 広く読まれるべき本です。
Posted by
ほぅーと海の世界を知らない当方にとっては興味深い蘊蓄話ばかり。自然ってやはり人知の及ばない深さを持ってるし、それに挑む科学もまた人類だけに与えられた特権的能力の結実だなと素直に感心。 一つ難点を挙げるとすると、読み物を目指した割には若干長い。まぁブルーバックスだから当然レベルのも...
ほぅーと海の世界を知らない当方にとっては興味深い蘊蓄話ばかり。自然ってやはり人知の及ばない深さを持ってるし、それに挑む科学もまた人類だけに与えられた特権的能力の結実だなと素直に感心。 一つ難点を挙げるとすると、読み物を目指した割には若干長い。まぁブルーバックスだから当然レベルのものかもしれないですが、もう少しだけ文章を推敲しても良かったかも。偉そうですいません。
Posted by
- 1
- 2