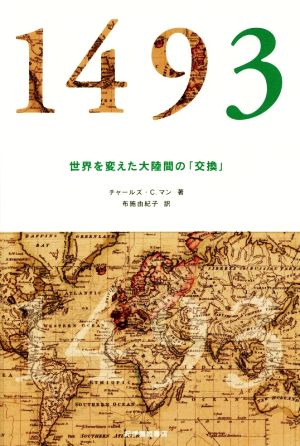1493 世界を変えた大陸間の「交換」 の商品レビュー
奴隷にしたインディアンも白人もマラリアでバタバタ死んだ、奴隷買入れよりはロンドンの失業者を雇入れするほうが安くついたが、幸か不幸か、アフリカ黒人はマラリアに耐性があった。彼らが合衆国を作った。タバコと砂糖製造で繁栄⑨可哀想なアメリカインディアンや黒人奴隷といったイメージを裏切って...
奴隷にしたインディアンも白人もマラリアでバタバタ死んだ、奴隷買入れよりはロンドンの失業者を雇入れするほうが安くついたが、幸か不幸か、アフリカ黒人はマラリアに耐性があった。彼らが合衆国を作った。タバコと砂糖製造で繁栄⑨可哀想なアメリカインディアンや黒人奴隷といったイメージを裏切って、両者が協力して合衆国と戦いプランテーション破壊し熱病蔓延を待つ戦術で勝利した例/アマゾン流域で、奴隷の子孫の共同体との地権争いは今も続く。二百年続き独自の文化を形成した村落は戸籍がなく盗電しかなかったが今や法的地位と電話を持った
Posted by
植物,病原菌などの情報はなるほどと思いながらも他の本で読んだこともあったが,奴隷達がただ気の毒な存在だと思っていたのが,中南米では意外と自由を求めて戦い,コロニーを作っていのは驚きだった.また中国の明清帝国の崩壊がサツマイモやトウモロコシにも原因があるとの論説にも目を見張る思いだ...
植物,病原菌などの情報はなるほどと思いながらも他の本で読んだこともあったが,奴隷達がただ気の毒な存在だと思っていたのが,中南米では意外と自由を求めて戦い,コロニーを作っていのは驚きだった.また中国の明清帝国の崩壊がサツマイモやトウモロコシにも原因があるとの論説にも目を見張る思いだ.また,一人一人にスポットライトを当てた展開は物語を読んでいるようで,とても面白かった.とにかく読み応えのある,グローバルということを本当の意味で考えさせられる本でした.
Posted by
人が動けばそれにくっついてきた病原菌や文化が現地の生命や生態系を壊し、新しい発展をもたらす。グローバル化って怖いんだなって思った。
Posted by
コロンブスによるアメリカ大陸の発見後、世界規模で何がおこったのかについて、最近の研究成果を中心に紹介した本である。 アメリカ大陸から、トマト、じゃがいも、トウモロコシ、チョコレート、タバコなどの作物が世界中に拡がったことは有名だが、事態はそんなレベルものではなかった。 人類の歴史...
コロンブスによるアメリカ大陸の発見後、世界規模で何がおこったのかについて、最近の研究成果を中心に紹介した本である。 アメリカ大陸から、トマト、じゃがいも、トウモロコシ、チョコレート、タバコなどの作物が世界中に拡がったことは有名だが、事態はそんなレベルものではなかった。 人類の歴史について深く考えさせられる。なぜ黒人は奴隷にならされたのか、なぜアメリカ大陸に白人ばかりすんでいるのか。 どの章も読みやすく、驚きに満ちていた。読み終わって呆然とした。この本とペアの1491もおすすめです。 ほぼ全ての人に読んでほしい。サピエンス全史より断然こっちを勧める。
Posted by
タイトルにある1943は、コロンブスが米大陸を「発見」した1492年の翌年であり、これを境に世界が大きく変わったことを象徴する数字。この「発見」を機に、ヨーロッパと北・南アメリカ、アフリカ、アジアの間で様々なもの(植物、動物、病原菌、奴隷、文化、発明品など)が交換される(いわゆる...
タイトルにある1943は、コロンブスが米大陸を「発見」した1492年の翌年であり、これを境に世界が大きく変わったことを象徴する数字。この「発見」を機に、ヨーロッパと北・南アメリカ、アフリカ、アジアの間で様々なもの(植物、動物、病原菌、奴隷、文化、発明品など)が交換される(いわゆるコロンブス交換)ようになり、世界は均一化していく。類似の書籍として「サピエンス全史」とか「銃・病原菌・鉄」などがあるが、本書の特徴は、ヨーロッパが起点になっていること、コロンブス交換が奴隷制や米国の独立戦争、人種差別の意識の起点になっていることを解説する。世界の成り立ちを理解する上でとても参考になる一冊。
Posted by
この本は、科学でもあり、歴史でもあり、非常にエキサイティングで面白い。 1492年にコロンブスが大西洋を越えてから、世界にどういう変化が起こり、現在に至っているのかという壮大な物語を、大陸間の生態系が出会った「コロンブス交換」という観点から解き明かしていく。歴史で習った様々な人...
この本は、科学でもあり、歴史でもあり、非常にエキサイティングで面白い。 1492年にコロンブスが大西洋を越えてから、世界にどういう変化が起こり、現在に至っているのかという壮大な物語を、大陸間の生態系が出会った「コロンブス交換」という観点から解き明かしていく。歴史で習った様々な人間の所業も、病原菌や昆虫、動植物たちの大陸を超えた大移動と、見えないところで密接に関わっている(というより、その上に成り立っている)ということに新鮮な驚きを覚える。 以前に読んだ『銃・病原菌・鉄』もそうだったが、家畜の普及や病原菌の伝播ということが人類の歴史に非常に大きな影響を与えている。「生物多様性の維持」ということについても、改めて考えさせられる。 新しい発見や、新しい検証技術の進歩により、歴史観はどんどん刷新されていく。 そこが面白い。
Posted by
今まで何となく興味があって病原菌や人類学、土壌資源やグローバル経済の本を読んできたが、それぞれの本で聞きかじった知識が本書で結びつき、「世界の在り方」を説明する力になったのを感じた。読書の醍醐味を味わえる一冊。 旧大陸から新大陸に持ち込まれた病原体により、免疫のなかった先住民が...
今まで何となく興味があって病原菌や人類学、土壌資源やグローバル経済の本を読んできたが、それぞれの本で聞きかじった知識が本書で結びつき、「世界の在り方」を説明する力になったのを感じた。読書の醍醐味を味わえる一冊。 旧大陸から新大陸に持ち込まれた病原体により、免疫のなかった先住民が大打撃を受け、スペイン人による侵略が容易になったことは知っていたが、牛や豚、ミミズやミツバチによる生態系への影響や、開拓による蚊の繁殖とそれにともなうマラリアの蔓延、マラリアによる軍隊への影響(病気で命を落とさなくとも高熱による消耗で「戦力」にはならなくなる)は知らなかった。 アジアやアフリカの植民地は第二次大戦後に独立したのに、南米の植民地は第一次大戦前に独立していたことを疑問に思っていたが、労働力としてアフリカから南米に連れてこられた「奴隷」は、それまでイメージしていた「抵抗の意思を失い、慈悲深い主人の恩寵にすがるだけの無力な民」ばかりではなく、アフリカでの出自は王族や軍人だったが「たまたま」戦争に敗北して奴隷として売られた人々もいて、彼ら(彼女ら)が、脱走し、ジャングルに根拠地を作り、逃亡奴隷を匿って勢力を増強し、植民地の補給路を脅かす戦術で食料と交換に武器を入手して抵抗することで、少なくとも一部の地域では「自力で」独立を勝ち得ていたことを知り、納得がいった。 グローバルな経済とは、突き詰めれば「自分たちが住んでいない地域の産物」を交換することであり、その結果世界は「均質新生」という、どこでも同じような風景(生態系)に変わっていく。 インディオやアイルランドやフィリピンの先住民が、「自分たちの風景」を維持してきた農法は、グローバル経済の競争原理に従い、有利な換金作物栽培に置き換えられていく。 「グローバル経済」は環境や伝統を保護する(本来の)政府機能とは相容れることなく、貪欲に目先の利益に従って利益を分配し、環境破壊という負債を現地「だけ」に負わせ、後には不毛の土地が残される。 エントロピー増大による熱的平衡と同様、経済のグローバル化が「必然」であれば、遠からず人類は滅ぶのだろう。
Posted by
1493 チャールズ・C・マン著 動植物などの移動、伝播を重視 2016/3/27付日本経済新聞 朝刊 15世紀末以来、病原菌から原材料や食糧、エネルギー源となる動植物、さらには奴隷を含む人間までが、大陸間を相互に移動・伝播(でんぱ)した。この歴史的事実は、A・クロスビー...
1493 チャールズ・C・マン著 動植物などの移動、伝播を重視 2016/3/27付日本経済新聞 朝刊 15世紀末以来、病原菌から原材料や食糧、エネルギー源となる動植物、さらには奴隷を含む人間までが、大陸間を相互に移動・伝播(でんぱ)した。この歴史的事実は、A・クロスビーの名著『ヨーロッパ帝国主義の謎』以来、「コロンブス交換」として知られている。ヨーロッパはその結果、ジャガイモや砂糖や茶、コーヒー、綿花などを獲得した。 本書は、以後の膨大な研究成果をふまえた、いわばクロスビーの著作の改訂版である。 同時に、それは「コロンブス交換」以前の世界を描いた、自著『1491』の続編でもある。 全体としての著者の議論には、二つの含意がある。ひとつは、コロンブス以前の各大陸には、それぞれに優劣のつけがたい生活文化があったのだということ、つまり、ヨーロッパ中心的な歴史観への警鐘である。 また、「コロンブス交換」以後の動植物の移動と「相互伝播」の重要性を主張する本書は、必然的に資源・エネルギーにかかわる人類学的・生態学的な歴史観の好例となっている。 いまひとつの含意は、「世界の一体化」の起点が、「大航海」時代にある、という主張である。それまでにも、大陸間でこうした「交換」が皆無だったわけではないが、動植物の相互伝播が、プランテーションの展開などをつうじて、関係するすべての社会の構造と生態環境を一変させたのは、「大航海」以後の現象だということである。 西洋諸国の工業化や金融経済の台頭ではなく、「大航海」時代こそが重要だとする点は、世界史的な視点に立つ歴史学のなかでも、同じ生態環境論的な立場のポメランツより、ウォーラーステインに近いといえる。 もっとも、本書は堅苦しい歴史論理を展開しているわけではない。論調は、科学的というよりは、記述的・文学的で、大著にもかかわらず、きわめて読みやすい。 植物を中心にさまざまなモノが扱われているが、白眉というべきは、ゴムノキにかかわる考察であろう。近代の技術革新にとって大きな意味があったことも、経済的に重要だったことも分かっていながら、比較的分析されることの少なかったモノのひとつであるだけに、フィールドワークの成果をふんだんに盛り込んだこの部分の記述は迫力がある。 「世界の一体化」の過程を重視する「グローバル・ヒストリー」や、歴史学と生態環境論との境界領域のあり方を示す、奥深い一書でもある。 原題=1493 (布施由紀子訳、紀伊国屋書店・3600円) ▼著者はジャーナリスト、サイエンスライター。著書に『1491』など。 《評》大阪大学名誉教授 川北 稔
Posted by
- 1