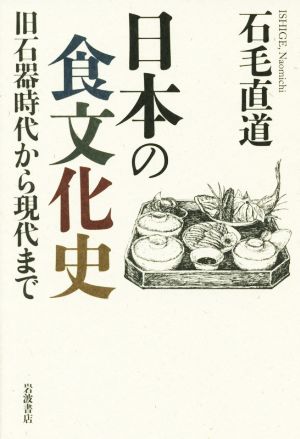日本の食文化史 の商品レビュー
第1部 日本の食文化史(稲作以前;稲作社会の成立;日本的食文化の形成期;変動の時代;伝統的な食文化の完成期;近代における変化) 第2部 日本人の食の文化(食卓で;台所で;外食、料理、飲みもの)
Posted by
11月の日経朝刊の「私の履歴書」は著者の連載。民族学博物館の館長された方。 11月23日の掲載に、魚醤は稲作文化と結びついていて、田んぼで採れた小魚から作ったとあり、吃驚した。 秋田のショッツルとか石川のイシリ、ベトナムのニョク・ナムとか、魚醤は海の民の文化で海の魚から作るものと...
11月の日経朝刊の「私の履歴書」は著者の連載。民族学博物館の館長された方。 11月23日の掲載に、魚醤は稲作文化と結びついていて、田んぼで採れた小魚から作ったとあり、吃驚した。 秋田のショッツルとか石川のイシリ、ベトナムのニョク・ナムとか、魚醤は海の民の文化で海の魚から作るものと思っていた。確かに魚醤に近いナレズシと云えば、琵琶湖の鮒寿司だなと自分の不明を確かめるため、本屋を探して、本書を手に取った。 フランスで出版され、イギリスで海賊出版された本が元になっている。日本人の食文化全史という内容。 じっくり読むと、今までの自分の思い込みに気付かされる。魚醤の東南アジア文化とは別系統に、穀醤の東アジアの文化があり、大宝律令にある醤(ひしお)は大豆が原料のペースト状調味料で、醤油の原型。そして万能調味料、醤油の発明が料理を変えていった。 それと戦乱の世が終わり、刀鍛冶が包丁を作り始め、料理が変わったという。包丁が進化しなかったら、お造りが料理のメインに成らなかったいう考察。 成程、包丁と醤油が無かったら、酢味噌和えで生サカナを食べてたかも。 読み進めて行くうち、あれ、ダシの話がないなあと思ったら、後半にでてきた。家庭料理にダシが使用されるのは江戸時代以降で、明治以降に常用されるようになったとある。割と新しいものという。鰹節や煮干しがあるから、魚醤と繋がるものかと僕は思ってたが、違うらしい。 昔の日本人は、殆どおかずもなく、9割程度の精米の飯をたらふく食べて、ビタミンも摂取していたという。その他にも、お膳やちゃぶ台の話など、知っているようで曖昧なことも多かった。 年末年始に読む本として、良い選択だったと思う。 「魚醤とナレズシ」も探してみようかな。
Posted by
タイトル通り。変わっているのはもともとフランスで出した本の日本向けというところ。とはいえ、日本の食生活は古代から大きく変わってきており今の日本人では知らないことがとても多いことがわかる。 縄文時代は狩猟採集だが、日本は魚の消費が多いのが特徴。また縄文土器は世界最古の土器であり、こ...
タイトル通り。変わっているのはもともとフランスで出した本の日本向けというところ。とはいえ、日本の食生活は古代から大きく変わってきており今の日本人では知らないことがとても多いことがわかる。 縄文時代は狩猟採集だが、日本は魚の消費が多いのが特徴。また縄文土器は世界最古の土器であり、これで煮たりしていたようだ。中国韓国から稲作がやってきて特に狩猟採集では条件が不利で遅れていた西日本で広まり、むしろそちらが政治文化の中心になる。食文化も中国から輸入されているが、さじはあまり普及しなかった。また日本の特徴としては一人一膳であり、数多くのおかずが貴族の食卓では出ていた。鎌倉時代以降は華美さは抑制され、高盛飯を限定されたおかずで出すというスタイルになる。また、仏教の普及と共に肉食が魚に限定されるようになり、明治の初めでもタンパク質は半分は米から摂取していた。欧米のパン食はタンパク質が少なくバターやチーズなどで摂取していた。とはいえ日本の肉食も薬食いなどと称して生きながらえてきた。日本の食は素材の味をできるだけ手を加えず、そのまま楽しむことが極意とされ、それは他の国とは異なる。著者はその点において、日本食が現在のように世界で受け入れられることになるとは思っていなかったと述べている。
Posted by
石毛さんは食文化の専門家で、民博の館長もやった人だ。ぼくはこれまでも石毛さんの本を何冊か読んで来た。本書は石毛さんが本来外国人のために書いた日本食文化史を日本語に翻訳しなおしたものだ。翻訳とはいえ、その文章は石毛さんのものでとても読みやすい。翻訳に際し、日本人には自明の部分は削除...
石毛さんは食文化の専門家で、民博の館長もやった人だ。ぼくはこれまでも石毛さんの本を何冊か読んで来た。本書は石毛さんが本来外国人のために書いた日本食文化史を日本語に翻訳しなおしたものだ。翻訳とはいえ、その文章は石毛さんのものでとても読みやすい。翻訳に際し、日本人には自明の部分は削除したそうだが、ぼくたちが当たり前と思っていることがいつから起こったのか等、はっとする記述がいたるところで見られる。たとえば、日本人は古来玄米を食べていたと言われるが、今の健康食品店で売っているような玄米を食べていたわけではないとか、昔の農民は米を食べられなかったというのはウソで、雑穀と合わせて食べたのだとか(これは食物史でもよく取り上げられる)、日本人の朝昼夕三食はいつからはじまったのかとか、外食産業はいつから広まったのか等々どこを開いても面白い。また、米は主食としてすぐれていることが強調され、米とパンは同時に主食になりえないこと、パンを主食にした場合副食に和風料理はこないこと等が問題にされる。また、米の位置は酒が代わりうるが、この場合酒と米をいっしょにとるのは本来のやりかたでないことが問題にされる。ぼくはお酒を飲みながらご飯も食べたい方なので、伝統的な食事法からは邪道ということになる。その他とんかつやカレー拉麺が日本料理になっていく過程等興味ある事実が満載である。なお、p270の「シャブシャブ」の中国語は「刷シュワ(羊肉)」ではなく、三水編に「刷」シュワンであろう。
Posted by
- 1