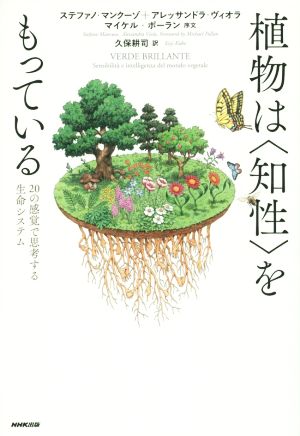植物は<知性>をもっている の商品レビュー
植物に対しては動物と違って動かない、動物より下等であるといったイメージを無意識に持たれていないでしょうか? しかしながら ・動物は体を半分にされると絶命してしまうが、植物は残された枝葉より再生可能である ・地球上のたんぱく質の99%以上を占めて居る ことを鑑みると植物には動物に勝...
植物に対しては動物と違って動かない、動物より下等であるといったイメージを無意識に持たれていないでしょうか? しかしながら ・動物は体を半分にされると絶命してしまうが、植物は残された枝葉より再生可能である ・地球上のたんぱく質の99%以上を占めて居る ことを鑑みると植物には動物に勝るとも劣らない知性を持ち合わせており、地球支配をされているとも言えるのではないか。 コペルニクス的転回を促される一冊。
Posted by
筆者によれば、植物には知性があるという。 それは、知性を問題を解決する能力と定義した場合である。 植物は、予測、選択、学習、記憶する能力や五感を持ち、他の植物、動物、昆虫と化学物質を使いコミュニケーションをし、親族と他者を区別することもできると、様々な例を用い説明している。 ...
筆者によれば、植物には知性があるという。 それは、知性を問題を解決する能力と定義した場合である。 植物は、予測、選択、学習、記憶する能力や五感を持ち、他の植物、動物、昆虫と化学物質を使いコミュニケーションをし、親族と他者を区別することもできると、様々な例を用い説明している。 前半部分は、人が地球上で一番賢く、優れているという思い込みから、植物を軽んじ、知性を持つという植物の生態ですら否定してきた人の歴史が語られている。 筆者が子供の頃に触れたSF小説(映画)では、エイリアンの種族が地球にやってきたが人間の動きを感知できないために、人間が自力で動こうとしないと結論づけ、人間を搾取したというストーリーが序文で紹介されており 本書を読むと植物が人とは異なる生命体だと捉えれば、植物に対して理解が進むように思った。 スイスでは、植物を好き勝手に扱ってはならず、植物を無差別に殺すことは倫理的に正答できないと植物の権利を認めたという。どうやって、その権利を守るのかは疑問だが、そういう決定をしたということは、植物は人の所有物ではなく、異なる生き物であると認めたということだ。 植物が様々な能力を備えていることを知ることができた。 そして、そもそも”知性”とは何かということから考えさせられる本だと感じた。 興味深かったのは以下の部分。 人間の体の器官が一つずつしかなく取り替えがきかないが植物は、体を分割可能なパーツを組み合わせてできており、体の90%を失っても、人の脳ともいえる根が生きていれば再生できる。 植物に影響を与える音楽はジャンルではなく周波数。 高周波数が成長を抑え、低周波数が発芽、成長に良い影響を与える。植物の”耳”は、地面の音の振動から情報を得ていて、自分でもクリッキング音を出している。 液体を上へ運ぶシステムは、木質(導管)で、上から下へ光合成で作った糖を運ぶ場合は師菅部を使い、人の血管に似ている。 花粉の運び屋としてコウモリを利用する植物は、コウモリの発する超音波を反射するためにパラボラアンテナのような丸い葉っぱをしている。 花が腐った動物の匂いを発して、くろばえを誘き寄せ、花粉を運ばせる植物もいる。 根端では、ニューロンと似た電気信号を使い、重力、湿度、磁場、光、圧力、化学物質、有毒物質、音の振動、酸素、二酸化炭素の有無などを感知している。
Posted by
知性とは何だろうか。著者は問題を解決する力だという。植物は人が持つ五感なんてもんじゃない。重力を、磁場を、化学物質を感知するなど20の感覚をフル回転させて、地球上で生き抜いているのだ。
Posted by
読んだ直後は植物の知性は人間と違うな、面白いなというくらいだったが、時間が経つにつれて、これはある種生き方に革命的な視点転換を示す本なのではと思い至った。今いる環境から抜け出したいけれど、残念ながらそこで生きざるを得ない(動けない)という人に、オルタナティブを提示するかもしれない...
読んだ直後は植物の知性は人間と違うな、面白いなというくらいだったが、時間が経つにつれて、これはある種生き方に革命的な視点転換を示す本なのではと思い至った。今いる環境から抜け出したいけれど、残念ながらそこで生きざるを得ない(動けない)という人に、オルタナティブを提示するかもしれない。
Posted by
この本をきっかけに植物が大好きになったし、植物はとても興味深いと思った。植物どうしのコミュニケーションだったり、植物と動物のコミュニケーションはとても興味深く、植物の生き方に感心した。
Posted by
なかなか刺激的なタイトルで、ちょっと疑似科学的な内容を期待したのだが(それはそれで好物なので)、いたって真面目?な本だった。 要は、「知性」をどう捉えるか、という話なんだと思う。ぼくらの文脈で知性というと、ある事象をどう解釈するかとか、それに基づいてどう判断を下すかとか、比較的短...
なかなか刺激的なタイトルで、ちょっと疑似科学的な内容を期待したのだが(それはそれで好物なので)、いたって真面目?な本だった。 要は、「知性」をどう捉えるか、という話なんだと思う。ぼくらの文脈で知性というと、ある事象をどう解釈するかとか、それに基づいてどう判断を下すかとか、比較的短い時間軸での知的能力を示すと思うのだが、本書で扱われる植物の「知性」は、植物が進化する過程で手に入れた各種の適応能力を示しているようだ。動物でいえば、たとえば免疫反応みたいなものを「知性」としているようで、確かにそれを「知性」とするなら、植物は明らかに知性を持っている。 その辺の違和感を別にすれば、なかなかおもしろかった。 基本的に動くことのできない植物は、体をユニット構造、つまり代替の効く部品から作り上げた、という見方はたしかにそうだ、と思う。動物は頭がもげたら生きていけないし、腕が取れたら(普通は)生えてこないので不便だ。しかし植物はそうではなく、草食動物に葉っぱを少し食べられたくらいでは枯れたりしない。そういう植物がいるから我々動物も生きていける、というのも全くその通りだ。 本書の頭の方で、そういう植物の研究が、動物の研究に比較して冷遇される傾向がある、という愚痴が出てくる。なるほどそうかもしれない。
Posted by
植物が、人間や動物と同じように動き、感じ、眠り、コミュニケーションを取るなど、知性と定義されるものを持っていることを提言した本。 植物が地球上の生物の総重量のうち、多細胞生物の99パーセントを占めながらも、思い上がった人間が「我々こそが地球の支配者である」と思うようになった原...
植物が、人間や動物と同じように動き、感じ、眠り、コミュニケーションを取るなど、知性と定義されるものを持っていることを提言した本。 植物が地球上の生物の総重量のうち、多細胞生物の99パーセントを占めながらも、思い上がった人間が「我々こそが地球の支配者である」と思うようになった原因を探るところから始まるのは痛快だった。そして植物が動物と同じような知性を持っている点とともに、人間が「我々こそが地球の支配者である」と考える上での矛盾点を挙げていく。「人間は、自分と異なるタイプの知性を認識することができない」から植物に知性を認めることが出来ないという説から、「植物の知性を研究すれば、私たち人間にとって、自分たちと異なる方法で思考する生命システムを理解するのが、どれほど難しいことかがわかる」と言い切ってしまう。 そもそもこの本は、自分自身の「植物も、動物と同じように地球上に生きる生き物だから、動物と区別するのはおかしいのではないか?」という疑問に、ある意味での正しさを求めて読んだのだが、やっぱり読んで良かったと思えた。文章も大変読みやすく、説明も分かりやすかった。
Posted by
マンクーゾさんの本の一冊目。植物の「知力」を論じた本としては、のほうが、論理的な抑制の効かせ方という点で、「植物はそこまで知っている」の方が僕は好き。 でも、マンクーゾの情熱とか、実際へのアウトリーチとか、好ましいのも確か。そういう意味では「未来を知っている」の方が、オリジナリテ...
マンクーゾさんの本の一冊目。植物の「知力」を論じた本としては、のほうが、論理的な抑制の効かせ方という点で、「植物はそこまで知っている」の方が僕は好き。 でも、マンクーゾの情熱とか、実際へのアウトリーチとか、好ましいのも確か。そういう意味では「未来を知っている」の方が、オリジナリティが高いかな。
Posted by
図書館本。 植物に知性がある事を様々な視点から考察している。 著書によると我々動物は5感だが、植物は20もの感覚があると言う。 特に興味深かったのが視覚だろうか。朝顔などの例で言えば、つるが支柱を探し伸びていくのは、明らかに周りが見えていないとできない事。動物のように光の反射から...
図書館本。 植物に知性がある事を様々な視点から考察している。 著書によると我々動物は5感だが、植物は20もの感覚があると言う。 特に興味深かったのが視覚だろうか。朝顔などの例で言えば、つるが支柱を探し伸びていくのは、明らかに周りが見えていないとできない事。動物のように光の反射から像を結びのではなく、電磁波などの音波で感じているのかも知れないが、これは我々動物で言う視覚と言っていい事だと思う。 他には根っこの先、根端は情報センターであり、進む方向を決めるべく水分の有無や障害物など、沢山の情報を処理している。
Posted by
結局、移動を選んだのが動物、定住を選んだのが植物。一見、動物の方が偉いように見えるが、植物が消え去ったら人間の生活は持たない。一方で動物が消えたら植物はこれまで動物に奪われていた領土を奪い返し、わずか数年で完全に取り戻すに違いない。 コペルニクス革命以前、地球は宇宙の中心にあり...
結局、移動を選んだのが動物、定住を選んだのが植物。一見、動物の方が偉いように見えるが、植物が消え去ったら人間の生活は持たない。一方で動物が消えたら植物はこれまで動物に奪われていた領土を奪い返し、わずか数年で完全に取り戻すに違いない。 コペルニクス革命以前、地球は宇宙の中心にあり、すべての星々が地球の周りを回っていると考えられ、人間中心の考え方で捉えられていたわけだが、現在の生物学もコペルニクス革命前にあるといっていいということで、光を感じる視覚や、嗅覚を使った植物同士のコミュニケーションについて語られる。 緑の多い街は犯罪が少ないという事実もいい。なぜかは分からないが感覚的に分かるし、とりあえず、家に緑は増やしておきたいと思った。
Posted by